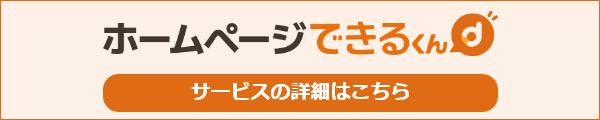お役立ち情報
サイト費用の相場は?初期やランニングコストの内訳などを解説

「ホームページ制作の費用って実際いくらかかるの?」「見積もりを取ったら思っていた金額と全然違った」そんな不安を抱えていませんか。特に中小企業の経営者やマーケティング担当者にとって、限られた予算の中でどこまで投資すべきか判断するのは簡単ではありません。
しかし、サイト制作の費用構造を理解すれば、無駄な出費を避けながら効果的な投資が可能になります。この記事では、初期費用から運用コストまでの内訳を詳しく解説。費用を抑えながら成果を出すための実践的なポイントをお伝えします。
\月額1,900円〜!高品質のHPを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/
サイト制作にかかる費用の全体像
サイト制作を検討する際、まず理解しておきたいのが費用の全体構造です。多くの方が初期費用だけに目が行きがちですが、実はサイト運営には継続的な費用も発生します。
初期費用とは、サイトを立ち上げるまでに必要な一時的な費用のことを指します。一方で運用費用は、サイト公開後に継続的にかかるランニングコストです。この両方を把握することで、予算計画が立てやすくなるでしょう。
費用の内訳と相場一覧(初期費用・運用費用)
サイト制作の初期費用は、複数の要素から構成されています。それぞれの項目がどのような役割を持ち、なぜその金額になるのかを見ていきましょう。
企画・ディレクション費
企画・ディレクション費は、プロジェクト全体の設計と管理にかかる費用です。要件定義やサイト構成の策定、スケジュール管理などが含まれます。
相場は全体費用の15~20%程度が一般的ですが、プロジェクトの複雑さによって変動します。中小企業向けの案件では5万円から20万円程度が目安となるでしょう。
デザイン費
デザイン費は、サイトの見た目や使いやすさを決める重要な要素。費用はトップページのデザインで5万円から15万円、下層ページは1ページあたり2万円から5万円が相場となっています。
テンプレートを活用すれば大幅にコストを削減できます。ただし、ブランドイメージを重視する場合はオリジナルデザインへの投資も検討すべきでしょう。
コーディング費
デザインをWebページとして実装する作業がコーディングです。HTML、CSS、JavaScriptなどを使用してブラウザで表示できる形にします。
ページ数や実装する機能の複雑さによって費用は変わりますが、5ページ程度の標準的なサイトなら10万円から30万円が相場です。レスポンシブ対応(スマホ対応)も含まれることが一般的になっています。
システム開発費
問い合わせフォームや会員登録機能など、動的な機能を実装する際に発生する費用です。既存のプラグインやサービスを活用すれば数万円で済みますが、独自開発となると数十万円以上かかることもあります。
中小企業の場合、まずは最小限の機能から始めて段階的に拡張していく方法がおすすめです。
コンテンツ制作費
サイトに掲載する文章や画像、動画などの制作費用です。自社で用意すれば費用はかかりません。ただし、プロのライターやカメラマンに依頼する場合は別途費用が発生します。
ライティングは1ページあたり1万円から3万円、写真撮影は半日で3万円から10万円程度が相場となっています。
SEO対策費
検索エンジンで上位表示されるための対策費用です。基本的なSEO設定は制作費に含まれることが多いです。ただし、本格的な対策を行う場合は月額5万円から20万円程度の費用がかかります。
予算に余裕がない場合は最初から高額なSEO対策に投資するよりも、コンテンツを充実させることに注力する方が費用対効果は高いでしょう。
サイト制作にかかる初期費用の内訳・相場
| サイト規模 | 初期費用の相場 | 備考 |
| 小規模企業サイト | 20万円~50万円 | 基本的な企業情報とお問い合わせ機能など |
| 中規模サイト | 50万円~100万円 | より充実したコンテンツと機能 |
| 大規模サイト | 100万円以上 | 複雑な機能や多数のページを含む |
初期費用の総額は、サイトの規模や要求される品質によって大きく異なります。小規模な企業サイトであれば20万円から50万円、中規模なら50万円から100万円、大規模サイトでは100万円以上が相場です。
ホームページできるくんのような効率的なサービスを利用すれば、品質を保ちながら費用を抑えることも可能になります。重要なのは、自社の目的に合った適切な投資額を見極めることです。
サイト公開後にかかる運用費用の内訳・相場
サイトは作って終わりではありません。公開後も様々な運用費用が発生ことを覚えておきましょう。運用費用を考慮しないと、予算オーバーになる可能性があるため注意が必要です。
ドメイン費用
ドメインは、インターネット上の住所のようなもの。「.com」や「.jp」などの種類によって費用は異なりますが、年間1,000円から5,000円程度が一般的です。
企業の信頼性を高めたい場合は「.co.jp」ドメインがおすすめですが、年間5,000円から1万円とやや高めになります。
サーバー費用
サイトのデータを保管し、インターネットに公開するためのサーバー費用です。共用サーバーなら月額500円から2,000円程度で利用できます。
アクセス数が多い場合や、表示速度を重視する場合は、月額3,000円から1万円程度の上位プランを検討しましょう。
SSL証明書費用
サイトのセキュリティを確保するSSL証明書の費用です。最近では無料のSSL証明書も普及していますが、ECサイトなど高いセキュリティが求められる場合は有料版(年間1万円から5万円)の導入も検討すべきでしょう。
保守・管理費
サイトの定期的なメンテナンスやトラブル対応にかかる費用です。制作会社に依頼する場合、月額1万円から3万円程度が相場となっています。
自社で対応できる部分は内製化し、技術的な部分のみ外注することでコストを抑えられます。
更新作業費
コンテンツの追加や修正にかかる費用です。CMSを導入していれば自社で更新できますが、外注する場合は1回あたり5,000円から2万円程度かかります。
更新頻度が高い場合は、保守契約に含めてもらう方が割安になることもあります。
マーケティング費用
サイトへの集客やコンバージョン率向上のための費用です。リスティング広告なら月額3万円から、SNS運用代行なら月額5万円から20万円程度が相場となっています。
最初は自社で運用を始め、成果が見えてきたら外注を検討するという段階的なアプローチがおすすめです。
運用費用の一覧表
運用費用を表にまとめると以下のようになります。年間の予算計画を立てる際の参考にしてください。
| 費用項目 | 金額 | 支払頻度 | 年間費用(目安) |
| ドメイン費用 | 1,000円~1万円 | 年間 | 1,000円~1万円 |
| サーバー費用 | 500円~1万円 | 月額 | 6,000円~12万円 |
| SSL証明書 | 無料~5万円 | 年間 | 0円~5万円 |
| 保守・管理費 | 1万円~3万円 | 月額 | 12万円~36万円 |
| 更新作業費 | 5,000円~2万円 | 1回あたり | 頻度により変動 |
| マーケティング費用 | 3万円~20万円 | 月額 | 36万円~240万円 |
これらを合計すると、最低でも年間10万円程度、本格的に運用する場合は年間100万円以上の予算を見込んでおく必要があります。
法人サイト・個人サイト・ECサイトの費用比較
サイトの種類によって必要な機能や規模が異なるため、費用にも大きな差が生まれます。ここでは、それぞれの特徴と費用相場を比較していきます。
法人サイト(企業サイト)の場合
法人サイトは企業の顔となる重要な存在です。会社概要、サービス紹介、お問い合わせフォームなど基本的な機能に加え、信頼性を演出するデザインが求められます。
中小企業の場合、30万円から100万円程度が相場ですが、ページ数や機能によって変動します。ホームページできるくんのようなサービスを利用すれば、月額1,900円から高品質なサイトを制作することも可能です。
個人サイト(個人ブログ・ポートフォリオ)の場合
個人サイトは比較的シンプルな構成で十分なケースが多く、費用も抑えやすい傾向にあります。自作なら年間1万円程度のランニングコストのみで運営可能です。
プロに依頼する場合でも、10万円から30万円程度で十分なクオリティのサイトが作れるでしょう。ただし、ポートフォリオサイトなど見た目重視の場合は、デザインに投資する価値があります。
ECサイト(ネットショップ)の場合
ECサイトは決済機能や在庫管理システムなど、複雑な機能が必要になるため費用も高額になりがちです。フルスクラッチで開発する場合、500万円以上かかることも珍しくありません。
しかし、ShopifyやBASEなどのECプラットフォームを利用すれば、月額数千円から本格的なネットショップを開設できます。中小企業の場合、まずはこうしたサービスから始めることをおすすめします。
【種類別】サイトの費用相場一覧
| サイト種類 | 費用相場 | 制作方法・備考 |
| 法人サイト | 30万円~100万円 | 中小企業向け |
| 個人サイト | 0円~30万円 | 自作または外注 |
| ECサイト | 10万円~500万円以上 | プラットフォーム利用またはフルスクラッチ |
これらの相場を参考に、自社の目的と予算に合った選択をすることが大切です。
まず知っておきたい「見積もりの考え方」
サイト制作の見積もりは、単純に金額だけを見て判断してはいけません。その内訳と根拠を理解することで、適正価格かどうかを判断できるようになります。
見積もりを決定する要素
見積もり金額は「作業内容×工数×単価」で算出されます。ページ数が多い、デザインが複雑、特殊な機能が必要といった要素があれば、それだけ工数が増えて費用も上がります。
また、制作会社の規模や実績によっても単価は変わります。大手は高額ですが品質保証があり、フリーランスは安価ですがリスクもあるという特徴を理解しておきましょう。
見積もりを依頼するポイント(発注側チェックリスト/契約書で確認すべき事項)
見積もりを依頼する際は、以下のポイントを明確にしておくことが重要です。
まず、サイトの目的と目標を具体的に伝えましょう。次に、必要なページ数と機能をリストアップします。そして、予算の上限を正直に伝えることで、現実的な提案を受けられます。
契約書では、納期、修正回数の上限、追加費用の条件、著作権の帰属、保守サポートの範囲を必ず確認してください。曖昧な部分を残すとトラブルの原因になります。
\月額1,900円〜!高品質のHPを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/
サイト制作方法別|費用と特徴を徹底比較

サイト制作には大きく分けて3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットと費用を比較して、最適な方法を選びましょう。
①自作(ノーコード/WordPress)の場合
技術的な知識がなくても、最近では様々なツールを使ってサイトを自作できるようになりました。費用を最も抑えられる方法ですが、時間と労力がかかることを覚悟する必要があります。
自作の費用相場
自作の場合、必要なのはドメイン代(年間1,000円~5,000円)とサーバー代(月額500円~2,000円)のみです。WordPressなら無料で利用でき、有料テーマを購入しても1万円~3万円程度で済みます。
自作のメリット
最大のメリットは費用の安さです。また、自分のペースで作業でき、修正や更新も自由に行えます。WordPressなら豊富なプラグインを活用して機能拡張も可能です。
自作のデメリット
時間がかかることが最大のデメリットです。また、デザインや機能面でプロには及ばず、トラブル対応も自己責任となります。SEO対策やセキュリティ面での不安も残るでしょう。
②フリーランスに依頼する場合
個人で活動するWebデザイナーやエンジニアに依頼する方法です。制作会社より安価で、柔軟な対応が期待できます。
フリーランスに依頼する費用相場
小規模サイトなら10万円~30万円、中規模でも30万円~50万円程度が相場です。制作会社の半額程度で依頼できることが多いですが、スキルレベルによって品質にばらつきがあります。
フリーランスに依頼するメリット
直接やり取りができるため、要望が伝わりやすく、スピーディーな対応が期待できます。また、制作会社より安価で、交渉次第では柔軟な料金設定も可能です。
フリーランスに依頼するデメリット
個人のため、病気やトラブルで作業が止まるリスクがあります。また、実績や信頼性の見極めが難しく、納品後のサポートが不十分な場合もあるでしょう。
③制作会社に依頼する場合
プロの制作会社に依頼する方法です。費用は高額ですが、品質とサポート体制は最も充実しています。
制作会社の費用相場
中小企業向けサイトで50万円~150万円、大規模サイトでは200万円以上が相場です。大手制作会社になると、さらに高額になることもあります。
制作会社のメリット
チーム体制で対応するため、デザイン、コーディング、マーケティングなど各分野の専門家が関わります。納期の信頼性も高く、アフターサポートも充実しています。
制作会社のデメリット
費用が高額なことが最大のデメリットです。また、大きな組織のため意思決定に時間がかかり、細かい要望への対応が遅れることもあります。
<h4>制作会社を選ぶポイント(ホームページできるくんならではの選び方レポート)</h4>
制作会社を選ぶ際は、実績、費用、サポート体制、納期を総合的に判断しましょう。ホームページできるくんのように、中小企業に特化したサービスなら、適正価格で質の高いサイトを短期間で制作できます。
\月額1,900円〜!高品質のHPを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/
サイト運用にかかる継続コストも要チェック
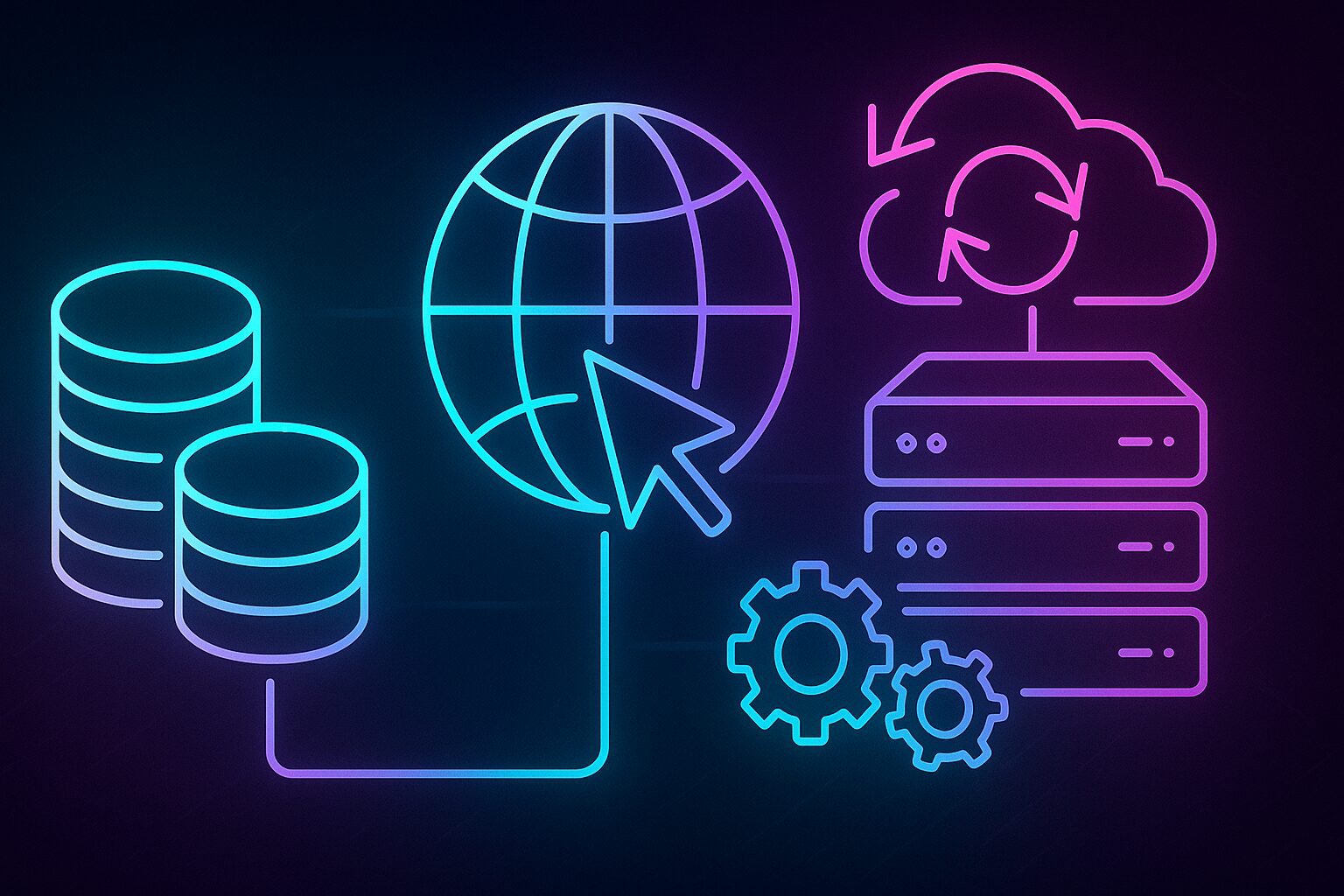
サイト制作後の運用コストは、長期的に見ると初期費用を上回ることもあります。計画的な予算配分が成功の鍵となります。
ドメイン・サーバー代(月額・年間)
ドメインとサーバーは、サイト運営に必須の固定費です。これらの選び方次第で、年間コストが大きく変わってきます。
【種類別】ドメイン費用一覧
| ドメイン種類 | 年間費用 | 特徴・用途 |
| .com | 1,000円~1,500円 | 最も一般的な商用ドメイン |
| .jp | 3,000円~4,000円 | 日本を表すドメイン |
| .co.jp | 5,000円~1万円 | 日本企業向け(法人登記が必要) |
| .net | 1,200円~1,800円 | ネットワーク関連で使われることが多い |
企業の信頼性を重視するなら.co.jpがおすすめですが、コストを抑えたい場合は.comでも十分です。
【種類別】サーバー費用一覧
| サーバー種類 | 月額費用 | 料金体系 | 適している用途 |
| 共用サーバー | 500円~3,000円 | 定額制 | 小規模サイト、個人ブログ |
| VPS | 2,000円~1万円 | 定額制 | 中規模サイト、複数サイト運営 |
| 専用サーバー | 1万円~5万円 | 定額制 | 大規模サイト、高トラフィック |
| クラウドサーバー | 3,000円~ | 従量課金制 | 柔軟なリソース調整が必要なサイト |
中小企業なら共用サーバーで十分ですが、アクセス数が増えてきたらVPSへの移行を検討しましょう。
保守・管理・更新の外注費
サイトの安定運用には、定期的なメンテナンスが欠かせません。自社で対応が難しい場合は、外注を検討する必要があります。
サイトの監視とトラブル対応
24時間365日の監視体制を外注する場合、月額2万円~5万円程度かかります。ただし、中小企業の場合は平日対応のみの契約で十分なケースが多いでしょう。
ソフトウェアのアップデート
WordPressやプラグインのアップデートは、セキュリティ維持に不可欠です。月額5,000円~15,000円程度で対応してもらえます。
定期バックアップ
データの定期バックアップは、万が一のトラブルに備えて必須です。自動バックアップサービスなら月額1,000円~3,000円程度で利用できます。
テキスト修正・画像差し替え
軽微な修正作業は、1回5,000円~1万円が相場です。月に複数回依頼する場合は、保守契約に含めた方が割安になります。
SEO対策やマーケティングにかかる費用
サイトを作っただけでは集客はできません。継続的なマーケティング投資が必要になります。
SEOの費用
本格的なSEO対策を外注する場合、月額5万円~20万円程度かかります。ただし、最初は自社でコンテンツを充実させることから始めるのがおすすめです。
リスティング広告の費用
Google広告やYahoo!広告の運用費は、月額3万円~が一般的です。運用代行を依頼する場合は、広告費の20%程度の手数料が追加でかかります。
コンテンツ制作の費用
ブログ記事の外注は1本5,000円~3万円が相場です。質の高いコンテンツは資産になるため、計画的な投資をおすすめします。
\月額1,900円〜!高品質のホームページを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/
費用を抑える5つのコツと注意点

限られた予算で最大の効果を得るには、戦略的なコスト削減が必要です。ここでは実践的な5つのコツを紹介します。
目的を明確にして「必要な機能」を絞る
「あれもこれも」と機能を詰め込むと、費用は際限なく膨らみます。まずは最小限の機能でスタートし、成果を見ながら段階的に拡張していく方法が賢明です。
例えば、最初は5ページ程度のシンプルな構成で始め、アクセス解析を見ながら必要なページを追加していけば、無駄な投資を避けられます。
テンプレートやCMSを活用する(ノーコード/クラウド)
オリジナルデザインにこだわらなければ、テンプレートの活用で大幅にコストダウンできます。最近のテンプレートは品質が高く、カスタマイズ次第でオリジナリティも出せます。
WordPressなどのCMSを使えば、更新作業も自社で行えるため、運用コストも削減できるでしょう。
相見積もりをとって価格と内容を比較
必ず3社以上から見積もりを取り、価格だけでなく提案内容も比較しましょう。安さだけで選ぶと後悔することもあるため、コストパフォーマンスを重視することが大切です。
補助金・助成金の活用(中小企業向け支援制度紹介)
IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、ホームページ制作に使える補助金があります。最大で費用の1/2から3/4が補助される場合もあるため、積極的に活用しましょう。
申請には手間がかかりますが、数十万円の補助を受けられる可能性があるため、検討する価値は十分にあります。
「安さ重視」で失敗しないために(失敗実例+チェックリスト)
極端に安い業者は、品質やサポートに問題がある可能性があります。過去の実績、契約内容、アフターサポートの有無を必ず確認してください。
失敗を避けるために、実績の確認、見積もり内訳の明確さ、納期の現実性、修正対応の範囲、著作権の扱いを確認することが重要です。
\月額1,900円〜!高品質のHPを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/
よくある質問(FAQ)
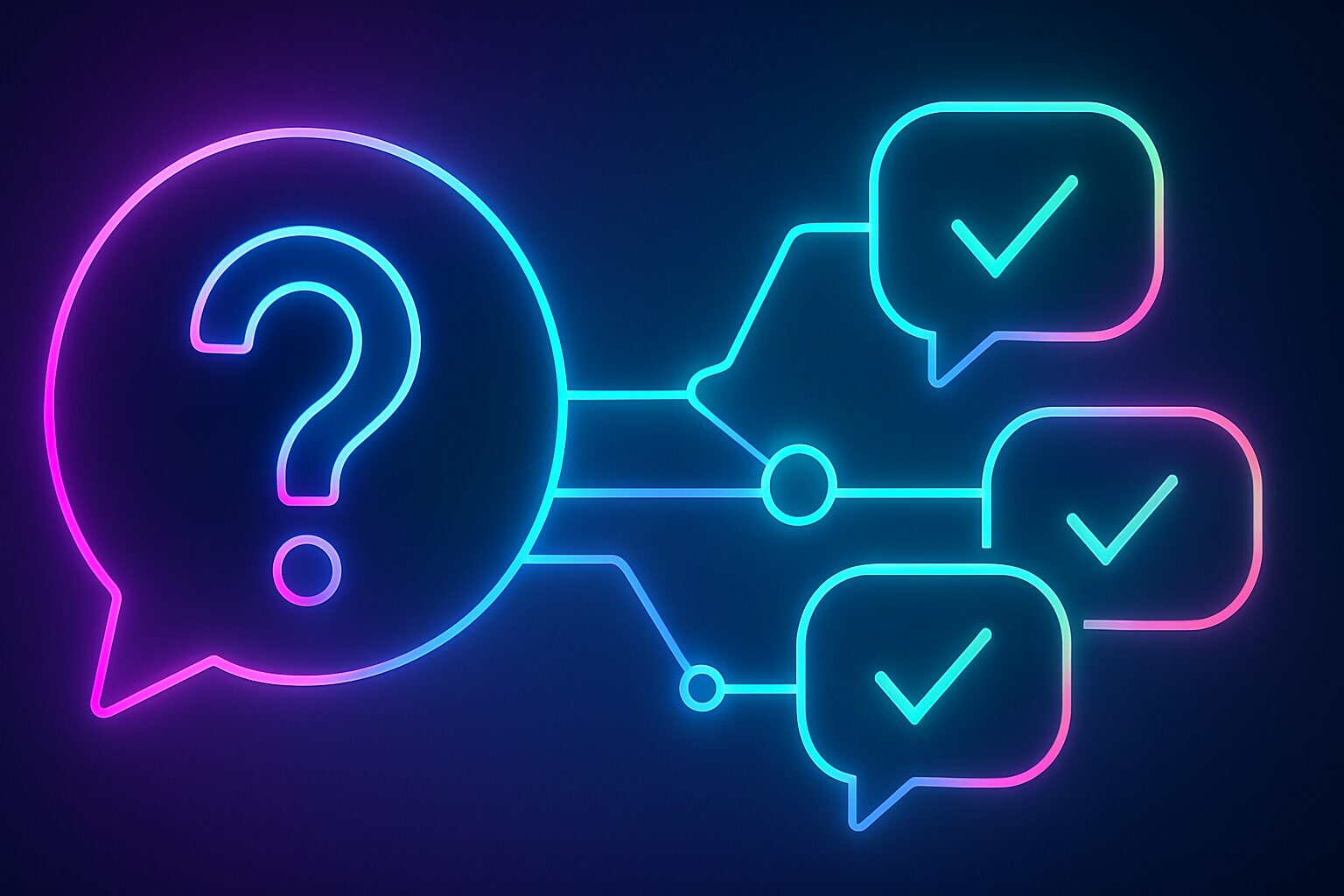
サイト制作に関してよく寄せられる質問にお答えします。疑問や不安を解消して、安心して制作を進めましょう。
サイト制作の初期費用は一括?分割?
回答:多くの制作会社では、着手時に50%、納品時に50%という分割払いが一般的です。ホームページできるくんのように、月額制で初期費用を抑えられるサービスもあります。
資金繰りに不安がある場合は、分割払いやリース契約が可能か事前に確認しましょう。
途中で仕様変更すると費用は増える?
回答:基本的に仕様変更は追加費用が発生します。特にデザイン確定後の大幅な変更は、作業のやり直しになるため高額になりがちです。
変更を最小限に抑えるため、要件定義の段階でしっかりと内容を詰めておくことが重要です。
無料でサイトを作るのはアリ?
回答:個人の趣味サイトなら無料サービスでも問題ありませんが、ビジネス用途では避けるべきです。独自ドメインが使えない、広告が表示される、サービス終了のリスクがあるなど、デメリットが多すぎます。
最低限、独自ドメインとレンタルサーバーは確保することをおすすめします。
保守契約は必須?
必須ではありませんが、トラブル時の対応やセキュリティ更新を考えると、契約しておいた方が安心です。月額1万円程度の保守契約で、大きなトラブルを未然に防げる可能性があります。
自社で技術者を抱えている場合を除き、最低限の保守契約は結んでおくことをおすすめします。
自分に合ったサイト制作方法と費用感を把握しよう
サイト制作の費用は、目的や規模によって大きく異なりますが、中小企業なら30万円から100万円程度を目安に考えると良いでしょう。初期費用だけでなく、年間10万円から50万円程度の運用コストも忘れずに予算計画に組み込んでください。
費用を抑えたい場合は、テンプレートの活用や段階的な機能追加、補助金の活用などを検討しましょう。ただし、安さだけを追求すると品質面で問題が生じる可能性もあるため、バランスを考えることが大切です。
ホームページできるくんなら、月額1,900円から高品質なサイトを最短1ヶ月で納品可能です。中小企業に特化したノウハウで、費用対効果の高いサイト制作をサポートします。まずは無料相談で、あなたのビジネスに最適なプランをご提案させていただきます。
\月額1,900円〜!高品質のHPを制作したい方は、ホームページできるくんにご相談ください/