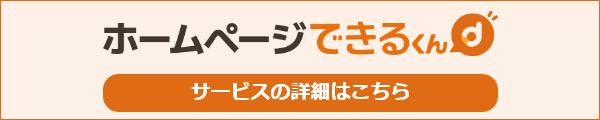お役立ち情報
会社のWebサイトはどう作る?制作や運用方法、費用相場を解説

「会社のWebサイトを作りたいけど、何から始めればいいのかわからない…」「制作費用はどのくらいかかるの?」「本当に必要なの?」と悩んでいませんか?
インターネット上の情報があふれる現代では、会社のWebサイトは「あって当たり前」の時代になりました。しかし、Webに詳しくない方にとっては、何から手をつければよいのか、どんな準備が必要なのか、悩みは尽きないでしょう。
この記事では、会社のWebサイトを作ろうと考えている中小企業の方に向けて、基本的な知識から制作方法、費用相場、運用方法まで、初心者でもわかりやすく解説します。この記事を読めば、自社に最適なWebサイト作りの第一歩を踏み出せるはずです。
\会社のWebサイト制作を検討中の方は月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを提供するホームページできるくんにご相談ください!/
会社のWebサイトはなぜ必要?作る目的とメリット
今や会社のWebサイト(コーポレートサイト)は、現代のビジネスに欠かせません。なぜ必要なのか、そのメリットについて具体的に見ていきましょう。
企業の信頼性・ブランディングを高める
会社のWebサイトは、企業の「顔」とも言える存在です。潜在顧客や取引先が初めて接点を持つ場合、多くの人はまずインターネットで検索します。この時にしっかりとしたWebサイトがあるかどうかで、企業の信頼性の印象が大きく変わります。
購入や取引を検討する前に、多くの消費者がその企業のWebサイトを確認すると言われています。つまり、Webサイトの有無や質が、企業の第一印象を大きく左右するのです。
また、Webサイトは自社の理念やビジョン、強みを伝える重要な手段でもあります。独自のブランドイメージを構築し、他社との差別化を図る上でも非常に効果的です。
採用活動に効果的
人材採用においても、Webサイトの存在は大きな影響力を持ちます。求職者の多くは、応募する企業について事前にリサーチします。このとき、魅力的なWebサイトがあれば、企業文化や雰囲気を伝えることができ、ミスマッチを減らす効果も期待できます。
ここで重要なのが、コーポレートサイトと採用サイトの違いです。コーポレートサイトは企業全体の情報を総合的に伝えるのに対し、採用サイトは求職者向けに特化したコンテンツを提供します。規模や予算に応じて、コーポレートサイト内に採用ページを設ける方法と、独立した採用サイトを構築する方法があります。どちらの場合も、会社の魅力や働く環境、成長機会などを具体的に伝えることが大切です。
問い合わせ・集客の窓口になる
Webサイトは24時間365日稼働する営業窓口として機能します。問い合わせフォームやチャットボットなどを設置することで、潜在顧客からの質問や相談を随時受け付けることができます。
また、サービスや商品の詳細情報を掲載することで、セールスの前段階である「情報提供」を自動化できるメリットもあります。会社のWebサイトがあることで、営業担当者は既に興味を持った見込み客に対して、より深い提案や交渉に注力できるようになります。
適切なUI/UXデザインをすれば、ユーザーを「お問い合わせ」や「資料請求」などの行動に自然と導くことも可能です。導線設計により、問い合わせ数の増加や商談率の向上が期待できるでしょう。
SNSや広告と連携して認知拡大ができる
Webサイトは、SNSや広告などの他のWebマーケティング施策と連携することで、さらに大きな効果を発揮します。また、Webサイト上のコンテンツをSNSで共有したり、ブログ記事などを定期的に更新したりすることで、継続的な認知拡大が可能になります。
結果、検索エンジンでの表示順位(SEO)も向上し、より多くの潜在顧客にリーチできるようになります。会社のWebサイトは単なる情報掲載の場ではなく、ブランディング、採用、営業、マーケティングなど、ビジネスの多方面で効果を発揮する重要なツールなのです。
会社Webサイトに必要なページ構成とは?
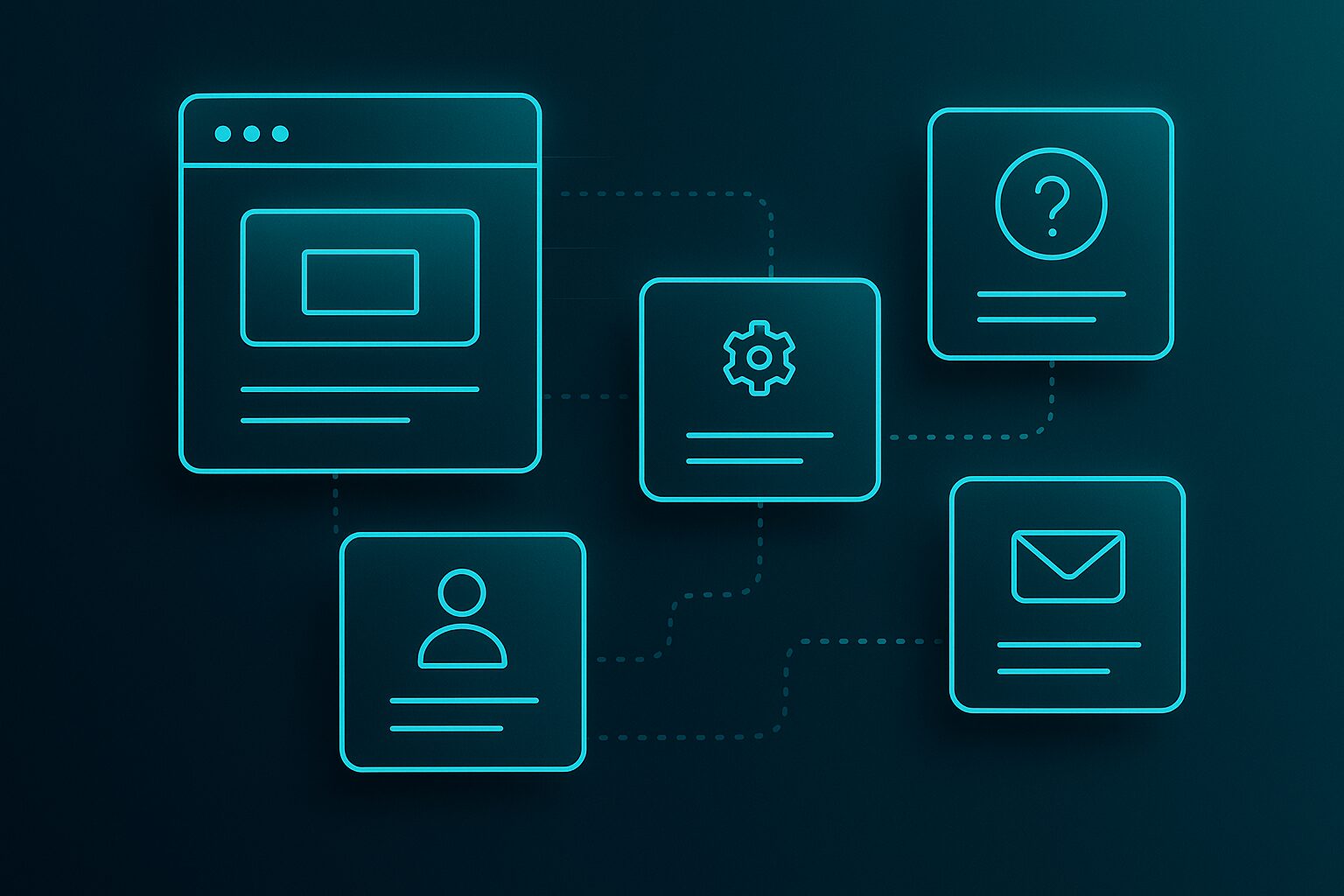
効果的な会社Webサイトを作るためには、適切なページ構成が欠かせません。ここでは、基本的に必要なページとその役割について解説します。
トップページ
トップページは、Webサイトの顔とも言える最も重要なページです。訪問者が最初に目にするページであり、ここでの印象がその後の行動を大きく左右します。効果的なトップページには以下の要素を含むといいでしょう。
- 企業の強みや特徴が一目でわかるキャッチコピー
- 清潔感のあるデザインと読みやすいレイアウト
- 重要なコンテンツへのナビゲーション(メニュー)
- お問い合わせボタンなどの主要なアクション導線
- 企業の信頼性を伝える実績や顧客ロゴ
トップページのデザインは、企業のブランドイメージを強く反映したものが望ましいでしょう。ただし、華やかさだけを追求するのではなく、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできる機能性も重視することが大切です。
会社概要・アクセス情報
会社概要ページは、企業の基本情報を伝える重要なセクションです。ここには以下の情報を掲載します。
- 社名、所在地、設立年月日
- 資本金、従業員数
- 事業内容
- 企業理念・ビジョン
- 代表者メッセージ
- 沿革(企業の歴史)
- アクセスマップ(できればGoogleマップと連携)
このページは、取引先や就職希望者が企業の基本情報を確認する際によく訪れる場所です。信頼性を高めるためにも、正確かつ最新の情報を掲載しましょう。
サービス紹介・商品ページ
自社のサービスや商品を紹介するページは、ビジネスの核となる部分です。ここでは、以下のポイントを意識して作成するとよいでしょう。
- 各サービス・商品の特徴や強み
- 他社との差別化ポイント
- 導入事例や実績
- 価格体系(可能であれば)
- よくある質問と回答(FAQ)
専門用語やビジネス特有の言葉は極力避け、初めて訪れた人にもわかりやすい表現を心がけることが重要です。また、文章だけでなく、写真や図解、動画などを活用することで、理解度を高めることができます。
お問い合わせフォーム
お問い合わせフォームは、潜在顧客との最初の接点となる重要な窓口です。使いやすく、かつ必要な情報を適切に収集できるフォーム設計が求められます。効果的なお問い合わせフォームの特徴は以下の通りです。
- シンプルで入力しやすいデザイン
- 必須項目は最小限に抑える
- 入力エラーが発生した場合の分かりやすいメッセージ
- 送信後の自動返信メール設定
- プライバシーポリシーへのリンク
また、フォームに至るまでの導線も重要です。各ページからお問い合わせボタンが見えやすい位置にあると、潜在顧客のアクションを促しやすくなります。
採用情報ページ
人材採用を行う企業にとって、採用情報ページは欠かせません。採用ページでは募集要項だけでなく、企業文化や働く環境、成長機会などを具体的に伝えることが重要です。採用ページを魅力的にするには、以下の要素を含むといいでしょう。
- 企業の価値観や文化
- 具体的な仕事内容
- 社員インタビューや社内の様子
- 福利厚生や研修制度
- 採用プロセスの説明
- エントリーフォーム
特に最近は、「どんな人と働けるか」「どのように成長できるか」といった情報を重視する求職者が増えています。単なる条件だけでなく、働く意義や環境を具体的に伝えることで、ミスマッチを減らし、企業文化に合った人材を採用しやすくなります。
プライバシーポリシー・利用規約など
法的な観点からも重要なのが、プライバシーポリシーや利用規約などのページです。特に個人情報を扱うフォームがある場合は、プライバシーポリシーの掲載は必須と言えます。これらのページには以下の内容を含めるとよいでしょう。
- 収集する個人情報の種類と目的
- 個人情報の管理方法
- 第三者への情報提供の有無
- お問い合わせ窓口
- クッキーポリシー(使用している場合)
これらのページは専門的な内容になるため、必要に応じて法務担当者や専門家に相談しながら作成するのが望ましいでしょう。会社のWebサイトには様々なページが必要です。ただし、全てを一度に完璧に作る必要はありません。まずは必須のページから始め、段階的に拡充していくアプローチも有効です。
会社のWebサイトを作る方法【自作 vs 外注】

会社のWebサイトを作る方法は大きく分けて、自分で作る方法と外部に依頼する方法があります。それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
自分で作る方法(Wix、WordPress、ペライチなど)
近年は、専門的な知識がなくても比較的簡単にWebサイトを作れるサービスが増えています。代表的なものには以下があります。
- Wix
ドラッグ&ドロップでレイアウトを自由に編集できるサービス。初心者にも使いやすく、テンプレートも豊富です。 - WordPress
世界で最も使われているCMS(コンテンツ管理システム)。自由度が高く、プラグインで機能拡張も可能です。ある程度の学習が必要ですが、一度覚えれば様々なサイトに応用できます。 - ペライチ
日本製のWebサイト作成サービス。名前の通り、1ページのシンプルなサイトを手軽に作れます。
自分で作るメリットは、コストを抑えられることと、更新や修正を自分のペースでできること。一方、デメリットは、プロフェッショナルなデザインやカスタマイズには限界があること、および学習時間が必要になることです。
特に小規模な企業や、まずは試験的にWebサイトを立ち上げたい場合には、こうしたサービスを活用するのも一つの選択肢です。ただし、企業の顔となるWebサイトですので、あまりに簡素なものでは信頼性に欠ける印象を与える可能性もあります。
Web制作会社に依頼するメリット・デメリット
Web制作会社に依頼する場合のメリットは、プロフェッショナルな品質のWebサイトが作れることです。以下のような特徴があります。
メリット
- プロによるデザイン・構成で差別化が図れる
- SEOや使いやすさなど専門的な知識を活かした設計が可能
- 制作後のサポートやメンテナンスも依頼できる
デメリット
- 費用が高くなる(規模にもよるが数十万円〜)
- 要望の伝達や修正のやり取りに時間がかかる場合がある
- 契約内容によっては小さな修正でも追加費用が発生することも
Web制作会社を選ぶ際には、過去の制作実績をチェックし、自社のイメージに合ったデザインスタイルの会社を選ぶことが重要です。また、制作後のサポート体制についても事前に確認しておきましょう。
フリーランスに依頼するケース
Web制作会社とフリーランスの中間的な選択肢として、フリーランスのデザイナーやエンジニアに依頼する方法もあります。
メリット
- Web制作会社よりも比較的低コスト
- 直接コミュニケーションを取りやすい
- スピーディーな対応が期待できる場合が多い
デメリット
- 個人の専門分野や得意領域に依存する
- 病気や多忙時のバックアップ体制がない
- 長期的なサポート体制が不安定な場合がある
フリーランスに依頼する場合は、ポートフォリオのチェックはもちろん、コミュニケーション能力や対応の迅速さなども重視して選ぶとよいでしょう。また、複数の案件を抱えている場合が多いため、納期については余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。
外注時に気をつけるポイント
外部に依頼する際には、以下のポイントに特に注意が必要です。
- 契約内容の明確化
- 制作物の範囲(ページ数、機能など)
- 納期と支払い条件
- 修正回数や追加料金の発生条件
- 制作後のサポート内容と期間
- 著作権や使用権の確認
- 制作物の著作権は誰に帰属するのか
- 使用する素材(写真・イラストなど)の権利関係
- ソースコードの所有権
- コミュニケーション方法
- 進捗確認の頻度と方法
- 担当者の連絡先と対応可能時間
- 緊急時の対応手順
これらの点を事前に明確にしておくことで、制作過程でのトラブルを未然に防げます。特に著作権については、後々問題になるケースも少なくないため、契約書で明確に定めておくことをおすすめします。
Webサイト制作方法は、予算、時間、求める品質のバランスによって決めるのが良いでしょう。まずは小規模からスタートし、段階的に拡充していくアプローチも、多くの企業で採用されています。
会社Webサイトの費用相場と内訳

会社のWebサイトを作る際の費用は、規模や機能によって大きく異なります。ここでは、一般的な費用相場と内訳について解説します。
初期制作費用の目安(10万〜100万円の差)
Webサイトの初期制作費用は、規模やデザインの凝り具合、機能の複雑さなどによって、10万円程度から100万円以上まで幅広く分布しています。
小規模なWebサイト(10〜30万円程度)
- 5ページ程度の基本的な構成
- テンプレートベースのデザイン
- 問い合わせフォームなどの基本機能
中規模なWebサイト(30〜70万円程度)
- 10〜15ページ程度の構成
- オリジナルデザイン
- ブログ機能やニュースリリース機能
- 簡単な予約フォームなど
大規模なWebサイト(70〜100万円以上)
- 多数のページを持つ複雑な構成
- 完全オリジナルのデザイン
- 会員機能や決済システム
- 多言語対応
- カスタムプログラミング
これらはあくまで目安であり、制作会社やデザイナーによっても価格設定は異なります。また、地域によっても相場に差があるため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
ドメイン・サーバー費用
Webサイトを公開するためには、ドメイン(URL)とサーバー(Webサイトのデータを保存する場所)が必要です。これらは継続的に発生する費用として計画に入れておく必要があります。
ドメイン費用
- 年間1,000〜3,000円程度
- 取得したいドメイン名の人気や希少性によって価格が変動
- .comや.jpなど、拡張子によっても価格が異なる
レンタルサーバー費用
- 月額500〜5,000円程度(プランによる)
- 共有サーバーは比較的安価
- 専用サーバーやVPSは高機能だが高価
- SSL証明書(https化)の費用も含まれる場合と別途必要な場合がある
これらの費用は、自分で管理する場合も外注する場合も基本的に同じく発生します。ただし、外注の場合は代行手数料が上乗せされることもあります。
保守・運用コスト
Webサイトは作って終わりではなく、継続的なメンテナンスが必要です。これにも費用がかかることを理解しておきましょう。
定期的な更新・運用費用
- 月額1万〜5万円程度
- 情報更新の頻度や量によって変動
- ブログやニュース記事の更新頻度
セキュリティ対策
- WordPress等のCMSを利用している場合、定期的なアップデートが必要
- セキュリティプラグインの導入費用
- 万が一の不正アクセス・改ざん時の復旧費用
技術サポート
- 不具合対応
- 機能追加・改修費用
- 相談やアドバイスの対応費用
特に中小企業ではこうした運用コストを見落としがちですが、長期的な視点で予算を組むことが重要です。月々の運用コストを含めた総所有コスト(TCO)で比較検討することをおすすめします。
無料ツールを使った場合との比較
Webサイトを無料ツールで作る方法もありますが、メリットとデメリットを理解した上で選択することが大切です。
メリット
- 初期投資がほぼゼロ
- 簡単な操作で作れる
- すぐに公開できる
デメリット
- 独自ドメインが使えない場合が多い(例:yourcompany.wixsite.com)
- デザインや機能のカスタマイズに制限がある
- 広告が表示される場合がある
- 企業イメージを損なう可能性
無料ツールは、予算が極めて限られている場合や、一時的な使用、あるいはテスト目的には適していますが、企業の正式なWebサイトとしては、有料プランや専門業者への依頼を検討する方が長期的には良い選択となるでしょう。
費用対効果の観点からは、自社のビジネス目標や予算規模に応じた適切な投資が重要です。初期費用を抑えることだけに注力するよりも、Webサイトを通じてどのようなビジネス成果を得たいかを明確にし、それに見合った予算配分を考えることをおすすめします。
\会社のWebサイト制作を検討中の方は月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを提供するホームページできるくんにご相談ください!/
デザイン・コンテンツで意識すべきポイント
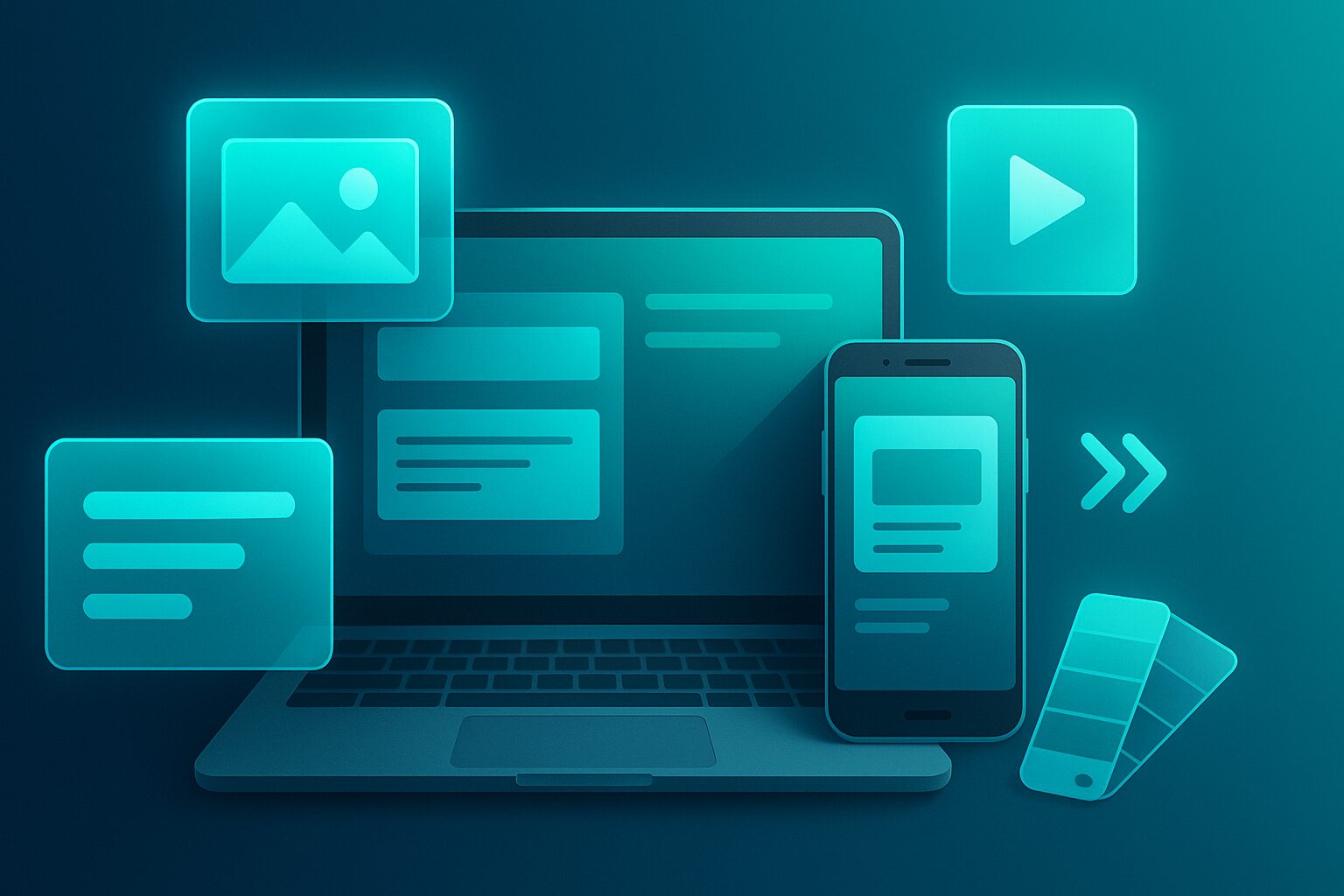
効果的な会社Webサイトを作るためには、デザインやコンテンツ面でも押さえるべきポイントがあります。ここでは、特に重要な要素について解説します。
スマホ対応(レスポンシブデザイン)の重要性
現在、インターネットトラフィックの約60%以上がモバイルデバイスからのアクセスだと言われています。そのため、スマートフォンでの閲覧に最適化されたデザイン(レスポンシブデザイン)は必須と言えるでしょう。
レスポンシブデザインとは、閲覧するデバイスの画面サイズに応じて自動的にレイアウトが変わる仕組みです。これにより、PCでもスマートフォンでも、ストレスなくWebサイトを閲覧できるようになります。
Googleの検索アルゴリズムもモバイル対応を重視しており、モバイルフレンドリーでないサイトは検索順位が下がる可能性があります。つまり、スマホ対応は単なるユーザビリティの問題だけでなく、SEO対策としても重要なのです。
ユーザー目線での導線設計
Webサイトの設計で最も重要なのは、ユーザーが求める情報にスムーズにたどり着けるかどうかです。これをUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)と呼びます。効果的な導線設計のポイントは以下の通りです。
- 重要な情報やアクションボタンを目立つ位置に配置する
- メニュー構造を分かりやすく整理する
- 検索機能を設置する(サイトが大きい場合)
- ユーザーの行動パターンを予測し、次のステップへ自然に誘導する
例えば、サービス紹介ページでは、詳細情報の次に「お問い合わせ」や「資料請求」といったアクションボタンを配置することで、興味を持ったユーザーの次のステップをスムーズに促すことができます。また、サイト内のどのページからでも最大3クリック以内に目的のページにたどり着けるような設計が理想的です。
写真・動画・文章のクオリティ
Webサイトの第一印象を大きく左右するのが、掲載されるコンテンツの質。特に以下の要素は重要です。
写真
- 可能な限りプロのカメラマンに撮影を依頼する
- 少なくとも経営者や主要スタッフの写真は専門家に撮影してもらう
- オフィスや製品の写真も、明るく清潔感のある印象を心がける
- フリー素材を使う場合は、ビジネス向けの質の高いものを選ぶ
動画
- 企業紹介やサービス説明に動画を活用すると効果的
- 短時間(1〜2分程度)で要点をまとめる
- 字幕をつけて音声がなくても理解できるようにする
文章
- 専門用語やビジネス特有の言葉は極力避ける
- 短く簡潔な文章を心がける
- 見出しや箇条書きを活用して読みやすくする
- SEOを意識したキーワードの自然な配置
これらのコンテンツは、時間をかけて少しずつ質を高めていくことも可能です。最初から完璧を目指すよりも、まずは基本的な部分を押さえた上で、継続的に改善していく姿勢が大切です。
よくある失敗例とその対策
会社Webサイト制作でよく見られる失敗例とその対策について紹介します。
情報過多で重要なメッセージが埋もれる
- 対策1:トップページでは核となるメッセージや強みに絞る
- 対策2:詳細情報は階層化して、必要な人だけが詳しく見られるようにする
問い合わせまでの導線が不明確
- 対策1:各ページに明確なCTA(Call To Action)ボタンを配置
- 対策2:お問い合わせフォームは簡潔で入力しやすいものにする
情報が古いまま放置される
- 対策1:更新が容易なCMSを採用する
- 対策2:定期的な更新スケジュールを設定する
- 対策3:日付や「NEW」マークなどで最新情報を明示する
ロード時間が長すぎる
- 対策1:画像サイズの最適化
- 対策2:不要なプラグインや重いスクリプトを削減
- 対策3:CDN(Contents Delivery Network)の活用
スマホでの表示崩れ
- 対策1:レスポンシブデザインの徹底
- 対策2:様々なデバイスでのテスト確認
- 対策3:スマホでの操作性を重視した要素サイズの設定
こうした失敗を防ぐためには、制作過程での十分なテストと、実際のユーザーからのフィードバックを活かした継続的な改善が欠かせません。デザインやコンテンツは、Webサイトの「顔」となる部分です。作って終わりではなく、ユーザーの反応を見ながら常に改善していきましょう。
【運用・改善編】Webサイトを作った後にやるべきこと

Webサイトの公開はゴールではなく、むしろスタートです。Webサイトの効果を最大化するために、公開後の運用・改善が重要になります。ここでは、Webサイト公開後に取り組むべき施策について解説します。
SEO対策(検索エンジンに見つけてもらう)
せっかく作ったWebサイトも、検索エンジンで見つけてもらえなければ意味がありません。SEO(検索エンジン最適化)対策は、Googleなどの検索エンジンでの表示順位を上げるための取り組みです。以下、基本的なSEO対策のポイントをご紹介します。
- 各ページにわかりやすいタイトルを設定する
- メタディスクリプション(検索結果に表示される説明文)を適切に設定する
- 見出しタグ(h1, h2, h3…)を階層的に使用する
- ページの読み込み速度を改善する
- モバイルフレンドリーなデザインにする
- 質の高いコンテンツを定期的に追加する
- 自然な形で関連キーワードを本文に盛り込む
特に重要なのは、ユーザーが求める情報を提供する「質の高いコンテンツ」です。検索エンジンのアルゴリズムは年々高度化しており、単にキーワードを詰め込むだけの対策は効果がなくなっています。自社の専門性を活かした有益な情報を発信することが、長期的に見て最も効果的なSEO対策と言えるでしょう。
Googleマップ・ビジネスプロフィールの連携
実店舗を持つ企業にとって特に重要なのが、Googleマップとの連携です。Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に登録することで、以下のメリットがあります。
- 地域検索で自社が表示されやすくなる
- 営業時間や住所、電話番号といった基本情報が表示される
- 顧客からのレビューを受けられる
- 写真やサービス情報を掲載できる
- 投稿機能で最新情報を発信できる
また、WebサイトにGoogleマップを埋め込むことで、アクセス情報をわかりやすく伝えることができます。これにより、訪問を検討している顧客の不安を減らし、実際の来店につなげやすくなります。Googleビジネスプロフィールの登録は無料で行え、地域ビジネスにとっては投資対効果の非常に高い施策と言えるでしょう。
アクセス解析(Googleアナリティクスなど)
Webサイトの効果を測定し、改善していくためには、アクセス解析ツールの導入が欠かせません。代表的なのがGoogleアナリティクスです。これらのツールを使うことで、以下のような情報を把握できます。
- 訪問者数や閲覧ページ数
- 訪問者の流入経路(検索、SNS、広告など)
- よく見られているページと離脱率の高いページ
- 訪問者の属性(地域、デバイス、年齢層など)
- サイト内での行動パターン
これらのデータを分析することで、Webサイトの問題点や改善点が見えてきます。例えば、特定のページでの離脱率が高い場合は、そのページのコンテンツやデザインに問題がある可能性があります。定期的にデータを確認し、PDCAサイクルを回していくことで、より効果的なWebサイトへと進化させることができます。
定期的な情報更新と改善(CMSの活用)
Webサイトは「生き物」のようなものです。情報が古いままだと、訪問者に「この会社は活動していないのでは?」という印象を与えてしまいます。定期的な更新は、以下の点で重要です。
- 最新の情報を顧客に提供できる
- 検索エンジンのクローラーが定期的に訪れるようになる(SEO効果)
- 訪問者が再訪問するきっかけになる
更新を容易にするために、CMS(コンテンツ管理システム)の活用をおすすめします。WordPressなどのCMSを使えば、専門知識がなくても簡単に記事の追加や編集が可能になります。更新すべき主な情報としては以下が挙げられます。
- 新サービスや商品の情報
- イベントやセミナーの告知
- 採用情報
- お知らせやプレスリリース
- ブログ記事やコラム
特にブログやコラムは比較的更新しやすく、専門性をアピールする有効な手段です。自社の知見や業界情報を発信することで、顧客からの信頼獲得にもつながります。
会社のWebサイトは「資産」。目的に合わせて賢く作ろう
会社のWebサイトは現代ビジネスに欠かせない「顔」となり、信頼構築や問い合わせ獲得、採用強化などの多彩な効果をもたらします。成功のカギは明確な目的設定にあります。企業情報の提供だけでなく、顧客が求める情報を分かりやすく届けることが重要です。
制作方法は自作から外注まで様々ですが、予算と必要な品質のバランスを考慮して選びましょう。費用は10万円台から100万円以上まで幅広く、初期費用だけでなく運用コストも計画に入れることが必須です。
公開後はSEO対策やアクセス解析を通じて継続的に改善し、定期的な情報更新も欠かせません。スマホ対応デザインや使いやすい導線設計など、ユーザー目線での構築が長期的な成果につながります。Webサイトは「資産」です。目的を明確にして、ユーザーに価値ある情報を提供することで、中小企業やスタートアップでも大きな効果を生み出せます。
\会社のWebサイト制作を検討中の方は月額1,900円〜プロのデザイナーが高品質のホームページを提供するホームページできるくんにご相談ください!/