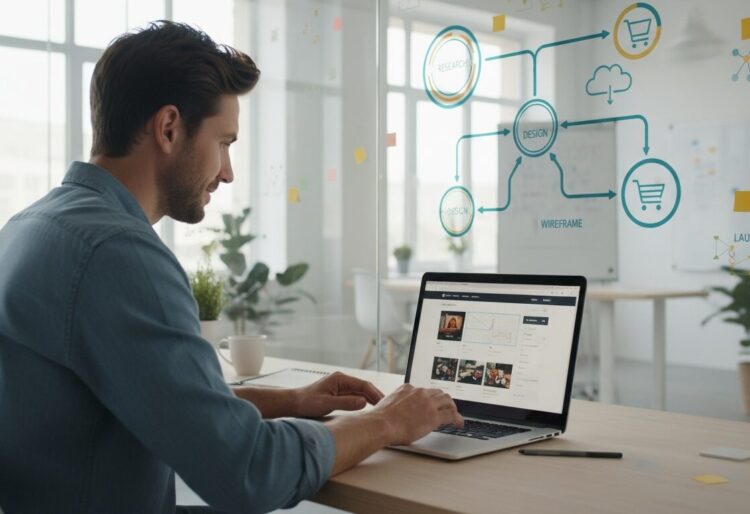お役立ち情報
ホームページ作成をフリーランスに依頼する方法は?費用相場・選び方・注意点を徹底解説

ホームページ制作を検討しているけれど、制作会社の見積もりが予想以上に高額で困っていませんか。最近では優秀なフリーランスのWebデザイナーやエンジニアが増えていて、制作会社よりも手頃な価格で質の高いホームページを作ることが可能になっています。
しかし、フリーランスへの依頼には「本当に信頼できるのか」「トラブルが起きたらどうしよう」という不安もつきものでしょう。本記事では、フリーランスにホームページ制作を依頼する際の費用相場から選び方、トラブル回避の方法まで、実際の事例を交えながら詳しく解説します。
制作会社に依頼をしたいけど予算の都合で諦めているなら「ホームページできるくん」へご相談ください。
制作費0円、月額1,900円から、プロが作成するオリジナルホームページを持つことができます。
フリーランスにホームページ作成を依頼するメリット・デメリット
フリーランスへの依頼を検討する際、まず理解しておきたいのがメリットとデメリットです。制作会社とは異なる特徴を把握することで、自社にとって最適な選択ができるようになります。
制作会社と比較したフリーランスの5つのメリット
まず、フリーランスに依頼するメリットから見ていきましょう。
コスパが高い
制作会社の場合、オフィス賃料や正社員の人件費などの固定費が料金に反映されますが、フリーランスはこうした経費が少ないため、同じクオリティでも20〜50%程度安く制作できることが多いのです。
柔軟に対応してくれる
制作会社では複数の担当者を経由するため意思決定に時間がかかりますが、フリーランスなら直接やり取りができるため、修正依頼や要望の反映がスピーディーに行えます。また、土日や夜間の対応も相談しやすいという利点があります。
専門性が高い
フリーランスの多くは特定の分野に特化したスペシャリストであり、例えばECサイト専門、美容業界専門など、業界特有のノウハウを持っている人材を見つけやすいという特徴があります。
小回りが利く
制作会社では最低発注金額が設定されていることが多いですが、フリーランスなら「トップページだけリニューアルしたい」「特定のページだけ作りたい」といった部分的な依頼にも対応も相談しやすい可能性があります。
長期的なパートナーシップを築きやすい
制作会社では担当者が変わることがありますが、フリーランスなら同じ人が継続して対応してくれるため、自社のビジネスを深く理解した上でのサポートが期待できます。
フリーランスに依頼する際の3つのデメリットと対策
一方で、フリーランスへの依頼にはデメリットも存在します。それぞれ見ていきましょう。
信頼性の担保が難しい
制作会社のような組織的なバックアップがないため、病気や事故などで突然連絡が取れなくなるリスクがあります。対策としては契約書をしっかりと交わすことと、定期的な進捗報告を義務付けることになります。
リソースに限りがある
フリーランスは基本的に一人で作業するため、大規模なプロジェクトや短納期の案件には対応が難しい場合があります。そのため、プロジェクトの規模や納期を事前にしっかりと相談し、無理のないスケジュールを組むことが大切です。
総合的なサポートができない
制作会社なら企画からデザイン、開発、運用まで一貫して対応できますが、フリーランスの場合は得意分野が限定されることが多く、例えばデザインは得意でもプログラミングはできないといったケースがあります。この場合は、複数のフリーランスでチームを組むか、不足する部分は別途専門家に依頼する必要があるでしょう。
フリーランスへの依頼が向いている企業・向いていない企業
フリーランスへの依頼が特に向いているのは、予算に制限がある中小企業やスタートアップ企業です。限られた予算内で最大限の成果を出したい場合、フリーランスの柔軟性とコストパフォーマンスは大きな武器になります。また、スピード感を重視する企業や、特定の専門性が必要なプロジェクトを抱えている企業にも適しています。
一方、向いていないのは大規模なシステム開発を伴うプロジェクトや、24時間365日のサポートが必要な企業でしょう。また、社内の承認プロセスが複雑で、制作会社のような組織的な対応を求める大企業の場合も、フリーランスでは対応が難しいケースがあります。
メリット、デメリットを踏まえ、コストを抑えながらも制作会社へ依頼したいとお考えでしたら「ホームページできるくん」へご相談ください。
Web業界10年、5,000社以上の制作支援実績から得た知見を基に、無料のオンライン相談でホームページのお悩みにお答えします。
https://lp.dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html
ホームページ作成をフリーランスに依頼する際の費用相場
フリーランスへの依頼を検討する際、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。ここでは制作内容別の相場から料金体系まで、詳しく解説していきます。
制作内容別の料金相場一覧
LP・コーポレートサイト・ECサイトなど、どのサイトを作るかによって料金相場は異なります。それぞれ見ていきましょう。
ランディングページ(LP)の制作費用相場
フリーランスの場合5万円〜30万円程度が相場となっています。シンプルな1ページ構成なら5〜10万円、アニメーションや複雑なデザインを含む場合は15〜30万円程度を見込んでおくとよいでしょう。制作会社なら同じ内容で10〜60万円程度かかることを考えると、かなりリーズナブルです。
コーポレートサイトの制作費用相場
ページ数や機能によって大きく変動しますが、5〜10ページ程度の標準的なサイトなら20〜80万円が相場となります。トップページ、会社概要、サービス紹介、お問い合わせフォームといった基本構成であれば、20〜40万円程度で制作可能です。ブログ機能やニュース更新機能を追加する場合は、プラス10〜20万円程度を見込んでおきましょう。
ECサイトの制作費用相場
使用するプラットフォームによって費用が大きく異なります。既存のECプラットフォーム(Shopify、BASE、STORESなど)を利用する場合は、デザインカスタマイズと初期設定で30〜100万円程度が相場です。一方、フルスクラッチで開発する場合は100万円以上かかることも珍しくありません。
これらの相場はフリーランスの経験年数やスキルレベルによっても変動します。実績豊富なベテランフリーランスなら相場の上限に近い金額になりますが、その分クオリティも期待できるでしょう。
フリーランスの料金体系の種類(固定報酬・時間単価・成果報酬)
フリーランスの料金体系は大きく3つに分類されます。詳しく見ていきましょう。
固定報酬制
プロジェクト全体の費用を事前に決める方式です。予算管理がしやすく、追加費用の心配がないため、多くの企業が採用しています。ただし、仕様変更や追加要望には別途費用が発生することに注意が必要です。
時間単価制
実際の作業時間に応じて報酬を支払う方式で、Webエンジニアの場合は時給3,000〜10,000円、デザイナーなら2,500〜8,000円程度が相場となっています。要件が明確でない場合や、継続的なサポートが必要な場合に適していますが、最終的な費用が読みにくいというデメリットもあります。
成果報酬制
売上向上やコンバージョン率改善など、具体的な成果に応じて報酬を支払う方式です。ECサイトやマーケティング要素の強いサイトで採用されることがありますが、成果の定義や測定方法について事前に詳細な取り決めが必要になります。
追加費用が発生しやすい項目と見積もり時の確認ポイント
見積もり時に見落としがちな追加費用として、まず挙げられるのがドメイン・サーバー費用です。これらは制作費とは別に必要となり、年間1〜5万円程度かかります。また、有料の写真素材やフォントを使用する場合も、別途ライセンス料が必要になることがあります。
修正回数の制限も重要な確認ポイントです。多くのフリーランスは「修正〇回まで無料」という条件を設けていて、それを超えると追加費用が発生します。事前に修正回数と追加修正の料金を確認しておきましょう。
さらに、納品後の保守・運用費用も忘れてはいけません。月額5,000〜30,000円程度で、定期的なバックアップやセキュリティアップデート、軽微な修正などに対応してもらえます。これらの費用を含めた総額で予算を検討することが大切です。
優秀なフリーランスWebデザイナー・エンジニアの探し方
適切なフリーランスを見つけることは、プロジェクトの成功を左右する重要な要素です。ここでは、効果的な探し方を3つの方法に分けて紹介します。
フリーランス向けマッチングサイト・クラウドソーシングの活用方法
現在、フリーランスを探す最も一般的な方法がマッチングサイトやクラウドソーシングサービスの利用です。代表的なサービスとして、ランサーズ、クラウドワークス、ココナラなどがあり、それぞれに特徴があります。
ランサーズやクラウドワークスは、幅広いジャンルのフリーランスが登録していて、予算や納期を提示してコンペ形式で募集することも可能です。一方、ココナラは料金が明確に設定されているため、予算に合わせて選びやすいという利点があります。
これらのサービスを利用する際のコツは、募集文を具体的に書くことです。「ホームページを作ってください」という漠然とした依頼ではなく、業種、ページ数、必要な機能、参考サイト、予算、納期などを明確に記載することで、適切なフリーランスからの応募を得やすくなります。
また、フリーランスのプロフィールや過去の評価を必ずチェックしましょう。特に、自社と同じ業界での制作実績があるかどうかは重要なポイントになります。
SNS(X・Instagram)でフリーランスを見つける方法
最近では、SNSを活用してフリーランスを探す企業も増えています。特にXやInstagramは、デザイナーやエンジニアが自身の作品を公開する場として活用されていて、実力のあるフリーランスを直接見つけることができます。
Xでは、「#Web制作」「#フリーランスWebデザイナー」などのハッシュタグで検索すると、多くのフリーランスの投稿を見つけることができます。日頃の投稿内容から、その人の人柄や仕事への姿勢も把握できるため、相性の良いフリーランスを見つけやすいという利点があります。
Instagramは特にデザイナーの作品探しに適しています。ビジュアル中心のプラットフォームなので、デザインセンスを直感的に判断できます。気に入ったデザインを見つけたら、DMで直接コンタクトを取ることも可能です。
ただし、SNS経由での依頼は、マッチングサイトのような仲介システムがないため、契約や支払いについては自己責任で管理する必要があることに注意しましょう。
知人からの紹介・リファラル採用のメリット
意外に効果的なのが、知人や取引先からの紹介です。実際に仕事をした経験がある人からの紹介なら、スキルや人柄について信頼できる情報を得られます。また、紹介者との関係性があるため、トラブルになりにくいというメリットもあります。
紹介を受ける際は、紹介者に具体的な要望を伝えておくことが大切です。予算感や求めるスキル、プロジェクトの規模などを明確にしておけば、ミスマッチを防ぐことができます。
また、業界の交流会やセミナーに参加することで、フリーランスと直接出会う機会を作ることも有効です。実際に会って話すことで、コミュニケーション能力や相性を確認できるため、長期的なパートナーシップを築きやすくなります。
失敗しないフリーランスの選び方|7つのチェックポイント
フリーランス選びで失敗しないためには、事前の見極めが非常に重要です。ここでは確認すべき7つのポイントを詳しく解説します。
ポートフォリオ・制作実績の見方と評価基準
ポートフォリオは、フリーランスの実力を判断する最も重要な材料です。単にデザインの美しさだけでなく、以下の観点から総合的に評価することが大切です。
まず確認したいのが、制作実績の多様性です。様々な業界、規模のサイトを手がけているフリーランスは、柔軟な対応力があると判断できます。特に自社と同じ業界の実績があれば、業界特有の課題やニーズを理解している可能性が高いでしょう。
次に、制作プロセスの説明があるかどうかも重要なポイントです。単に完成品を見せるだけでなく、クライアントの課題、解決策、制作過程での工夫点などが説明されているポートフォリオは、フリーランスの思考プロセスを理解する上で参考になります。
また、実際のサイトがまだ公開されているかも確認しましょう。リンク切れが多い場合は、メンテナンスやアフターフォローが不十分な可能性があります。
スキル・技術力を見極める質問リスト
技術力を確認するためには、具体的な質問を投げかけることが効果的です。例えば、「レスポンシブデザインにはどのような手法を使いますか」「SEO対策として具体的にどのような施策を行いますか」といった質問で、実務レベルの知識を確認できます。
使用可能なツールやプログラミング言語についても確認しておきましょう。HTML、CSS、JavaScriptは基本として、WordPressなどのCMS、PhotoshopやFigmaなどのデザインツールの習熟度も重要です。最新の技術トレンドについての知識があるかどうかも、継続的な学習意欲を測る指標になります。
また、過去のプロジェクトでの課題と解決方法を聞くことで、問題解決能力を評価できます。具体的なエピソードを交えて説明できるフリーランスは、実践的な経験を積んでいると判断できるでしょう。
コミュニケーション能力・レスポンスの確認方法
技術力と同じくらい重要なのが、コミュニケーション能力です。初回の問い合わせへのレスポンススピードは、その後のプロジェクト進行の予測材料になります。24時間以内に返信があれば標準的、それ以上かかる場合は要注意です。
メールや電話での説明が分かりやすいかどうかも重要なポイントです。専門用語を多用せず、クライアントの理解度に合わせて説明できるフリーランスは、プロジェクト進行中のコミュニケーションもスムーズに行えるでしょう。
また、質問に対する回答の的確さも確認しましょう。曖昧な回答や、質問の意図を理解していない回答が多い場合は、コミュニケーションに問題がある可能性があります。
契約書・納期・アフターフォローの確認事項
契約に関する意識の高さは、プロフェッショナルとしての信頼性を測る重要な指標です。契約書の作成を提案してくるフリーランスは、トラブル防止の意識が高く、安心して仕事を任せられます。
納期についても、現実的なスケジュールを提示できるかどうかを確認しましょう。あまりに短納期を約束するフリーランスは、品質面でのリスクがあります。逆に、バッファを含めた余裕のあるスケジュールを提案してくる場合は、計画性があると判断できます。
アフターフォローの内容と期間も必ず確認しておきましょう。納品後の不具合対応期間、軽微な修正の対応範囲、保守契約の有無など、長期的な関係性を見据えた提案ができるフリーランスを選ぶことが大切です。
ホームページできるくんは、フリーランスへの依頼と同等程度の費用で制作から公開後の運用サポートまで実施しています。
オンライン無料相談を実施しているのでお気軽にご相談ください。
フリーランスとの制作プロジェクトの進め方
フリーランスとの協業を成功させるには、プロジェクトの進め方にもコツがあります。ここでは、各フェーズでの重要なポイントを解説します。
要件定義の作成ポイント
プロジェクトの成功は、最初の要件定義で8割が決まると言っても過言ではありません。曖昧な要件のまま進めると、後々の修正や追加費用の原因となります。
要件定義には、最低限以下の項目を含めましょう。
- サイトの目的と目標
- 「かっこいいサイトを作りたい」ではなく、「新規顧客からの問い合わせを月10件獲得したい」といった具体的な目標を設定することが重要です。
- ターゲットユーザーの属性
- 年齢、性別、職業、インターネットリテラシーのレベルなど、できるだけ具体的にペルソナを設定することで、デザインや機能の方向性が明確になります。
- 必要な機能やコンテンツのリストアップ
- お問い合わせフォーム、ブログ機能、会員登録機能など、必要な機能を優先順位付けして伝えることで、予算内での最適な提案を受けられます。
デザインカンプ・ワイヤーフレームの確認ポイント
デザイン段階での確認は、完成度を大きく左右します。ワイヤーフレーム(設計図)の段階では、レイアウトや情報の配置、導線設計を重点的にチェックします。この段階で大きな変更を行うことは比較的容易なので、遠慮なく意見を伝えましょう。
デザインカンプ(デザイン案)の確認では、ブランドイメージとの整合性を重視します。色使い、フォント、写真の雰囲気などが、企業のイメージと合っているかを確認します。また、競合他社のサイトと差別化できているかも重要なチェックポイントです。
スマートフォンやタブレットでの表示も必ず確認しましょう。現在、多くのユーザーがモバイル端末からアクセスするため、モバイルファーストの設計になっているかは極めて重要です。
修正依頼の伝え方とフィードバックのコツ
修正依頼の伝え方次第で、プロジェクトの進行スピードと最終的な品質が大きく変わります。「なんとなく違う」という曖昧な指摘ではなく、具体的に何をどう変更してほしいのかを明確に伝えることが大切です。
効果的なフィードバックのコツは、問題点と改善案をセットで伝えることです。例えば、「この部分が見づらい」だけでなく、「文字サイズを大きくして、背景とのコントラストを強くしてほしい」といった具体的な改善案を提示します。
また、良い点も積極的に伝えることで、フリーランスのモチベーション維持にもつながります。修正箇所だけでなく、気に入った部分についても具体的にフィードバックすることで、より良い関係性を築けるでしょう。
納品後の保守・運用・更新の取り決め
Webサイトは作って終わりではなく、継続的な運用が必要です。納品前に、保守・運用について明確な取り決めをしておくことが重要です。
まず、保証期間と対応範囲を明確にします。一般的には納品後1〜3ヶ月程度の不具合対応期間が設定されますが、その間にどこまでの修正が無料で対応されるのかを確認しておきましょう。
定期的な更新作業についても月額制の保守契約を結ぶのか、都度依頼にするのかを決めておきます。更新頻度が高い場合は月額契約の方がコスト的にもメリットがありますが、年に数回程度なら都度依頼でも問題ありません。
また、緊急時の連絡方法や対応時間についても確認しておくことで、トラブル時の不安を軽減できます。
フリーランスに依頼する際のトラブル事例と予防策
フリーランスとの取引では、残念ながらトラブルが発生することもあります。事前に想定されるリスクを知り、予防策を講じることが重要です。
よくあるトラブル5選(音信不通・納期遅延・品質問題など)
最も深刻なトラブルが、フリーランスとの音信不通です。プロジェクトの途中で突然連絡が取れなくなるケースは、意外と少なくありません。病気や事故、他の案件でのトラブルなど、理由は様々ですが、企業側としては大きな損失につながります。
納期遅延も頻繁に発生するトラブルの一つです。フリーランスは複数の案件を同時に抱えることが多く、スケジュール管理が甘いと納期に間に合わないことがあります。特に、他の案件を優先されて後回しにされるケースは要注意です。
品質問題も見過ごせません。ポートフォリオで見た作品と実際の納品物のクオリティが大きく異なる場合や、要件を満たしていない成果物が納品されることもあります。
著作権トラブルも時折発生します。使用した画像や素材の権利関係が不明確だったり、他社のデザインを流用していたりするケースです。後から問題が発覚すると、サイトの作り直しを余儀なくされることもあります。
最後に、追加費用の請求トラブルです。当初の見積もりになかった作業を勝手に行い、後から追加請求してくるケースや、修正回数の認識違いによる追加費用の発生などがあります。
契約書に盛り込むべき条項と法的保護
これらのトラブルを防ぐためには、しっかりとした契約書の作成が不可欠です。契約書には最低限、以下の条項を含めるべきでしょう。
業務内容と成果物の定義を明確に記載します。「Webサイト制作」という曖昧な表現ではなく、ページ数、機能、デザインの修正回数など、具体的に記載することが重要です。
納期と検収条件も必須項目です。いつまでに何を納品し、どのような基準で検収とするかを明記します。段階的な納品がある場合は、各マイルストーンも設定しておきましょう。
報酬の支払い条件も詳細に定めます。前払い、分割払い、完成後払いなど、支払いタイミングと金額を明確にし、追加作業が発生した場合の料金体系も記載しておきます。
著作権の帰属についても重要です。一般的には報酬の支払い完了後に発注者に著作権が移転する条項を設けますが、フリーランスが実績として公開する権利を残すケースもあります。
機密保持条項も忘れてはいけません。プロジェクトで知り得た情報を第三者に漏らさない義務を明記し、違反した場合の損害賠償についても定めておきます。
トラブル発生時の対処法と相談先
万が一トラブルが発生した場合の対処法も知っておく必要があります。まず、冷静に事実関係を整理し、契約書の内容を確認します。感情的にならず、建設的な解決策を探ることが大切です。
話し合いで解決しない場合は、第三者機関の活用も検討しましょう。フリーランス協会などの業界団体では、トラブル相談窓口を設けている場合があります。また、少額訴訟や調停といった法的手段も選択肢の一つです。
クラウドソーシングサービスを利用している場合は、運営会社のサポートを受けられることもあります。多くのサービスでは、トラブル時の仲裁機能を提供しているため、積極的に活用しましょう。
予防と対策を理解したところで、最後にフリーランスへの発注を成功させるための準備について解説します。
フリーランスへの発注を成功させるための準備
フリーランスとの協業を成功させるには、発注側の準備も重要です。ここでは、スムーズな発注のための具体的な準備方法を紹介します。
RFP(提案依頼書)の作成テンプレート
RFP(Request For Proposal)は、フリーランスに対して具体的な提案を依頼する文書です。これを作成することで、複数のフリーランスから比較可能な提案を受けることができます。
RFPには、プロジェクトの背景と目的を明記します。なぜWebサイトをリニューアルするのか、どのような課題を解決したいのかを具体的に記載することで、フリーランスも的確な提案ができるようになります。
要求仕様も詳細に記載します。必須機能と希望機能を分けて記載し、技術的な要件(使用するCMS、対応ブラウザ、表示速度の目標など)も明確にしておきます。
予算と納期の目安も重要な情報です。予算を明示することに抵抗がある場合は、レンジで示すだけでも構いません。納期についても、希望納期と必須納期を分けて伝えると、現実的な提案を受けやすくなります。
評価基準も事前に伝えておくと良いでしょう。価格だけでなく、実績、提案内容、対応力など、どのような観点で選定するかを明示することで、フリーランス側も力を入れるポイントが明確になります。
予算設定と相見積もりの取り方
適切な予算設定もプロジェクトの成功には欠かせません。まず、同規模の企業のWebサイト制作事例を調査し、相場感を掴むことから始めましょう。
予算は初期制作費用だけでなく、運用費用も含めて考える必要があります。月々の保守費用、年間のドメイン・サーバー費用、将来的な機能追加の費用なども考慮に入れて、トータルコストで判断することが大切です。
相見積もりを取る際は、3〜5社程度から取ることをおすすめします。あまり多すぎると選定に時間がかかりすぎ、少なすぎると適正価格が判断できません。
見積もりを比較する際は金額だけでなく、含まれている作業内容を詳細に確認します。一見安い見積もりでも、重要な作業が含まれていない場合があるため、注意が必要です。
社内承認を得るための資料作成のポイント
フリーランスへの発注には、多くの場合社内承認が必要になります。承認を得やすくするための資料作成のポイントを押さえておきましょう。
まず、制作会社との比較表を作成します。コスト、納期、対応の柔軟性、実績などを項目別に比較し、フリーランスを選ぶメリットを視覚的に示します。
リスクと対策も明記することが重要です。フリーランス特有のリスクを隠すのではなく、正直に提示した上で、それぞれに対する対策を示すことで、信頼性のある提案になります。
費用対効果の試算も説得力があります。Webサイトリニューアルによる問い合わせ増加や売上向上の見込みを数値化し、投資回収期間を示すことで、経営層の理解を得やすくなります。
成功事例の紹介も効果的です。同業他社や同規模企業がフリーランスを活用して成功した事例を紹介することで、不安を軽減できます。
フリーランスとの協業でコスパの良いホームページを作成しよう
フリーランスの最大のメリットであるコスパと柔軟性を活かすには、発注側の準備が重要です。要件を明確にし、コミュニケーションを密に取ることで、制作会社以上の成果を得ることも十分できるでしょう。
また、フリーランスとの関係を単なる外注先としてではなく、パートナーとして捉えることも大切です。お互いの強みを活かし弱みを補完し合う関係を築くことで、長期的に見て大きなメリットを享受できます。
プロジェクトの規模や性質に応じて、フリーランスと制作会社を使い分けることも大切です。小規模で専門性の高いプロジェクトはフリーランスに、大規模で総合的なサポートが必要なプロジェクトは制作会社に依頼するなど、適材適所の判断が求められます。
フリーランスとの協業にはリスクもありますが、適切な準備と管理によりリスクを十分にコントロールできます。この記事で紹介したポイントを参考に、ぜひフリーランスを活用した効果的なホームページ制作にチャレンジしてみてください。きっと期待以上の成果を得られるはずです。
最後になりますが、もしフリーランスへのホームページ発注に不安が残る方は、ホームページできるくんにご相談ください。プロのクリエイターが制作費0円、月額1,900円〜オリジナルで高品質のホームページを提供します。手軽にホームページを作成して集客力向上を実現したい方はぜひお気軽にご相談ください。