お役立ち情報
ランディングページとは?ホームページとの違い・作り方を解説

「ランディングページって聞いたことはあるけど、実際どんなものなのかよくわからない」
そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?
ホームページとランディングページの違いがわからず困っている方も多いことでしょう。
ランディングページは、商品やサービスの成約率を劇的に向上させる強力なツールです。
この記事では、ランディングページの基本的な意味から作り方までわかりやすく解説。ランディングページを活用したWeb集客を実現したい方は、ぜひ最後までお読みください。
\月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/
ランディングページ(LP)とは?
ランディングページの概念について見ていきましょう。
まず「ランディング(Landing)」の意味を理解しよう
ランディング(Landing)とは、英語で「着陸」や「到着」を意味する言葉です。飛行機が空港に着陸するように、ユーザーが最初に到着するWebページのことを指します。
Google検索、SNS、Web広告など、さまざまな経路から訪問者が「着陸」する最初の接点。ランディングページとは「ユーザーが最初に訪れる入り口ページ」という意味なのです。
広義のランディングページと狭義のランディングページの違い
実は、ランディングページには「広義」と「狭義」の2つの意味があることをご存知でしょうか。この違いを理解することで、より効果的なWeb戦略を立てることができます。
広義のランディングページとは、文字通り「ユーザーが最初に着陸するページ全般」を指します。これはトップページかもしれませんし、ブログ記事かもしれません。商品ページや会社概要ページの場合もあるでしょう。Google Analyticsなどで表示されるのは、広義のランディングページです。
一方、狭義のランディングページはマーケティング用語として使われます。具体的には、「購入・申込み・資料請求などを達成するための1枚完結型の縦長ページ」のことです。
狭義のランディングページは、広告やメールマガジンなどから誘導された訪問者に商品やサービスの魅力を伝え、行動を促すことに特化しています。一般的にビジネスでは、この狭義の意味でLPという言葉が使われることがほとんどです。
企業サイトでも意識すべき「入り口ページ」としての役割
広義のランディングページは、企業サイト運営においても非常に重要な視点となります。なぜなら、すべてのページが潜在的に「最初の接点」になる可能性があるからです。
現代のWeb集客では、必ずしもトップページから訪問者が入ってくるとは限りません。ブログから流入することもあれば、SNSから訪れることもあります。「このページが最初の接点になったとき、訪問者に何を伝えるか」を意識する必要があるのです。
入り口ページの役割を意識することでコンバージョン率向上につながっていくのです。
ランディングページとホームページの違い
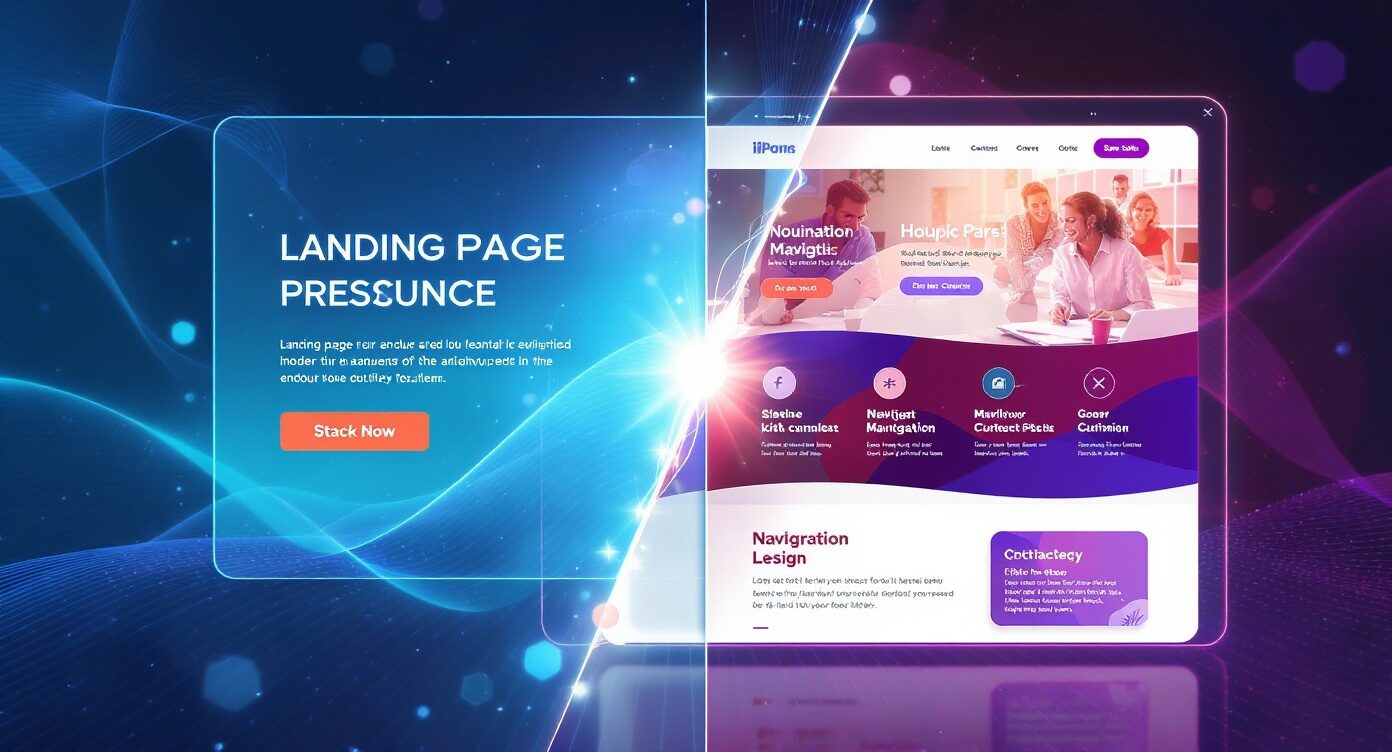
ランディングページとホームページには、目的や構成に違いがあります。
目的の違い(LP=成果特化/HP=情報発信・ブランディング)
まず最も大きな違いは、それぞれのページが持つ目的です。ランディングページは「成果(コンバージョン)」を出すことに特化しています。商品の購入、サービスの申込み、資料請求などの行動を促すことが最優先事項となります。
一方でホームページは、企業や店舗の総合的な情報発信とブランディングが主な目的です。会社概要、事業内容、実績、お知らせなど、さまざまな情報を体系的に整理して発信します。訪問者との長期的な関係構築を重視し、信頼性や専門性を伝えることが目的です。
ランディングページは「今すぐ行動してもらう」。ホームページは「じっくり理解してもらう」。こうした目的の違いが、デザインや構成、コンテンツの作り方にも大きく影響してくるのです。
構成の違い(1ページ完結 vs 複数ページ構造)
ページ構成においても、両者には明確な違いがあります。ランディングページは基本的に1ページで完結する縦長の構成になっています。スクロールしていくだけで、必要な情報がすべて得られるように設計されているのです。
これに対してホームページは、複数のページが階層構造で組み合わさっています。トップページを起点として、会社概要ページ、サービス紹介ページ、お問い合わせページなど、情報の種類ごとにページが分かれています。
ランディングページが1ページ完結型である理由は、訪問者の離脱を防ぐためです。他のページへ移動する選択肢を減らすことで、最後まで読んでもらい、コンバージョンにつなげやすくなります。
一方、ホームページが複数ページ構造を採用する理由は、情報を整理して提供するためです。訪問者が必要な情報を探しやすくし、サイト内を回遊してもらうことで、企業への理解を深めてもらうことができます。
デザイン・導線の違い(CV最適化型 vs ナビゲーション重視)
デザインと導線設計においても、それぞれ異なるアプローチが取られています。ランディングページは、コンバージョン最適化を最優先に考えたデザインになります。
目立つボタン、説得力のあるコピーなど、訪問者の心理に働きかける要素が盛り込まれます。また、余計なリンクを極力排除し、申込みボタンやフォームへの導線を明確にしています。こうすることで、迷わずアクションを起こしてもらえるようになるのです。
対照的にホームページは、ナビゲーションの使いやすさを重視したデザインになります。グローバルメニュー、パンくずリスト、サイドバーなど、サイト内を自由に移動できる設計です。求める情報にスムーズにたどり着けるよう考慮したデザインになっています。
運用の違い(広告用LPとSEO型HPの使い分け)
運用面でも、ランディングページとホームページには大きな違いがあります。ランディングページは主に広告運用と連動して使われることがほとんどです。リスティング広告やSNS広告からの流入を前提として制作されます。
また、広告のターゲティングに合わせて複数のランディングページを用意することも一般的。A/Bテストを実施して改善を重ねたりと、短期的な成果を追求する運用が中心となります。広告費をかけて集客し、その投資を回収するための仕組みとして機能するわけです。
一方、ホームページはSEO(検索エンジン最適化)を重視した長期的な運用が基本となります。コンテンツを追加・更新し、検索エンジンからの自然流入を増やしていくことが重要です。ブログ、お知らせ、実績など、継続的な情報発信によってサイトの価値を高めていくのです。
それぞれの特性を理解して使い分けることが、効果的なWeb集客の鍵となるのです。
\月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/
ランディングページの目的と役割
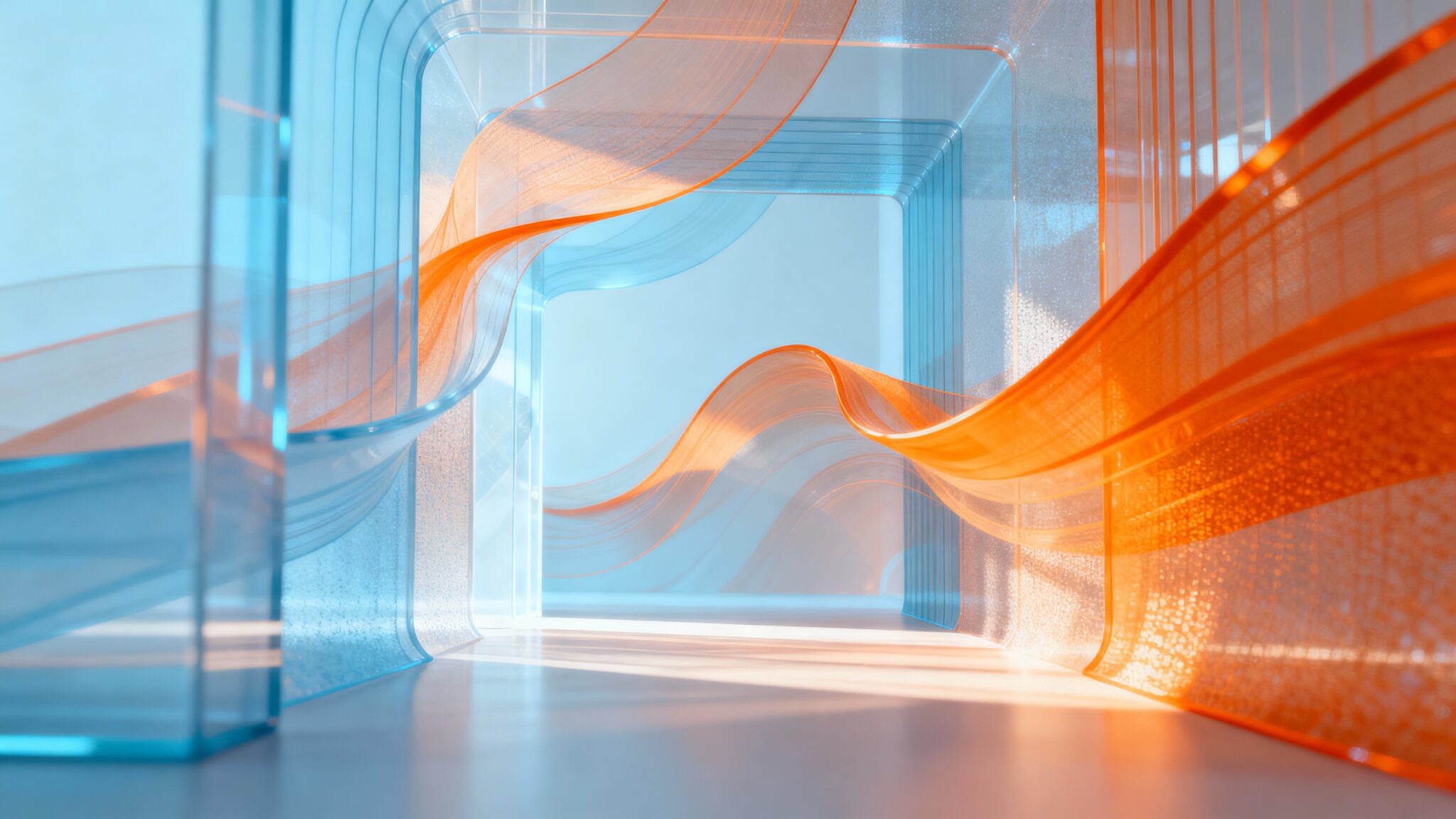
ここではランディングページの目的と、ビジネスにおける役割について解説します。
コンバージョン(申込み・購入)を最大化するための設計
ランディングページの目的は、コンバージョン率を最大化すること。コンバージョンとは、訪問者が望ましいアクションを起こすことを指します。例えば、商品の購入、サービスの申込み、資料請求、会員登録などが該当します。
ランディングページはあらゆる要素がコンバージョンに向けて最適化されています。不要な情報は削ぎ落とし、必要な情報だけを適切な順序で配置します。
たとえば、商品の特徴を説明した後に、利用者の声を紹介。限定特典を提示して、最後に申込みボタンを配置する。このような設計で訪問者の購買意欲を高め、自然とを起こしたくなる心理へ導くのです。
また、フォームの項目数を最小限に抑えたり、入力しやすいデザインにしたりする工夫も施されます。細部にわたってコンバージョンを意識した工夫が施されています。
広告・SNS・メールなど外部導線から成果を生み出す
ランディングページは、さまざまな導線からの流入を成果へつなげる役割を担っています。リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告、メルマガ、アフィリエイトなどからの訪問者を受け止める受け皿として機能しています。
それぞれの流入元によって、訪問者の属性や関心度は異なります。広告をクリックした人は、ある程度興味を持っている状態ですが、まだ購入を決めているわけではありません。
ランディングページは、このような「興味はあるが迷っている」状態の訪問者に対して、商品やサービスの価値を効果的に伝え、購入への後押しをする役割を果たします。流入元ごとに異なるランディングページを用意することで、それぞれの訪問者に最適化されたメッセージを届けることも可能になります。
外部導線からの流入を成果へつなげることが、ランディングページの役割なのです。
見込み顧客の心理を1ページで完結して導くストーリー設計
見込み顧客の心理変化を考慮したストーリー設計もランディングページの役割。訪問者の疑問や不安から購入決定まで、心理的な流れに沿って情報を配置します。
典型的なストーリー構成としては、まず共感を得るための問題提起から始まります。「こんな悩みはありませんか?」といった形で、訪問者の課題に寄り添います。
次に、その問題を解決する方法として商品やサービスを提示。なぜそれが最適な解決策なのかを論理的に説明します。さらに、実際の利用者の声や実績データを示すことで信頼性を高めます。最後に今すぐ行動すべき理由(限定性や緊急性)を提示する流れです。
心理的な流れを1ページで完結させることで、訪問者は自然と購入へ導かれていきます。途中で他のページへ移動する必要がなく、最後まで読み進めてもらえるのです。
ランディングページの特徴

効果的なランディングページには、共通する特徴があります。
縦長構成で1ページ完結
ランディングページの最も顕著な特徴は、縦長の1ページ完結型構成です。訪問者はスクロールするだけで、必要な情報をすべて得ることができます。
この構成には明確な理由があります。人は情報を順序立てて理解する傾向があるからです。上から下へと自然な流れで情報を配置することで、理解を深めてもらえるのです。
また、1ページに情報を集約することで、訪問者の離脱を防ぐ効果もあります。複数ページに分かれていると、ページ移動のたびに離脱のリスクが生じます。しかし、1ページ完結なら最後まで読んでもらえる可能性が高まります。
縦長構成は、スマートフォンでの閲覧にも適しています。スマホユーザーは縦スクロールに慣れているため、自然な操作で情報を取得できるのです。このような理由から、現代のランディングページは縦長構成が主流となっているのです。
他ページへのリンクが少なく集中導線を作る
ランディングページでは、意図的に他ページへのリンクを最小限に抑えています。通常のWebサイトにあるようなグローバルナビゲーションやフッターリンクを排除し、訪問者の選択肢を限定することで、コンバージョンへの集中導線を作り出しています。
心理学的に、選択肢が多すぎると人は決断を先延ばしにする傾向があります。これを「選択のパラドックス」と呼びます。ランディングページは、この心理を考慮して、「申込む」か「離脱する」かの二択に絞ることで、決断を促しやすくしているのです。
ただし、プライバシーポリシーや特定商取引法に基づく表記など、法的に必要なリンクは設置されます。これらは通常、ページの最下部に小さく配置され、メインの導線を妨げないよう配慮されています。
ファーストビューが命
ランディングページにおいて、ファーストビュー(最初に表示される画面)は極めて重要な要素です。訪問者は最初の数秒で、そのページを読み続けるか離脱するかを判断すると言われています。
そのため、ファーストビューには商品やサービスの価値を端的に伝えるキャッチコピー、魅力的なビジュアル、明確なベネフィットが配置されます。「何を提供しているのか」「誰のためのものか」「どんな価値があるのか」が一目でわかるよう工夫されているのです。
また、スクロールを促すような視覚的な仕掛けも重要です。画面の下部に続きがあることを示唆するデザインや、矢印などの視覚的なガイドを配置することで、訪問者に「もっと読みたい」と思わせる工夫がなされています。
強いコピーライティングとビジュアル訴求が鍵
ランディングページの成否を左右する重要な要素として、コピーライティングとビジュアルの力があります。単に商品の機能を説明するだけでなく、訪問者の感情に訴えかける言葉選びが求められます。
効果的なコピーライティングでは、ベネフィット(利用者が得られる利益)を中心に訴求します。「この商品を使えば、あなたの生活がこう変わる」という未来像を具体的に描き出すことで、購買意欲を刺激するのです。
ビジュアル面では、商品の魅力を最大限に引き出す写真や動画、インフォグラフィックなどを活用します。文字だけでは伝わりにくい情報も、視覚的に表現することで直感的に理解してもらえます。
さらに、配色やフォント選びも重要です。ターゲット層に合わせた色使いや、読みやすさを考慮したフォントサイズなど、細部にまでこだわることで、全体的な説得力を高めていくのです。
ランディングページのメリットとデメリット

ランディングページを活用する前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。両面を把握することで、より効果的な運用が可能になります。
メリット
ランディングページには、ビジネスの成果を大きく向上させる3つの主要なメリットがあります。
CV率を高めやすい
ランディングページのメリットは、高いコンバージョン率を実現しやすいこと。余計な情報や選択肢を排除し、一つの目的に特化することで、訪問者を迷わせることなくアクションへと導けます。通常のWebサイトと比較しても、高いコンバージョン率を達成する傾向にあります。
情報を理想的な順序で伝えられる
縦長の1ページ構成により、情報を戦略的な順序で配置できます。訪問者の心理状態に合わせて、共感→興味→欲求→行動という流れで情報を提示できるため、自然な形で購買意欲を高めていくことができます。この順序立てた情報提供により、商品やサービスの価値を最大限に伝えることが可能になります。
分析・改善がしやすい
1ページ完結型のため、どこで離脱したか、どの要素が効果的かといった分析が容易です。ヒートマップツールを使えば、訪問者がどこまでスクロールしたか、どのボタンをクリックしたかが一目瞭然になります。このデータを基にA/Bテストを実施し、継続的な改善を行うことで、さらなる成果向上が期待できます。
デメリット
一方で、ランディングページにはいくつかの課題も存在します。これらを理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。
SEOに弱く、集客が広告依存になりがち
ランディングページは1ページで構成されているため、SEOで上位表示を狙うのが困難です。コンテンツ量が限られ、内部リンクも少ないため、検索エンジンからの評価を得にくいという特性があります。結果として、集客は広告に依存することが多く、継続的な広告費が必要になるケースが一般的です。
制作コストがかかる場合もある
効果的なランディングページを制作するには、専門的なスキルが必要です。コピーライティング、デザイン、コーディングなど、各分野のプロフェッショナルに依頼すると、制作費が高額になることがあります。また、商品やサービスごとに個別のランディングページを作る必要がある場合、その分コストも増加します。
一度作って終わりではなく継続改善が必要
ランディングページは作って公開したら終わりではありません。市場環境の変化、競合の動向、訪問者のニーズの変化に応じて、継続的な改善が必要になります。定期的なA/Bテストの実施、コンテンツの更新、デザインの最適化など、運用にも手間とコストがかかることを理解しておきましょう。
ランディングページの種類と活用シーン

ランディングページは、目的や業界によってさまざまな種類があります。それぞれの特徴と活用シーンを理解することで、自社に最適なランディングページを選択できるようになります。
商品・サービス訴求型(例:キャンペーンLP)
最も一般的なランディングページが、商品やサービスを直接販売することを目的としたタイプです。新商品の発売、期間限定キャンペーン、特別価格での提供など、具体的な商品・サービスの購入を促すために活用されます。
このタイプのランディングページでは、商品の特徴やメリットを詳細に説明し、競合との差別化ポイントを明確に打ち出します。価格や特典情報を目立たせ、「今すぐ購入すべき理由」を強調することが重要です。
化粧品、健康食品、家電製品など、BtoCビジネスで特に多く見られるタイプですが、BtoBでもソフトウェアやサービスの販売で活用されています。季節商品や期間限定商品の場合は、緊急性を演出することで、より高い成果を期待できます。
資料請求・セミナー申込型
すぐに購入を決められない高額商品や、検討期間が長いサービスの場合、まず資料請求やセミナー参加を促すランディングページが効果的です。不動産、金融商品、教育サービスなどでよく活用されています。
このタイプでは、無料で価値ある情報を提供することで、見込み顧客の連絡先を獲得することが目的となります。「無料」であることを強調し、資料やセミナーで得られる具体的なメリットを明示することが大切です。
フォームの項目は最小限に抑え、心理的なハードルを下げることも重要なポイントです。獲得した見込み顧客に対しては、その後メールマーケティングなどで関係を構築し、最終的な成約へとつなげていきます。
求人・採用LP
人材採用に特化したランディングページも、近年増加しています。求職者に向けて企業の魅力や働きがい、具体的な待遇などを訴求し、応募を促すことが目的です。
採用LPでは、実際に働いている社員の声や、職場の雰囲気が伝わる写真・動画を多用することが特徴的です。仕事内容だけでなく、企業文化や成長機会、福利厚生など、求職者が重視するポイントを網羅的に伝えます。
特に新卒採用や中途採用の大規模キャンペーンでは、専用のランディングページを制作することで、他の求人媒体との差別化を図ることができます。応募のハードルを下げるため、まずは説明会参加や資料請求から始めるケースも多く見られます。
ブランディング・ストーリー型LP
直接的な販売や申込みではなく、ブランドイメージの向上や企業理念の浸透を目的としたランディングページもあります。新ブランドの立ち上げ、周年記念、社会貢献活動のPRなどで活用されます。
このタイプでは、感動的なストーリーや美しいビジュアルを中心に構成し、訪問者の感情に訴えかけます。創業者の想い、商品開発の背景、社会課題への取り組みなど、ブランドの価値観を深く伝えることが目的です。
コンバージョンは必ずしも明確ではありませんが、SNSでのシェアやメールマガジン登録など、緩やかな関係構築を促すことが多いです。長期的なブランド価値向上に貢献し、将来的な購買行動につながることを期待して制作されます。
効果的なランディングページの作り方

ランディングページ制作は専門的に見えるかもしれませんが、基本的なステップを理解すれば、初心者でも効果的なページを作ることができます。ここでは、制作の流れを5つのステップに分けて解説します。
①目的・ターゲット・訴求内容を明確にする
ランディングページ制作の第一歩は、明確な戦略を立てることです。まず「このランディングページで何を達成したいのか」という目的を具体的に定義します。商品購入なのか、資料請求なのか、会員登録なのか、ゴールを明確にすることが重要です。
次に、ターゲットとなる顧客像を詳細に設定します。年齢、性別、職業、悩み、価値観など、できるだけ具体的にペルソナを描きます。「30代の子育て中の主婦で、家事の時短に興味がある」といった具合に、リアルな人物像を想定することで、響くメッセージが見えてきます。
そして、そのターゲットに対して何を訴求するのかを決定します。商品の機能ではなく、顧客が得られる価値(ベネフィット)を中心に考えることが大切です。この3つの要素を明確にすることで、ブレのない一貫性のあるランディングページが作れるようになります。
②ワイヤーフレームを作り、ストーリーを設計
戦略が決まったら、次はページの構成を考えます。ワイヤーフレームとは、ページの骨組みとなる設計図のことです。どの順番で、どんな情報を配置するかを決めていきます。
効果的なストーリー構成の基本は、「共感→興味→信頼→行動」の流れです。まず訪問者の悩みに共感を示し、その解決策として商品を提示します。次に具体的なメリットや特徴を説明し、お客様の声や実績で信頼を築き、最後に申込みへと導きます。
各セクションで伝えるメッセージを箇条書きにし、全体の流れが自然かどうかを確認します。この段階では、デザインは考えず、情報の配置と流れだけに集中することがポイントです。紙に手書きでスケッチするだけでも十分効果的です。
③デザインで「信頼感・共感・行動喚起」を伝える
ワイヤーフレームが完成したら、いよいよデザインの段階に入ります。デザインは見た目の美しさだけでなく、訪問者の心理に働きかける重要な要素です。
信頼感を演出するには、清潔感のあるレイアウト、読みやすいフォント、適切な余白の使用が効果的です。企業ロゴや資格認定マークなども信頼性向上に貢献します。共感を生むには、ターゲット層に合わせた配色や、親近感のある写真素材を選ぶことが大切です。
行動喚起については、CTAボタンの色やサイズ、配置位置が重要になります。一般的にオレンジなどの暖色系が行動を促しやすいとされています。また、ボタンの文言も「今すぐ申し込む」「無料で試してみる」など、具体的で行動を促す表現を使用します。
④フォーム最適化・CTA配置で離脱を防ぐ
せっかく興味を持ってもらえても、フォームが使いにくかったり、CTAが見つからなかったりすると、離脱につながってしまいます。フォームの最適化は、コンバージョン率に直結する重要な要素です。
フォームの項目は必要最小限に留めます。名前とメールアドレスだけで十分な場合は、それ以上の情報を求めないようにしましょう。また、入力エラーがあった場合は、具体的に何が問題なのかを明示し、ストレスなく修正できるようにします。
CTAボタンは、ページ内に複数配置することが効果的です。ファーストビュー、中間地点、ページ最下部など、訪問者が行動を起こしたくなったタイミングですぐにアクションできるよう配慮します。ただし、過度に多すぎると押し売り感が出てしまうため、バランスが大切です。
⑤公開後はデータ分析で継続的に改善
ランディングページは公開してからが本当のスタートです。実際の訪問者の行動データを分析し、継続的に改善していくことで、成果を最大化できます。
Google Analyticsなどの分析ツールを使って、訪問者数、滞在時間、離脱率、コンバージョン率などの基本指標を確認します。特に注目すべきは、どこで離脱が多いかという点です。ヒートマップツールを使えば、訪問者がどこまでスクロールしたか、どの部分に注目したかが視覚的にわかります。
これらのデータを基に、問題のある箇所を特定し、改善策を実施します。キャッチコピーの変更、画像の差し替え、ボタンの色変更など、小さな改善の積み重ねが大きな成果につながります。A/Bテストを実施して、どちらのバージョンがより効果的かを検証することも重要です。
成果を出すなら「ホームページできるくん」のLP制作へ
最後に専門家にLP制作の依頼を検討している方は、ぜひホームページできるくんにご相談ください。プロのデザイナーが低価格で高品質のLPを制作します。
さらにランディングページの企画段階から公開後の運用までワンストップでサポート。お客様のビジネスを深く理解し、最適なLPを制作します。
本業に専念しながらWeb集客で成果を出したい方には、最適な選択肢と言えるでしょう。あなたのビジネスを次のステージへ導くランディングページ制作を全力でサポートします。
\月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/





