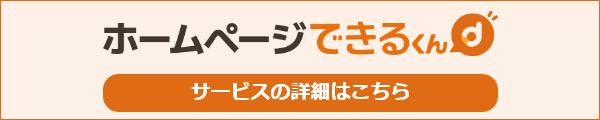お役立ち情報
ホームページデザイン料金はいくら?相場と費用内訳を解説!

「ホームページデザイン料金はいくらかかるのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか?依頼先やサイト内容によって費用は10万円台から100万円以上と幅があり、何が適正なのか分かりづらいものです。そのため「安い業者で大丈夫か」「高額を払う価値があるのか」と悩む方も多いはず。
そこで本記事ではホームページデザイン料金の基本事項から相場感、内訳や依頼先別の違い、見積もりのポイントまで徹底解説します。記事後半の「ホームページのデザイン料金に関するQ&A」では、よくある質問にもお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。
\月額1,900円〜!プロのクリエイターが質の高いホームページを制作します | ホームページできるくん/
ホームページデザイン料金の基本
はじめにホームページデザインの料金について基本的なポイントを押さえましょう。制作の全体フローや料金発生のタイミング、費用に影響する主な要素を理解しておくと、見積もり内容も把握しやすくなります。
ホームページ制作の流れと料金が発生するタイミング
ホームページ制作は、一般的に「企画・提案 → デザイン → コーディング → テスト・公開 → 納品」という工程で進み、それぞれの段階で作業に応じた費用が発生します。
ヒアリングや企画提案の段階は無料相談となる場合が多いですが、デザイン着手以降から本格的な制作費用がかかるのが通常です。
費用の支払いタイミングは契約により異なりますが、着手時に一部前払いし、納品時に残額を支払うケースなどがよく見られます。
また、サイト公開時にはドメイン取得費用やサーバー契約料といった初期費用が別途発生します。さらに公開後の保守・更新作業を依頼する場合は、制作費とは別の保守契約が必要になる点にも注意しましょう。
料金に影響する 3 つの要素(デザイン、機能、ページ数)
ホームページのデザイン料金は、主に以下の3つの要素によって左右されます。
- デザインの凝り具合
テンプレートを使った簡易なデザインか、オリジナルで凝った UI/UX デザインにするかで費用は大きく変わります。独自性の高いオリジナルデザインほどデザイナーの工数が増え、費用も上がります。 - 実装する機能の種類
お問い合わせフォームや会員登録、EC機能、ブログなど盛り込む機能が増えるほど、開発コストがかさみます。シンプルな案内サイトより、多機能なサイトの方が費用は高くなりがちです。 - ページ数(サイト規模)
ページの数が多いほどデザイン・コーディングの作業量が増えるため、料金も上昇します。1ページ完結のランディングページと10ページ以上の企業サイトでは、後者のほうが必要な工数が多くなります。
これらの要素は複合的に作用します。例えばページ数が多く機能も豊富なサイトは、そのぶんデザインにも時間を要し、総費用が大きくなります。
逆にページ数や機能を絞ればテンプレート活用などで費用を抑えることも可能です。まずは自社サイトに必要な要素を見極めて、適切な予算を設定しましょう。
テンプレート vs オーダーメイドの料金差とは?
ホームページ制作ではテンプレート(既成のデザイン)を利用する方法と、オーダーメイドでデザインを一から作る方法があります。この違いは料金に大きく影響します。
テンプレートを使う場合、あらかじめ用意されたデザインテーマやノーコードツール(Wix や STUDIO など)を流用して制作するため、制作費用を大幅に抑えられるのがメリットです。
テンプレート利用の小規模サイトなら制作費が10万円前後で収まるケースもあります。ただし、その分デザインの自由度や独自性は限定され、他社サイトと似た見た目になる可能性があります。
一方、オーダーメイドのオリジナルデザインは、ゼロから企業の要望に沿ってデザイナーが設計します。自由度が高くブランドイメージに合ったサイトを実現できますが、費用はテンプレート利用に比べて格段に高くなります。
凝ったオーダーメイドデザインのサイトでは20万~100万円程度の予算が必要になることもあります。テンプレートを部分的にカスタマイズする方法もありますが、その場合も費用は「テンプレートそのまま」より増加します。
タイプ別で見る!ホームページデザインの料金相場

続いて、ホームページの種類・規模ごとにデザイン料金の相場感を見てみましょう。サイトの目的によって必要な機能やページ数が異なるため、費用の目安もケースごとに変わります。ここでは大きく3つのタイプについて、その相場を解説します。
個人向け・小規模サイトの相場(10万円〜)
個人事業主や小規模ビジネス向けで、ページ数が少なくシンプルなホームページの場合、デザイン料金の相場は概ね10万円台からが目安です。
具体的にはトップページ+会社・サービス案内+問い合わせフォーム程度の5ページ以内の構成であれば、10万〜20万円前後で制作可能なケースが多いでしょう。
この価格帯ではテンプレートデザインの活用や、比較的安価なフリーランスへの依頼によってコストを抑えることが一般的です。
たとえばフリーのWebデザイナーにテンプレートベースで作ってもらう、またはWordPressの既存テーマを用いて自作するなどの方法で、低予算でもホームページを持つことができます。
ただし、予算が低い分対応範囲が限定されがちな点には注意が必要です。デザインの細かなカスタマイズが難しい、納品後のサポートが手薄になる、といった可能性もあります。
依頼前にどこまで対応してもらえるのか(レスポンシブ対応や基本的な SEO 対策は含まれるか等)を確認し、必要最低限の品質を確保しましょう。
中小企業向け・コーポレートサイトの相場(30万円〜)
中小企業のコーポレートサイトや店舗の公式サイトなど、内容が充実したサイトの場合、30万円以上の予算を見ておくのが一般的です。
ページ数が10~20ページ程度で、会社概要・事業紹介・製品サービス情報・採用情報・問い合わせフォームなど複数のコンテンツを含むサイトがこの範囲に該当します。
このクラスのサイトでは、デザインもテンプレート流用ではなくオリジナルデザインを適用することが多く、自社のブランドイメージに合わせたUIデザインにこだわります。
また、自社で更新できるよう CMS(例: WordPress)の導入を行うケースも一般的です。そうした手間を含め、費用相場は30万~100万円前後と幅広くなります。
制作をWeb制作会社に依頼する場合、中堅の制作会社であればこの価格帯で対応可能ですが、要求する機能やデザイン品質が高いほど費用も上振れします(多言語対応や特殊なシステム連携が必要な場合など)。
プロジェクト開始前にしっかりと要件の優先順位と予算のすり合わせを行い、コストに見合った内容になるよう調整することが重要です。
ECサイトや多機能サイトの相場(50万円以上)
商品販売を目的とするECサイトや、会員機能・予約システムなど高度な機能を持つWebサイトの場合、デザイン料金は50万円以上が一つの目安となります。
ECサイトは、一般的な企業サイトに比べて必要な機能が格段に多く、商品の登録管理、カート・決済機能、会員ログイン、在庫データ連携などを実装するため、その分開発コストも高額になります。
また多機能サイトでは、ユーザーが快適に操作できるようUI/UX設計に時間をかける必要があり、さらにセキュリティ対策やサーバー負荷への配慮など技術的な作業も増えます。
こうした要素から、ECや大規模サイトの制作には100万円以上の予算が投じられるケースも珍しくありません。
小規模なオンラインショップであれば、ShopifyやBASEといったサービスを利用して安価に開設することも可能ですが、企業の本格的なECサイトや独自システム構築が伴うサイトでは、開発チームを組んで取り組む大掛かりなプロジェクトとなりがちです。
そのため、機能要件に応じて十分な予算を確保することが成功の鍵となります。
\月額1,900円〜!プロのクリエイターが質の高いホームページを制作 | ホームページできるくん/
ホームページの種類・規模ごとのデザイン料金相場
| サイトタイプ | 対象 | ページ数・構成 | 費用相場 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 個人向け・小規模サイト | • 個人事業主 • 小規模ビジネス | • 5ページ以内 • トップページ • 会社・サービス案内 • 問い合わせフォーム | 10万〜20万円 | コスト削減方法: • テンプレートデザイン活用 • フリーランスへの依頼 • WordPressの既存テーマ使用 注意点: • 対応範囲が限定的 • デザインのカスタマイズが難しい • 納品後のサポートが手薄な可能性 • レスポンシブ対応やSEO対策の確認が必要 |
| 中小企業向け・コーポレートサイト | • 中小企業 • 店舗の公式サイト | • 10〜20ページ程度 • 会社概要 • 事業紹介 • 製品サービス情報 • 採用情報 • 問い合わせフォーム | 30万〜100万円 | 特徴: • オリジナルデザイン • ブランドイメージに合わせたUIデザイン • CMS(WordPress等)導入 費用変動要因: • 多言語対応 • 特殊なシステム連携 • デザイン品質の要求レベル ポイント: 要件の優先順位と予算のすり合わせが重要 |
| ECサイト・多機能サイト | • オンラインショップ • 会員機能付きサイト • 予約システム搭載サイト | • 商品登録管理 • カート・決済機能 • 会員ログイン • 在庫データ連携 • その他高度な機能 | 50万円以上 (100万円以上も一般的) | 必要な要素: • UI/UX設計への時間投資 • セキュリティ対策 • サーバー負荷への配慮 低予算の選択肢: • Shopify、BASEなどのサービス利用 本格的なサイト: • 開発チームによる大規模プロジェクト • 機能要件に応じた十分な予算確保が必要 |
格安制作と高額案件の違いとは?
同じホームページ制作でも、数十万円以下でできる場合と数百万円かかる場合があります。その違いは主に対応範囲と品質の差です。
- 格安制作
既存テンプレートの流用や機能を最低限に絞るなど、制作側の手間を省く工夫で低価格を実現しています。その分、デザインの独自性や作り込みは限定的で、納品後のフォローも最小限となるケースが多いです。 - 高額制作
企画段階からじっくりヒアリングを行い、オリジナルデザインや豊富な機能実装、プロによるコンテンツ作成やSEO対策まで手厚く対応することが多くなります。当然ながら工数が多いため費用も高くなりますが、サイトの完成度や成果にこだわる場合に選ばれるアプローチです。
低価格には低価格なりの理由があり、高額には高額なりの理由があります。どこに重点を置くかによって適切な予算感は変わってきますので、費用と内容のバランスを見極めて選択しましょう。
料金に含まれる主な費用項目とその内訳

次に、ホームページ制作において主にどのような項目に費用が発生するのか、その内訳を確認します。見積もりを見る際は、各費用項目の内容を理解しておくことで、提示額が適正か判断しやすくなります。
デザイン費(UI/UX設計、ビジュアルデザイン)
サイトの見た目や使い勝手を設計・制作するための費用です。具体的にはサイト構造のプランニング(UI/UX設計)から、各ページのビジュアルデザイン作成、デザイン修正対応、画像素材の加工調整などが含まれます。
テンプレートを軽く調整する程度であれば数万円、オリジナルデザインでしっかり作り込む場合は20万~50万円以上と、要求度合いによって幅があります。
コーディング費(HTML/CSS/レスポンシブ対応など)
デザインをWebページとして実装する作業の費用です。HTML/CSSによるページ構築やレスポンシブ対応(スマホ等でも崩れないよう調整)、必要に応じたJavaScriptでの動的機能実装などを行います。
ページ数と機能の複雑さによって工数が変動し、サイト全体で10万~30万円程度が一つの目安と言われます。
CMS構築(WordPress導入など)
WordPressなどのコンテンツ管理システムを導入・設定するための費用です。CMSソフトのインストールと初期設定、サイトデザインのテーマ適用(または開発)、必要プラグインの設定、運用マニュアル作成などの作業が該当します。
ブログ機能を追加する程度なら数万円、サイト全体をCMS化するなら10万~20万円前後が一般的です。独自開発のCMSや特殊な要件がある場合は、さらに費用が掛かります。
写真・イラスト・ライティングなどのオプション費用
案件によっては、写真素材の購入費やライティング費、イラスト・動画制作費などのオプション費用が発生することもあります。
これは必要に応じて追加で依頼する部分で、たとえば有料のストックフォト画像を使う場合の購入費用、プロのライターに文章作成を依頼する場合の原稿料などです。
なお、セキュリティ強化や高度な SEO 設定がオプション扱いとなっている場合もあります。見積もりにオプション項目がある場合は、その内容と金額を事前に確認し、自分たちに必要なものか検討しましょう。
ホームページ制作の費用内訳
| 費用項目 | 作業内容 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デザイン費 (UI/UX設計、ビジュアルデザイン) | • サイト構造のプランニング(UI/UX設計) • 各ページのビジュアルデザイン作成 • デザイン修正対応 • 画像素材の加工調整 | • テンプレート調整:数万円 • オリジナルデザイン:20万〜50万円以上 | 要求度合いによって費用に幅がある |
| コーディング費 (HTML/CSS/レスポンシブ対応など) | • HTML/CSSによるページ構築 • レスポンシブ対応(スマホ等での表示調整) • JavaScriptでの動的機能実装 | サイト全体で10万〜30万円程度 | ページ数と機能の複雑さによって工数が変動 |
| CMS構築 (WordPress導入など) | • CMSソフトのインストールと初期設定 • サイトデザインのテーマ適用(または開発) • 必要プラグインの設定 • 運用マニュアル作成 | • ブログ機能追加:数万円 • サイト全体のCMS化:10万〜20万円 | 独自開発のCMSや特殊要件がある場合はさらに高額 |
| オプション費用 | • 写真素材の購入費 • ライティング費(原稿作成) • イラスト・動画制作費 • セキュリティ強化 • 高度なSEO設定 | 案件により変動 | • 必要に応じて追加で依頼 • 見積もりのオプション項目は内容と金額を事前確認 • 自社に必要なものか検討が重要 |
制作会社・フリーランス・自作の比較
続いて、制作会社、フリーランス、自作それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 依頼先 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 制作会社 | • デザインからコーディング、CMS構築まで専門スタッフが担当 • 一定以上の品質が期待できる • 保守などアフターサポート体制が整っている • 納期やセキュリティ対応なども含め安心して任せられる | • 見積もり金額は高め • 進行フローが確立されている分、細かな修正や追加要望への対応には別途費用がかかる • 対応範囲が契約で明確に区切られる傾向 |
| フリーランス | • 中間マージンがない分、制作会社より安い • 柔軟に対応してもらいやすい • コミュニケーションが密に取れる | • 依頼先によって仕上がり品質に差が出やすい • 大規模案件は対応できないことも • 保守・更新を継続依頼できないことも |
| 自作 (Wix、STUDIO、WordPressなど) | • 必要なのはサーバー代や独自ドメイン取得費程度 • WixやSTUDIOなどのノーコードサービスやWordPressを利用すれば低コストでサイト構築が可能 | • 思い通りのサイトを作るには相応の時間と労力が必要 • デザインの微調整やSEO設定など、専門知識がないと難しい • サイトの不具合や更新作業も自分で対処が必要 • 本業の合間に対応するのは負担 • ITにある程度精通している方向け |
見積もりの見方と失敗しない業者選びのポイント

最後に、ホームページ制作を依頼する際の見積もりチェックポイントと業者選びのコツについて説明します。適正な契約を結ぶために、以下を参考にしてください。
相場より安すぎる見積もりに注意すべき理由
相場とかけ離れて極端に安い見積もりを提示された場合、その理由を慎重に見極めましょう。サービス内容が大幅に簡略化されていたり、品質面でのリスクが潜んでいる可能性があります。
例えば「デザインはテンプレートそのまま」「ページ数がごく少ない前提」「機能追加は別料金」など、低価格の理由を確認してください。また、あまりに安い場合は本当に完成まで対応してもらえるのか、実績や信頼性もチェックが必要です。
一社だけの価格を見て判断せず、必ず他の業者からも見積もりを取り比較しましょう。同じ条件で複数社に依頼することで、その見積もりが適正かどうか判断しやすくなります。
追加費用がかかりやすいポイントとは?
契約後に追加費用が発生しやすいポイントも把握しておきましょう。当初の見積もり範囲に含まれていない修正や変更が生じた場合に費用増となるケースが多いです。
例えば、デザイン修正回数の上限を超えた追加対応、予定にない新ページの追加、用意できなかった素材の追加依頼、公開後の更新作業依頼などが該当します。
契約前に「どこまでが基本料金に含まれるか」「追加対応が必要な場合の料金体系」について確認し、可能な限り認識齟齬をなくしておきましょう。
制作会社選びでチェックすべき項目リスト
業者選びで失敗しないために、以下のポイントをチェックしましょう。
- 制作実績
過去の制作事例を確認し、自社のイメージに近いサイトを手掛けているか、業種の知識がありそうかを見ます。 - 見積もり内容の明確さ
提示された見積もりが項目ごとに明細化されているか、内容に納得できるかを確認します。不明点は質問し、丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。 - コミュニケーション
問い合わせや見積もり依頼時の対応が迅速かつ誠実かどうかは重要です。やり取りがスムーズな相手だと、制作中の意思疎通も円滑に進みます。 - サポート体制
納品後の更新サポートや保守サービスの有無、内容をチェックします。リリース後も長く付き合えるパートナーかどうか判断しましょう。
ホームページのデザイン料金に関するQ&A

最後に、ホームページのデザイン料金についてよくある質問とその回答を紹介します。
Q: SEO対策は料金に含まれる?
A: 基本的な内部SEO対応(タイトルやメタタグの適切な設定など)は制作時に行ってもらえる場合がありますが、本格的なSEO対策は通常、制作費用には含まれていません。
集客を目的としたSEO施策を期待する場合は、別途オプション契約や専門業者への依頼を検討しましょう。
Q: 保守・更新費用は別途必要?
A: はい、多くの場合保守・更新サービスは別契約となります。サイト公開後、内容の更新や不具合対応、定期メンテナンスを制作会社に依頼したい場合は、月額固定費の保守契約(保守費用)を結ぶケースが一般的です(費用相場は更新頻度や内容によりますが数千円〜数万円/月程度)。
保守契約を結ばずに自社対応することも可能ですが、その場合、ソフトウェアの更新管理やトラブル対応は自己責任になります。
Q: 相見積もりは取ったほうがいい?
A: はい。2~3社程度から相見積もりを取ることをおすすめです。他社と比較することで相場感がつかめ、各社の提案内容や対応の違いも見えてきます。
各社に伝える要件は可能な限り同じに揃え、純粋に金額と内容を比較しましょう。価格だけでなくコミュニケーションの質なども含めて総合的に判断すると、より満足度の高い依頼先を選ぶことができます。
納得のいく料金で、効果的なホームページを作るために
ホームページのデザイン費用は、一概に「○○円」と言い切れないほど幅があり、様々な要因で数万円にも数百万円にもなり得ます。大切なのは、自分の目的と予算に合った形でホームページを制作することです。
相場観や内訳のポイントを理解していれば、見積もり比較の際にも適切な判断ができますし、費用を抑える工夫や信頼できる業者の選び方を知っていれば、限られた予算内でも満足度の高いサイトを作ることができるでしょう。
正しい知識を持って複数の見積もりを比較し、費用面だけでなく自分たちに合ったパートナーかどうかも見極めて、納得のいくホームページ制作を実現させましょう。
\月額1,900円〜プロのクリエイターが質の高いホームページを制作します | ホームページできるくん/