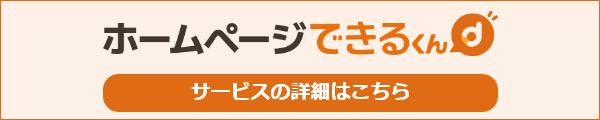お役立ち情報
ホームページデザイン費用の相場は?内訳やコスト削減術も解説

ホームページを作りたいけれど、デザイン費用がいくらかかるのか分からず不安を感じていませんか。
実は、ホームページのデザイン費用は規模や目的によって大きな幅があります。しかし、相場を知らないまま依頼すると高額な見積もりを受け入れてしまうことも。また、安すぎる業者を選んで、失敗する恐れもあります。
そこで本記事ではホームページデザイン費用の相場を詳しく解説。費用を決める要素や依頼先による違い、コストを抑える具体的な方法までお伝えします。予算に合ったホームページ制作を実現したい方はぜひ最後までお読みください。
\ホームページできるくんは、月額1,900円〜プロのデザイナーが高品質のホームページを提供!/
ホームページデザイン料金早見表
まず最初に、ホームページデザインにかかる費用の全体像を早見表で確認しましょう。この表を参考にすれば、自社に必要な予算の目安がすぐに把握できます。
ページ単価の相場一覧
| ページ種別 | 料金相場 | 特徴・備考 |
| トップページ | 10万〜20万円 | 企業の顔となる重要なページのため、デザインに最も工数がかかる |
| 下層ページ | 3万〜5万円/ページ | 1ページあたりの単価で制作可能 |
| ランディングページ(LP) | 10万〜50万円 | ・シンプルな構成:10万円程度・コンバージョン重視の凝ったデザイン:50万円超 |
これらの単価は、オリジナルデザインを前提とした金額。テンプレートを活用する場合は、この半額以下で制作できることもあります。
規模別相場の詳細
| サイト規模 | ページ数 | 料金相場 | 主な利用者・特徴 |
| 小規模サイト | 5ページ以下 | 10万〜100万円 | スタートアップ企業や個人事業主が最初に作るサイトとして最も一般的※品質により幅がある |
| 中規模サイト | 10ページ程度 | 80万〜150万円 | オリジナルデザインの場合の目安 |
| 大規模サイト | 20ページ以上 | 150万〜500万円 | コンテンツ量が多い分、デザインの統一性を保ちながら制作する難易度が上がるため高額になる |
依頼先別の料金比較
| 依頼先 | 料金相場 | 詳細・特徴 |
| 自作(ノーコードツール) | 0〜5万円 | Wix、Jimdoなどのサービス利用で月額数千円で運営可能 |
| フリーランス | 10万〜30万円 | 個人のデザイナー・エンジニアへの依頼 |
| 制作会社 | 30万円以上 | 一般的な制作会社への依頼大手制作会社なら100万円超も珍しくない |
| クラウドソーシング | 5万〜30万円 | ランサーズ、クラウドワークスなどのプラットフォーム経由での依頼 |
【目的・種類別】ホームページデザイン費用相場
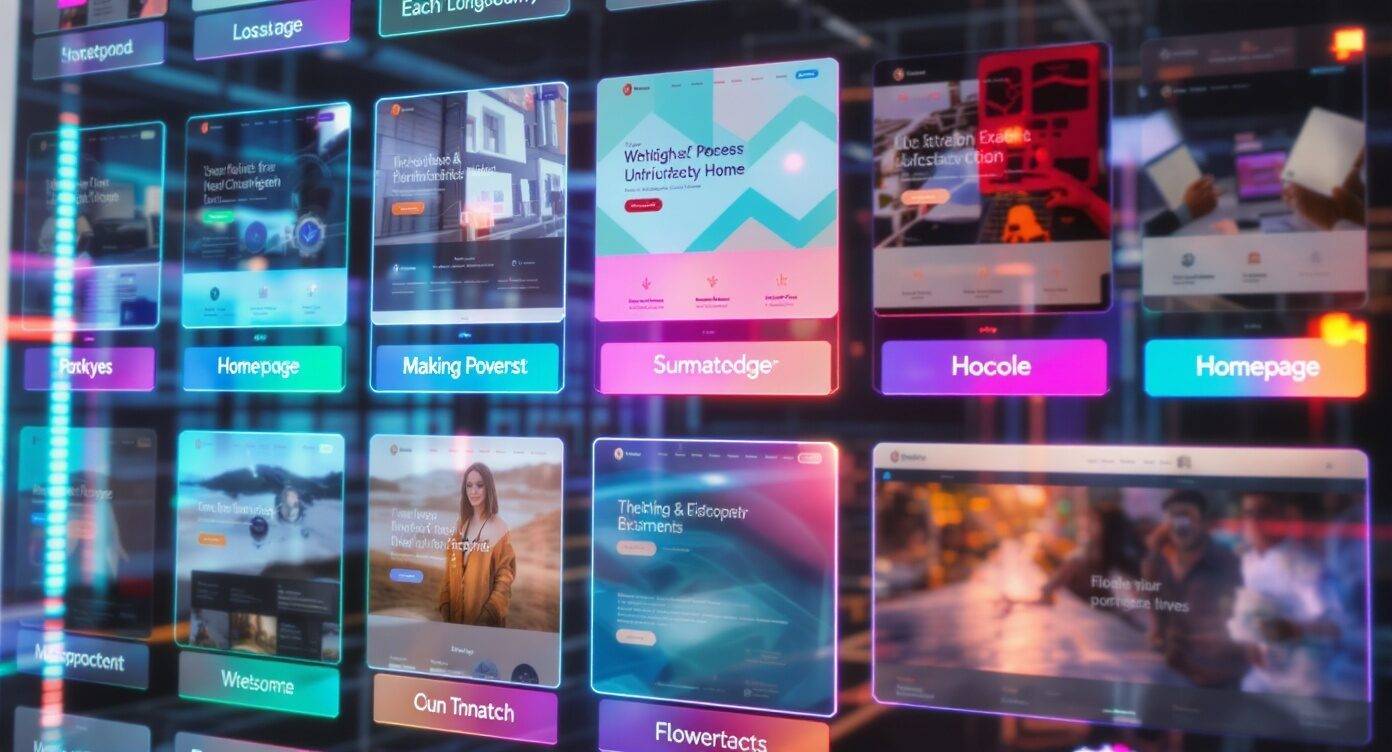
サイトの目的や種類によって、必要な機能やページ数が異なるため、費用も大きく変わります。ここでは、代表的なサイト種類ごとの費用相場と内訳を詳しく見ていきましょう。
企業サイト(30万〜50万円)の内訳
| 項目 | 費用 | 構成比 |
| デザイン費 | 15万〜25万円 | 約40-50% |
| コーディング費 | 10万〜15万円 | 約25-30% |
| ディレクション費 | 5万〜10万円 | 約15-20% |
| 合計 | 30万〜50万円 | 100% |
基本的な構成として、トップページ、会社概要、サービス紹介、実績紹介、お問い合わせの5ページから10ページが含まれます。お問い合わせフォームやGoogleマップの埋め込みなど、基本的な機能も含まれている場合が多いです。
ブランディングを重視する企業の場合、オリジナルイラストやプロカメラマンによる撮影を追加することで、100万円を超えるケースもあります。
ECサイト(50万〜100万円)の内訳
| 項目 | 費用 | 含まれる内容 |
| 基本デザイン | 20万〜30万円 | ・トップページ・商品一覧ページ・商品詳細ページ |
| カート機能実装 | 15万〜25万円 | ・商品の追加・削除機能・在庫管理機能 |
| 初期商品登録 | 10万〜20万円 | 50商品程度の登録作業 |
| 決済システム連携 | 5万〜15万円 | 各種決済方法との連携設定 |
| 合計 | 50万〜100万円 | – |
本格的なネットショップを構築する場合、会員機能やポイント機能、レビュー機能なども実装することになり、200万〜300万円規模の投資が必要になることもあるでしょう。
ランディングページ(10万〜50万円)の詳細
| 価格帯 | 費用 | 仕様・特徴 | 含まれる内容 |
| シンプル | 10万円程度 | 情報を伝えることが主目的 | 基本的なデザインと情報掲載 |
| コンバージョン重視 | 50万円超 | 成約率向上を目的とした設計 | ・A/Bテストの実施・ヒートマップ分析 |
| 動画・アニメーション付き | 追加費用発生 | 視覚的インパクトを重視 | ・アニメーション制作・動画組み込み※基本料金に上乗せ |
また、アニメーションや動画を組み込む場合は、さらに費用が上乗せされます。
採用サイトの相場
| 仕様 | 費用 | 含まれる内容 |
| シンプル構成 | 30-50万円 | ・募集要項・応募フォーム |
| 充実構成 | 100万円前後 | ・社員インタビュー・職場紹介動画・募集要項・応募フォーム |
ブランドサイトの相場
| 仕様 | 費用 | 含まれる内容 |
| 標準構成 | コンテンツの充実度により変動 | 基本的なブランド情報 |
| 充実構成 | 150万〜300万円 | ・ブランドストーリー・製品開発秘話・丁寧に作り込んだコンテンツ |
ポートフォリオサイト(5万〜20万円)の費用
| 制作方法 | 費用 | 特徴・備考 |
| 外注制作(基本) | 5万〜20万円 | 作品を見せることが主目的のシンプルな構成で十分な場合が多い |
| ノーコードツールで自作 | 年間数千円程度 | ドメイン代とサーバー代のみで制作可能 |
| オリジナルデザイン制作 | 10万〜20万円 | プロとしての信頼性を高めたい場合に推奨独自性のあるデザインで差別化可能 |
\ホームページできるくんなら月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを提供!/
ホームページデザイン費用に影響を与える5つの要素

ホームページのデザイン費用は、さまざまな要素によって変動します。ここでは、料金に大きく影響する5つの要素について詳しく解説していきましょう。
ページ数・構成のボリューム
| 項目 | 費用・影響 | 備考 |
| 1ページ追加あたりの費用 | 3万〜5万円 | ページ数が増えるほどデザイン作業も増加 |
| 10ページと20ページの差額 | 30万〜50万円 | 10ページ分の追加による費用差 |
| コスト削減方法 | 追加コストを抑制可能 | ・同じレイアウトを使い回す・ブログ記事やニュースページなどテンプレート化・効率的に制作可能 |
オリジナルデザインの有無
| デザイン方式 | 費用 | 内容・特徴 |
| オリジナルデザイン | 50万円以上 | ・デザイナーが一から作り込む・企業のブランドイメージに合わせて制作・色使い、レイアウト、アイコンなどすべてをカスタマイズ |
| テンプレート活用 | 10万〜20万円程度 | ・既存テンプレートをベースに制作・カスタマイズ費用を含めた金額 |
| WordPressテーマ利用 | 1万〜3万円+カスタマイズ費 | ・有料テーマを購入・多少のカスタマイズを加えて使用 |
写真・イラスト・アイコン素材の制作
| 素材の種類 | 費用 | 用途・備考 |
| プロカメラマン撮影 | 5万〜10万円/日 | 商品撮影、社員の写真撮影など、オリジナル写真が必要な場合 |
| オリジナルイラスト | 1万〜3万円/点 | 1点あたりの制作費用 |
| アイコンセット | 5万〜10万円 | 10〜20個のセット制作費用 |
レスポンシブ対応・UI/UX設計
| 項目 | 追加費用 | 含まれる作業・内容 |
| レスポンシブデザイン | 10万〜20万円 | ・PC版デザイン・スマホ版の調整作業・タブレット版の調整作業※今や必須の要件 |
| UI/UX設計 | 20万〜30万円 | ・ワイヤーフレーム作成・プロトタイプ制作・ユーザーテスト※ユーザビリティを重視する場合 |
CMS対応の有無
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 追加費用 | 15万〜30万円 | WordPress等のCMS対応にかかる一般的な費用 |
| 必要な作業 | ・テーマのカスタマイズ・プラグインの設定 | 初期構築時に必要 |
| 導入メリット | 公開後の更新作業を自社で実施可能 | 長期的に更新費用を削減できるため、投資価値は十分 |
費用シミュレーター:あなたのホームページデザイン費はいくら?

自社のホームページ制作にどれくらいの費用がかかるか、簡単にシミュレーションしてみましょう。以下の項目をチェックして、概算費用を算出してください。
ページ数による費用の変動
まず、必要なページ数を確認します。ページ数に応じた料金の目安は以下の通りです。
| ページ数 | 費用目安 |
| 5ページ以下 | 30万〜50万円 |
| 6-10ページ | 50万〜80万円 |
| 11-20ページ | 80万〜150万円 |
| 21ページ以上 | 150万円以上 |
ページ数を決める際は、本当に必要なページだけに絞ることが大切です。情報を整理して統合できるページは1つにまとめることで、費用を抑えることができます。
デザインレベル別の価格差
次に、デザインのレベルを選択します。レベル別の追加費用は以下の通りです。
| デザインレベル | 追加費用 | 特徴 |
| テンプレート利用 | 10万〜20万円 | 既存のテンプレートをベースに制作 |
| セミオーダー | 30万〜50万円 | テンプレートをカスタマイズして制作 |
| フルオーダー(オリジナルデザイン) | 50万〜100万円 | 完全オリジナルのデザインを一から制作 |
予算に限りがある場合は、トップページだけオリジナルデザインにして、下層ページはテンプレートを活用するという方法もあります。
必要機能による追加費用
最後に、必要な機能を確認します。機能ごとの追加費用は以下の通りです。
| 機能 | 追加費用 | 備考 |
| 問い合わせフォーム | ほぼ0円 | 基本機能のため追加費用はほとんどかからない |
| ブログ機能 | 10-20万円 | 記事投稿・管理機能 |
| EC機能 | 50-100万円 | ショッピングカート・商品管理機能 |
| 会員機能・マイページ | 30-50万円 | ログイン・会員管理機能 |
| 予約システム | 追加費用発生 | 外部サービスとの連携が必要 |
| 決済機能 | 追加費用発生 | 外部サービスとの連携が必要 |
運用・保守費用の実態
ホームページは制作して終わりではありません。公開後の運用や保守にも費用がかかることを理解しておく必要があります。
月額保守費の相場
| プラン | 月額費用 | 含まれる内容 | 特徴 |
| 簡易保守 | 5,000円程度 | ・サーバー監視・セキュリティ更新・定期バックアップ | 基本的な保守のみ |
| 標準保守 | 5,000〜3万円 | ・サーバー監視・セキュリティ更新・定期バックアップ | 一般的な保守内容 |
| 手厚いサポート | 3万円以上 | ・24時間監視・緊急対応・サーバー監視・セキュリティ更新・定期バックアップ | サイトの規模や重要度に応じた充実サポート |
サイトの規模や重要度に応じて、適切なプランを選択することが大切です。
更新作業費の目安
まず、都度更新の場合の費用は以下になります。
| 作業内容 | 費用(1回あたり) | 詳細 |
| 簡単な更新作業 | 5,000-1万円 | テキストの修正、画像の差し替えなど |
| 大規模な更新作業 | 2万-5万円 | 新規ページの追加、大幅なレイアウト変更 |
一方、月額プランの場合は以下の費用になります。
| 更新頻度 | 月額費用 | 備考 |
| 月10回程度の更新 | 3万-5万円 | 頻繁に更新が必要なサイトの場合、都度更新よりお得 |
SEO対策・マーケティング費用
SEO対策を本格的に行う場合、費用相場は以下になります。
| 項目 | 月額費用 | 含まれる内容 |
| 本格的なSEO対策 | 3万〜50万円 | ・キーワード選定・コンテンツ作成・内部対策の実施 |
一方、Web広告の運用代行を依頼する場合、費用相場は以下になります。
| 項目 | 費用構造 | 具体例 |
| 運用手数料 | 広告費の20%程度 | 月額広告費50万円の場合→ 運用手数料10万円が追加 |
よくある失敗パターンと対策

ホームページ制作で失敗しないために、よくあるトラブルパターンと対策方法を知っておきましょう。
内訳が不明確な一式見積もりの危険性
「ホームページ制作一式50万円」といった大雑把な見積もりは要注意です。何にいくらかかるのか分からないため、追加費用が発生しやすくなります。
必ず、デザイン費、コーディング費、ディレクション費など、項目ごとの内訳を確認しましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問することが大切です。
修正回数が明記されていない場合のリスク
見積もりに修正回数が明記されていない場合、1回の修正ごとに追加費用を請求される可能性があります。通常、2回から3回の修正は無料対応が一般的です。
契約前に、何回まで無料で修正してもらえるのか必ず確認しましょう。また、修正の範囲についても明確にしておくことが重要です。
著作権の扱いが曖昧な契約の問題点
納品後の著作権が制作会社に残る契約の場合、自社でサイトを自由に修正できなくなる可能性があります。将来的にリニューアルする際にも、同じ会社に依頼しなければならないかもしれません。
契約時に、著作権の譲渡について明確に取り決めておきましょう。追加費用がかかっても、著作権は自社に譲渡してもらうことをおすすめします。
見積もりチェックリスト
見積もりを取る際に確認すべきポイントをチェックリスト形式でまとめました。このリストを活用して、後悔のない発注を行いましょう。
デザイン関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | デザイン費の内訳が明確になっているか |
| □ | トップページと下層ページの単価が分かれているか |
| □ | レスポンシブ対応は含まれているか |
修正対応関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | 修正回数は何回まで無料か |
| □ | 修正範囲はどの程度まで対応してもらえるか |
素材費関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | 写真撮影費用は別途か、見積もりに含まれているか |
| □ | イラスト制作費用は別途か、見積もりに含まれているか |
納期・スケジュール関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | 納期は現実的か(短納期すぎないか) |
| □ | 制作スケジュールは明確か |
支払い条件関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | 着手金はいくら必要か |
| □ | 完成後の支払い期限はいつまでか |
納品後のサポート関連項目
| □ | 確認項目 |
| □ | 不具合対応期間は設定されているか |
| □ | 操作方法のレクチャーは含まれているか |
その他重要確認事項
| □ | 確認項目 |
| □ | 著作権の帰属は明確か |
| □ | キャンセル規定は設定されているか |
補助金・助成金の活用方法
ホームページ制作費用の負担を軽減するため、各種補助金や助成金を活用する方法があります。2025年度に利用可能な制度を詳しく解説します。
IT導入補助金(最大450万円)の申請方法
IT導入補助金は、中小企業のデジタル化を支援する制度です。ホームページ制作も対象となり、最大450万円の補助を受けられます。補助率は2分の1から4分の3となっており、企業規模や導入内容によって変動します。
申請には、IT導入支援事業者として登録された制作会社を通じて行う必要があります。事業計画書の作成や、導入効果の数値目標設定なども求められるため、準備期間として2か月程度見込んでおくとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金(最大250万円)の活用
小規模事業者持続化補助金は、従業員20人以下の企業が対象となる制度です。ホームページ制作費用の3分の2、最大250万円まで補助を受けられます。
この補助金の特徴は、比較的申請が簡単なことです。商工会議所や商工会のサポートを受けながら申請書を作成できるため、初めての方でも挑戦しやすいでしょう。
各自治体の独自補助金情報
都道府県や市区町村でも、独自の補助金制度を設けている場合があります。例えば、東京都の「創業助成金」では最大300万円、大阪府の「ものづくり補助金」では最大100万円の支援を受けられます。
地域の商工会議所や産業振興センターで情報収集することをおすすめします。自治体の補助金は競争率が比較的低いため、採択される可能性も高くなるでしょう。
よくある質問(FAQ)

ホームページデザイン費用に関して、よく寄せられる質問にお答えします。
最低費用はいくらから可能か
Q: ホームページデザインの最低費用はいくらですか?
A: テンプレートを利用すれば5万円程度から制作可能です。ただし、企業サイトとして最低限の品質を確保するなら、30万円程度は必要だと考えておくべきでしょう。自作なら無料のツールもありますが、プロレベルの仕上がりは期待できません。
追加費用が発生しやすい項目
Q: 見積もり以外に追加費用が発生することはありますか?
A: 写真撮影、原稿作成、3回目以降の修正、追加ページの制作、急な仕様変更などで追加費用が発生することがあります。特に、当初予定になかった機能の追加は高額になりやすいため、要件定義の段階でしっかり検討しておくことが大切です。
相場より安い業者の注意点
Q: 相場の半額以下で請け負う業者は信頼できますか?
A: 極端に安い業者には注意が必要です。品質が低い、納期が守られない、追加費用を後から請求されるなどのトラブルが起きやすくなります。安さの理由を確認し、実績や評判をしっかりチェックしてから依頼することをおすすめします。
費用相場を理解して理想のホームページを実現しよう
ホームページのデザイン費用は、ページ数やデザインの凝り具合、必要な機能によって大きく変動します。費用を抑えたい場合は、テンプレートの活用や段階的な制作、素材の自社準備などの工夫が有効です。また、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金を活用すれば、実質的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
重要なのは自社の目的と予算のバランスを考えて、最適な選択をすること。安さだけを追求すると品質が犠牲になりますし、逆に高額な投資をしても効果が出なければ意味がありません。
見積もりを取る際は、本記事で紹介したチェックリストを活用して、内訳や契約内容をしっかり確認しましょう。複数の業者から見積もりを取って比較検討することも大切です。
最後に、ホームページは作って終わりではなく、運用や更新も重要だということを忘れないでください。初期費用だけでなく、運用コストも含めた総合的な判断が必要です。適正な価格で質の高いホームページを制作し、ビジネスの成長につなげていきましょう。
\ホームページできるくんなら月額1,900円〜!プロのデザイナーが高品質のホームページを提供!/