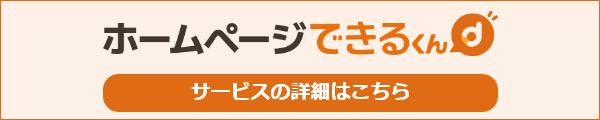お役立ち情報
ホームページ納品までの流れは?注意点・成果物の定義を解説

「ホームーページが納品されるまでの流れってどうなっているの?」「納品後に自分たちで更新できるようになるの?」「何を持って納品になるの?」ホームページ制作を初めて依頼する中小企業や個人事業主の方にとって、「納品」という言葉は少し不安を感じるものかもしれません。
Webサイトは形のない商品。パソコンやスマホで見るものだけど、実際に手元に残るものは何なのか、納品後にトラブルが起きないか心配される方も多いでしょう。
この記事では何を持ってホームページの納品となるのか、成果物の定義から納品までの流れ、注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。初めてホームページを作る方が、安心して納品を迎え、その後のスムーズな運用をスタートできるよう、必要な知識をお伝えします。
「スムーズにホームページを納品してほしい」「納品後の運用もお任せしたい」そんな方はホームページできるくんにご相談ください!
ホームページの「納品」とは?
ホームページ制作において「納品」とはどういう意味なのでしょうか。実際に手に取れる商品ではないホームページの納品について、その定義や目的を詳しく見ていきましょう。
Web業界における「納品」の意味
Web業界における「納品」とは、制作会社やフリーランスのデザイナー・エンジニアが制作したホームページを、依頼主に引き渡すことを意味します。具体的には、以下のいずれか(または両方)の形で行われます。
サーバーへのアップロード
完成したホームページのデータをインターネット上のサーバーにアップロードし、実際にWebサイトとして閲覧できる状態にすること
データの引き渡し
HTMLやCSS、画像などのファイル一式、またはWordPressなどのCMSのデータを、依頼主に引き渡すこと
つまり、「納品」とは単にホームページが完成したというだけでなく、そのホームページを構成するデータや情報が、正式に依頼主の手元やサーバーに移る瞬間なのです。
納品の目的と重要性
ホームページの納品には、以下のような重要な目的があります。
所有権の移転
制作されたホームページの所有権(場合によっては著作権も)が、制作者から依頼主に移ること
管理権限の移転
ホームページの管理・更新権限が依頼主側に移ること
契約の完了
制作依頼の契約が完了し、正式に取引が終了すること
運用フェーズへの移行
制作フェーズから運用・保守フェーズへと移行するタイミングとなること
これらの目的から分かるように、納品は単なる形式的な手続きではなく、ホームページの所有や管理に関わる重要なステップです。特に自社で更新・運用していきたいと考えている場合は、この納品のタイミングで必要な情報やデータをしっかり受け取ることが大切になります。
制作完了=納品ではない?よくある誤解
「ホームページができあがったら、それが納品ではないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、実は制作の完了と納品は厳密には異なります。よくある誤解として以下のようなものがあります。
誤解1: デザインが完成したら納品完了
デザインはあくまで見た目だけ。実際のプログラム(HTML/CSS)やサーバーへの設置まで含めて納品となります。
誤解2: 納品=公開
納品されても即公開されるとは限りません。公開日の設定や最終確認などを経て公開されるケースが一般的です。
誤解3: 納品後は全て自分たちで対応できる
納品時に必要なマニュアルやアカウント情報などを受け取らないと、自社での更新ができないケースがあります。
このような誤解を避けるためにも、納品とは具体的にどのような状態を指すのか、事前に制作会社と確認しておくことが重要です。
ホームページ納品までの基本的な流れ【初心者向け】

ホームページが納品されるまでには、いくつかの段階があります。初めてホームページを制作依頼する方向けに、基本的な流れを解説します。
①要件定義・打ち合わせ
ホームページ制作の最初のステップは、要件定義と打ち合わせです。この段階では、以下のようなことを決めていきます。
- ホームページの目的や目標
- ターゲットユーザーの設定
- 掲載内容やコンテンツの種類
- デザインの方向性
- 予算や納期
- 納品形式(サーバーアップロード型か、データ納品型か)
- 納品物の範囲(ソースコード、マニュアル、デザインデータなど)
特に重要なのは、この段階で納品形式と納品物の範囲を明確にしておくことです。後になって「こんなはずじゃなかった」というトラブルを防ぐためにも、契約書や発注書に明記しておくとよいでしょう。
②デザイン・コーディング
要件定義が完了すると、実際のデザイン制作とコーディング(HTMLやCSSなどのプログラミング)の工程に入ります。一般的な流れは以下の通りです。
- ワイヤーフレーム(骨組み)の作成
- デザインカンプ(完成イメージ)の制作
- デザイン確認・修正
- HTML/CSSコーディング
- WordPressなどのCMSへの実装(CMSを使用する場合)
- 各種機能の実装
デザイン段階では、「Figma」や「Adobe XD」などのツールで作成されたデザインデータを確認することになります。この段階でのチェックはとても重要です。納品後の大幅な変更は追加費用が発生することも多いため、デザイン段階でしっかり確認しましょう。
③テスト・検収(チェック項目の例も紹介)
デザインとコーディングが完了したら、テストと検収の段階に入ります。この段階では、以下のようなチェック項目を確認します。
基本的なチェック項目
- 各ページが正しく表示されるか
- リンクが正しく機能するか
- 問い合わせフォームが正常に動作するか
- スマートフォンやタブレットでの表示に問題がないか
- 主要なブラウザ(Chrome、Safari、Edgeなど)で正常に表示されるか
- 読み込み速度に問題はないか
- 文字の誤字脱字がないか
応用的なチェック項目
- SEO対策(タイトルタグ、meta description、alt属性など)が適切に設定されているか
- WordPressなどのCMSの管理画面が使いやすく設定されているか
- セキュリティ対策は十分か
- アクセス解析(Google Analyticsなど)の設定が完了しているか
検収時に見つかった問題点は、納品前に修正してもらうことが基本です。「後で直しておきます」という約束だけでは不十分なので、修正が完了したことをきちんと確認しましょう。
④納品(アップロードまたはデータ渡し)
テスト・検収が完了すると、いよいよ納品の段階です。納品の形態は大きく分けて2つあります。
1.サーバーアップロード型納品
制作会社がホームページのデータを、指定されたサーバーにアップロードして納品する方法です。この場合、ホームページはすぐに(または指定日に)公開可能な状態になります。
2.データ納品型
ホームページのデータ一式(HTML/CSS、画像、WordPressのデータなど)を、依頼主に直接渡す方法です。CDやUSBメモリでの納品、またはオンラインストレージサービスを利用する場合もあります。
どちらの納品形態でも、以下のものを受け取ることが一般的です。
- ホームページのデータ一式
- 各種アカウント情報(サーバー、ドメイン、WordPressなど)
- 更新マニュアル
- 納品書
特にアカウント情報は重要です。サーバーやドメインの管理者アカウント、WordPressの管理者アカウントなどが、確実に依頼主側に引き継がれているか確認しましょう。
⑤運用・保守に移行
納品が完了すると、ホームページは運用・保守フェーズに移行します。ここからは、以下のような内容が中心となります。
- コンテンツの更新
- セキュリティ対策
- バックアップの取得
- アクセス解析と改善
- 必要に応じたリニューアル
納品時に受け取った更新マニュアルを参考に、自社での更新を行うケースが多いでしょう。ただし、技術的な部分や大規模な変更については、継続的に制作会社に依頼するケースも少なくありません。
運用・保守については、納品時にどこまでが制作会社の対応範囲なのか、明確にしておくことが重要です。無償対応の範囲と有償対応の範囲を理解しておきましょう。
「スムーズにホームページを納品してほしい」「納品後の運用もお任せしたい」そんな方はホームページできるくんにご相談ください!
納品時に受け取るべきもの一覧

ホームページの納品時には、どのようなものを受け取るべきなのでしょうか。トラブルを防ぐために、しっかりチェックしておきたい納品物のリストを見ていきましょう。
納品形態の種類(サーバー納品 / データ納品 / CMS納品 など)
先ほども触れましたが、ホームページの納品形態には大きく分けて以下のようなタイプがあります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
1.サーバー納品
- サーバーに直接アップロードされた状態で納品
- メリット:すぐに公開できる、技術的な知識が少なくても対応可能
- デメリット:サーバーの管理権限がない場合、自由度が低くなる可能性がある
2.データ納品
- HTML/CSSなどのファイル一式が納品される
- メリット:自由に管理・編集が可能
- デメリット:自社でサーバーへのアップロードなどの技術的な対応が必要
3.CMS納品(WordPressなど)
- WordPressなどのCMSが導入された状態で納品される
- メリット:専門知識がなくても更新しやすい
- デメリット:CMSの仕様に縛られる部分がある
4.クラウドサービス型(Wix、Jimdoなど)
- クラウド型ホームページサービス上で制作・納品される
- メリット:メンテナンスが容易
- デメリット:カスタマイズの自由度が低い、サービス依存度が高い
納品形態によって受け取るべきものが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
受け取るべき具体的なファイル・情報
ホームページの納品時に受け取るべき具体的なファイルや情報は以下の通りです。制作会社によって提供内容に差があるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。
1.HTML/CSS/JSファイル
- ホームページを構成するすべてのHTMLファイル
- CSSファイル(スタイルシート)
- JavaScriptファイル
- 画像ファイル(jpg、png、svgなど)
- フォントファイル(使用している場合)
- その他、ホームページに使用されているすべてのファイル
2.CMSのログイン情報(WordPressなどを使用している場合)
- 管理画面のURL
- 管理者アカウントのユーザー名とパスワード
- データベースの接続情報(必要に応じて)
- プラグインのリストと設定情報
3.デザインデータ
- Figma、Adobe XD、Photoshopなどで作成されたオリジナルデザインデータ
- ロゴや特殊なグラフィックの元データ
- 使用しているフォント情報
4.各種アカウント情報
- サーバーの管理者アカウント情報
- ドメインの管理アカウント情報
- メールアカウント情報(ホームページに関連する場合)
- Google Analytics、Search Consoleなどの外部サービスのアカウント情報
5.ドキュメント類
- 納品書
- 更新マニュアル(一般的な更新方法の説明)
- サイトマップや構成図
- 仕様書(機能や設定の詳細)
特に中小企業や個人事業主の方が自社でホームページを更新・運用していく場合は、更新マニュアルが非常に重要です。基本的な更新方法から、トラブル時の対処法まで記載されているか確認しましょう。
受け取らないと困るもの・確認ポイント
納品時に特に重要な確認ポイントをいくつか紹介します。これらは後々のトラブルに直結する可能性が高いため、必ず確認しておきましょう。
1.権限関係の確認
- サーバーの管理者権限が移管されているか
- ドメインの所有者情報が正しく設定されているか
- WordPressなどのCMSの管理者アカウントが引き渡されているか
2.セキュリティ関連
- SSLは正しく設定されているか(https://で始まるURL)
- バックアップの方法が説明されているか
- セキュリティ対策のプラグインや設定が行われているか
3.更新関連
- コンテンツの更新方法が説明されているか
- 画像のアップロード方法が説明されているか
- メールフォームの設定変更方法が説明されているか
4.契約関連
- 納品後のサポート範囲が明確になっているか
- 保証期間や無償修正の範囲が明確になっているか
- 追加・修正の際の料金体系が説明されているか
特に重要なのは、サーバーやドメインの管理権限です。これらが制作会社側のままだと、将来的に制作会社を変更したい場合や自社で全て管理したい場合に問題が生じる可能性があります。必ず自社名義になっているか、または移管手続きが行われているか確認しましょう。
よくある納品トラブルと回避方法

ホームページの納品時にはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。ここでは、よくあるトラブルとその回避方法について解説します。
データが渡されていない・更新できない
よくあるトラブルの一つが、「必要なデータや情報が渡されていない」または「更新方法がわからない」というケースです。
具体的なトラブル例
- WordPressの管理者アカウント情報が渡されていない
- サーバーのFTP接続情報が不明で、ファイルをアップロードできない
- 更新マニュアルがなく、どうやって更新すればいいかわからない
- デザインデータ(PSDファイルなど)が納品されず、バナーなどの追加制作ができない
回避方法
- 契約前に納品物の詳細リストを作成してもらい、契約書に明記する
- 納品時に「納品物チェックリスト」を用意し、一つずつ確認する
- 納品後すぐに、実際に自分たちで更新できるか試してみる
- わからない点があれば、納品直後に質問し、必要に応じて追加の説明を求める
特にWordPressサイトの場合は、実際に管理画面にログインし、記事の投稿や画像のアップロードなど、基本的な操作ができるか確認することが重要です。
著作権・素材の権利関係のトラブル
ホームページに使用されている画像や素材の著作権に関するトラブルも少なくありません。
具体的なトラブル例
- 使用している画像の著作権が明確でない
- 制作会社が有料の素材を使用しているが、その使用権が依頼主に移転されていない
- フォントのライセンスが不明確で、商用利用できるか不安
- 制作会社がホームページの著作権を主張し、別の会社での修正ができない
回避方法
- 契約時に著作権の帰属について明確にする(基本的には依頼主に帰属するのが一般的)
- 使用している素材のライセンス情報を納品時に提出してもらう
- 可能な限り、権利関係がクリアな素材(自社で撮影した写真、ロイヤリティフリーの素材など)を使用する
- 特に重要なデザイン要素については、使用権や著作権の範囲を明確にしておく
ホームページの著作権は、特に明記がなければ制作者側に帰属するケースもあります。自社での自由な更新や、将来的な別会社への依頼を考えている場合は、著作権の帰属を明確にしておくことが重要です。
契約書や仕様書が曖昧だった場合のリスク
契約書や仕様書が曖昧だと、納品時に「これは含まれていない」というトラブルに発展する可能性があります。
具体的なトラブル例
- スマホ対応が含まれていると思っていたが、別料金だった
- SEO対策が含まれていると思っていたが、実施されていなかった
- 更新マニュアルの作成が含まれていなかった
- 納品後のサポート期間や範囲が不明確で、トラブル時に対応してもらえなかった
回避方法
- 契約書や仕様書に具体的な納品物と作業範囲を明記する
- 曖昧な表現(「SEO対策込み」など)は避け、具体的に何をするのか明記してもらう
- 見積書の項目が不明確な場合は、詳細を確認する
- 口頭での約束は必ず書面化する
特に初めてホームページを制作依頼する場合は、業界用語や専門用語がわかりにくいことも多いでしょう。不明な点は必ず質問し、明確にしておくことが重要です。
トラブルを防ぐには?制作前に確認すべき項目
ホームページの納品トラブルを防ぐためには、制作前の段階で以下の項目を確認しておくことが効果的です。
納品物の詳細リスト
・どのようなファイル・データが納品されるのか
・更新マニュアルは含まれるのか
・デザインデータは含まれるのか
著作権・使用権の帰属
・アカウント情報の取り扱い
・サーバー・ドメインのアカウントは誰の名義になるのか
・各種アカウント情報はどのように引き渡されるのか
・セキュリティ対策はどのように行われるのか
納品後のサポート
・無償対応の範囲と期間はどうなっているのか
・有償サポートの料金体系はどうなっているのか
・トラブル時の対応方法や連絡先は明確か
これらの項目を事前に確認し、契約書や仕様書に明記しておくことで、納品時のトラブルを大幅に減らすことができます。不明な点は遠慮せずに質問することが大切です。
納品後にやるべきこと

ホームページの納品が完了したら、次は公開・運用フェーズに入ります。納品直後にやっておきたいことを解説します。
納品後に確認しておくべきこと
納品直後には、以下の点を確認しておくことをおすすめします。
- 全ページの動作確認
- 各ページが正しく表示されるか
- すべてのリンクが正常に機能するか
- 問い合わせフォームが正しく動作するか
- スマートフォン・タブレットでの表示に問題がないか
- 主要ブラウザ(Chrome、Safari、Edge、Firefoxなど)での表示に問題がないか
- 各種アカウントの確認
- サーバーの管理画面にログインできるか
- ドメインの管理画面にログインできるか
- WordPressなどのCMSの管理画面にログインできるか
- アカウントの有効期限や更新方法は確認したか
- バックアップの確認
- バックアップの取得方法は理解できているか
- 定期バックアップは設定されているか
- 万が一の場合の復元方法は理解できているか
- 更新方法の確認
- テキストの更新方法はマスターしたか
- 画像の差し替え方法はマスターしたか
- 新しいページの追加方法は理解できているか
特に重要なのは、実際に自分たちで更新作業を試してみることです。納品直後であれば、わからない点があっても制作会社に質問しやすい状況です。基本的な更新作業を実践してみて、不明点があれば解消しておきましょう。
検索エンジンへの登録
ホームページが納品されても、自動的に検索エンジンに表示されるわけではありません。以下の作業を行い、検索エンジンへの登録を進めましょう。
- Google Search Consoleの設定
- Google Search Consoleのアカウントを作成(またはログイン)
- サイトの所有権を確認
- サイトマップの送信
- インデックス登録のリクエスト
- Google Analyticsの設定
- Google Analyticsのアカウントを作成(またはログイン)
- トラッキングコードがホームページに正しく設置されているか確認
- 目標設定や詳細な分析設定
- その他の検索エンジン対策
- titleタグ、meta descriptionの確認と必要に応じた修正
- 画像のalt属性が適切に設定されているか確認
- 構造化データ(スキーママークアップ)の確認
これらの設定は制作会社が行っているケースも多いですが、自社のアカウントで設定されているか確認することが重要です。また、これらの設定方法を理解しておくことで、今後のSEO対策や分析にも役立ちます。
保守・運用の依頼や自社での対応方針を決める
納品後には、ホームページの保守・運用体制を整えることも重要です。
- 社内での役割分担
- 誰がコンテンツ更新を担当するか
- 誰がお問い合わせ対応を担当するか
- 緊急時の対応フローはどうするか
- 継続的なサポート契約の検討
- 月額保守契約の内容と費用
- スポット対応の料金体系
- 緊急時のサポート体制
- 更新計画の策定
- どのくらいの頻度で更新するか
- どのようなコンテンツを追加していくか
- 大規模なリニューアルのタイミング
継続的な更新と保守がホームページの価値を維持・向上させるポイントです。納品時に受け取った資料やマニュアルを参考に、無理のない運用体制を構築しましょう。
ホームページ納品に関するよくある質問(FAQ)
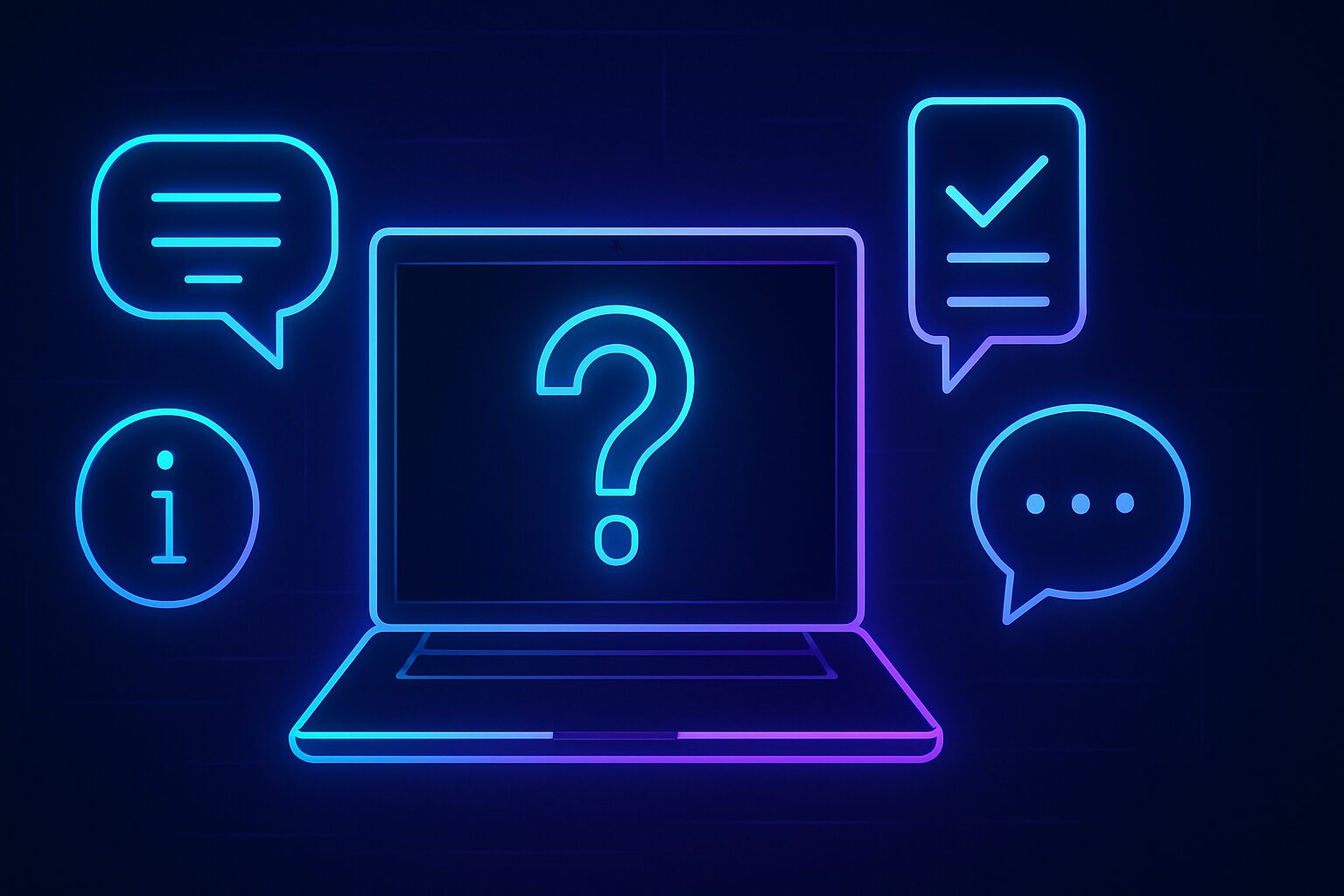
ホームページの納品に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q: 納品されたホームページのデータや著作権は自社のものになりますか?
A: 基本的には、制作費を支払って納品されたホームページは依頼主に帰属しますが、契約内容によって異なる場合があります。特に以下の点に注意が必要です。
- 著作権
契約書に明記がなければ、デザインや構成などの著作権は制作者側に残るケースもあります。 - 使用権
著作権が制作者側にあっても、依頼主には使用権が与えられます。 - 素材の権利
ホームページに使用されている写真やイラストなどの素材については、別途ライセンスが必要な場合があります。
権利関係でトラブルを避けるためには、契約時に著作権の帰属を明確にしておくことをおすすめします。
Q: 納品後に修正が必要になった場合、対応してもらえますか?
A: 納品後の修正対応は、以下のようなケースによって異なります。
- 瑕疵担保責任による修正
納品物に明らかな不具合や契約内容との相違がある場合は、無償で修正対応されるのが一般的です。通常は納品から1ヶ月〜3ヶ月程度の保証期間が設けられています。 - 仕様変更による修正
依頼主の要望による変更(デザインの変更、機能の追加など)は、通常有償対応となります。料金体系は制作会社によって異なります。 - 軽微な修正
テキストの誤字脱字修正など、軽微な修正については無償対応してくれるケースもありますが、これも契約内容によります。
納品後の修正対応については、事前に「保証期間」「無償対応の範囲」「有償対応の料金体系」を確認しておくことが重要です。また、自社で更新できる範囲と、制作会社に依頼すべき範囲を理解しておくことも大切です。
Q: WordPressで作ったサイトは、どのような形で納品されるのですか?
A: WordPressサイトの納品は、主に以下の2つの形式があります。
- サーバー設置型納品
- サーバーにWordPressがインストールされ、設定やカスタマイズが完了した状態で納品されます。
- 管理者アカウントの情報(ユーザー名・パスワード)が引き渡されます。
- データベースの情報やバックアップの方法なども提供されます。
- データ納品
- WordPressのデータベースダンプファイル(SQLファイル)
- WordPressのテーマファイルやプラグインファイル一式
- 設定方法やインストール手順のマニュアル
特に重要なのは、WordPressの管理者アカウント情報の引き渡しです。また、使用しているテーマやプラグインのライセンス情報も確認しておくべきでしょう。有料テーマや有料プラグインを使用している場合、ライセンスの扱いが問題になることがあります。
Q: ホームページのドメインやサーバーの所有権はどうなりますか?
A: ドメインやサーバーの所有権については、契約内容によって異なります。以下のパターンがあります。
- 依頼主が直接契約するケース
- 依頼主自身がドメインやサーバーを取得・契約し、所有権も依頼主にあります。
- 更新管理も依頼主が行います。
- この方式が最も安全で推奨されます。
- 制作会社が代行取得するケース
- 制作会社がドメインやサーバーを取得し、依頼主に使用権を与えるケース。
- 契約書で明確に所有権の移転や管理方法を定めておく必要があります。
- 将来的に制作会社との契約が終了した場合の取り扱いも確認しておくべきです。
- 制作会社の共有サーバーを使用するケース
- 制作会社が管理する共有サーバーにホームページを設置するケース。
- コストは抑えられますが、制作会社に依存度が高まります。
- 制作会社との契約終了時に、データの移行方法を確認しておくことが重要です。
ドメインやサーバーの契約は、可能な限り依頼主自身の名義で行うことをおすすめします。そうすることで、将来的に制作会社を変更する際にもスムーズに対応できます。
ホームページ納品を正しく理解し、安定運用を
中小企業や個人事業主の方にとって、ホームページは重要な資産です。納品時にしっかりと必要なものを受け取り、その後の運用方法を理解しておくことで、ホームページを効果的に活用し続けることができます。
そのためにも制作会社との良好なコミュニケーションを維持しながら、自社でも適切に管理・運用できる体制を整えていきましょう。納品をゴールではなく、ホームページ運用の新たなスタートと捉え、継続的な改善と更新を行っていくことが成功のポイントになります。
初めてのホームページ制作で不安な点があれば、この記事を参考に制作会社にしっかりと確認しながら進めてください。適切な納品を受けることで、その後の運用もスムーズになるはずです。
「スムーズにホームページを納品してほしい」「納品後の運用もお任せしたい」そんな方はホームページできるくんにご相談ください!