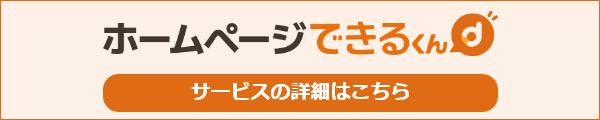お役立ち情報
ホームページ作成費用の相場は?料金内訳や安く抑えるコツを解説

「ホームページを作りたいけど、一体いくらかかるの?」「見積もりを取ったら予想以上に高額で驚いた」このような悩みを抱えていませんか。
ホームページ作成費用は依頼先や規模によって数万円から数百万円まで大きく幅があります。適正価格を知らないまま依頼すると、必要以上に高額な費用を支払ってしまうかもしれません。
本記事では、ホームページ作成にかかる費用相場を依頼先別・規模別に詳しく解説します。
制作費をできる限り抑えたい方は「ホームページできるくん」にご相談ください。
プロのクリエイターが作成したホームページを「制作費0円」「月額1,900円~」持つことができます。
ホームページ作成費用の全体像を掴む【早見表付き】
ホームページ作成費用は依頼先によって大きく異なります。
制作会社に依頼する場合は30万円から300万円以上、フリーランスなら10万円から100万円程度が相場となっています。自分で作成する場合は月額数千円から始められますが、デザインや機能に制限があることを理解しておく必要があります。
依頼先別の費用相場
ホームページ作成の依頼先によって、費用は大きく変動します。以下の表で、それぞれの特徴と費用相場を比較してみましょう。
| 依頼先 | 費用相場 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 大手制作会社 | 100万円以上 | 高品質・充実したサポート体制 | 費用が高額 |
| 中小制作会社 | 30万円~100万円 | 品質とコストのバランスが良い | 会社により品質に差がある |
| フリーランス | 10万円~50万円 | 制作会社より安価 | 個人のスキルにばらつきあり・実績確認が重要 |
| 自作(CMS利用) | 月額1,000円程度~ (サーバー代・ドメイン代) | 圧倒的に低コスト | 専門知識が必要・学習コストがかかる |
この表を参考に、予算と求める品質のバランスを考えながら、最適な依頼先を選択することが重要です。初期費用だけでなく、運用面でのサポートや将来的な拡張性も含めて検討しましょう。
目的・規模別の費用相場
ホームページの種類や目的によって、必要な機能や規模が異なるため費用も大きく変わります。以下の表で、主要なサイトタイプごとの費用相場をご確認ください。
| サイトの種類 | 費用相場 | ページ数・規模 | 必要な主な機能 |
|---|---|---|---|
| コーポレートサイト | 50万円~150万円 | 10ページ程度 | 会社概要・サービス紹介・お問い合わせフォーム |
| ECサイト | 100万円~500万円 | 商品数により変動 | 商品管理システム・決済機能・会員機能 |
| ランディングページ | 10万円~30万円 | 1ページ | お問い合わせフォーム・コンバージョン最適化 |
| 採用サイト | 80万円~200万円 | 5~15ページ程度 | エントリーフォーム・社員インタビュー・募集要項管理 |
| 会員制サイト | 150万円~400万円 | 機能により変動 | 会員管理機能・ログイン機能・会員限定コンテンツ |
| 予約システム付きサイト | 100万円~300万円 | 10ページ程度+システム | 予約管理・カレンダー機能・自動通知機能 |
特殊な機能を追加する場合は、上記の基本費用に加えて50万円から200万円程度の追加開発費用が必要になることもあります。
必要な機能を事前に整理し、優先順位をつけることで、予算内で最適なサイトを構築できるでしょう。
「ホームページにそこまで予算をかけられない」というお悩み、ホームページできるくんで解決できるかもしれません。Web業界10年、制作支援実績5,000件以上の知見を活かし、低コストで制作から運用まで行うホームページ支援を行っています。
ホームページ作成費用の内訳
ホームページ作成費用は大きく初期費用と運用費用に分けられます。初期費用には企画からデザイン、開発まで含まれ、運用費用は公開後に継続的にかかる費用を指します。それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。
初期費用の内訳
企画・ディレクション費
プロジェクト全体の進行管理や要件定義にかかる費用で、総額の10%から20%程度を占めます。サイトの目的やターゲット設定、競合調査などを行い、制作の方向性を決定していきます。この工程をしっかり行うことで、後の手戻りを防ぐことができるでしょう。
デザイン費
デザイン費用はページの種類やデザインの方法によって大きく異なります。以下の表で、具体的な費用相場を確認してみましょう。
| 項目 | 費用相場 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| トップページデザイン | 5万円~30万円 | サイトの顔となる最も重要なページ |
| 下層ページデザイン | 1万円~5万円/ページ | トップページのデザインを踏襲した統一感のあるデザイン |
| オリジナルデザイン | 上記費用の1.5~2倍程度 | 完全オーダーメイドで独自性の高いデザイン |
| テンプレート活用 | 上記費用の30~50%程度 | 既存テンプレートをカスタマイズして使用 |
| レスポンシブデザイン | 追加費用なし(標準対応) | スマートフォン・タブレット対応は現在必須機能 |
オリジナルデザインは費用が高くなりますが、ブランディング効果が期待できます。一方、テンプレートを活用すれば大幅にコストを削減できるため、予算と目的に応じて選択することが重要です。
現在ではスマートフォン対応のレスポンシブデザインは標準仕様となっており、追加費用なしで含まれることがほとんどです。
コーディング費
デザインをWeb上で実際に動作するページとして構築するコーディング作業には、以下のような費用がかかります。
| 項目 | 費用相場 | 作業内容・特徴 |
|---|---|---|
| 基本コーディング | 1万円~3万円/ページ | HTML・CSSによる基本的なページ構築 |
| JavaScript実装 | 5,000円~3万円/機能 | スライダー・アニメーション・動的な表示切替など |
| 構造化マークアップ | 1万円~5万円/サイト全体 | SEO対策のための適切なHTML構造の実装 |
| フォーム実装 | 1万円~3万円/フォーム | 入力チェック・確認画面・送信機能の実装 |
| CMS組み込み | 3万円~10万円/サイト全体 | WordPressなどのCMSへの組み込み作業 |
| ブラウザ対応調整 | 1万円~3万円/サイト全体 | 各種ブラウザでの表示確認と調整作業 |
基本的なコーディングは1ページあたり1万円から3万円が相場ですが、JavaScriptを使った動きのある演出や複雑な機能を追加する場合は、追加費用が発生します。
SEO対策のための構造化マークアップも重要な要素であり、検索エンジンでの表示順位に影響するため、この工程での適切な実装が欠かせません。
システム開発費
ホームページに実装する機能によって、システム開発費は大きく変動します。以下の表で、主要な機能の費用相場と特徴をまとめました。
| 機能・システム | 費用相場 | 既存サービス利用 | オリジナル開発 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | 3万円~10万円 | 3万円~5万円 | 8万円~10万円 |
| 予約システム | 20万円~100万円 | 20万円~40万円 | 60万円~100万円 |
| 会員ログイン機能 | 15万円~50万円 | 15万円~25万円 | 35万円~50万円 |
| 決済システム | 30万円~80万円 | 30万円~40万円 | 60万円~80万円 |
| 検索機能 | 10万円~30万円 | 10万円~15万円 | 20万円~30万円 |
| 多言語対応 | 20万円~60万円 | 20万円~30万円 | 40万円~60万円 |
既存のサービスやプラグインを活用すれば費用を抑えられますが、カスタマイズの自由度は制限されます。
一方、オリジナル開発は費用が高額になりますが、自社の業務フローに完全に合わせた仕様にできます。必要な機能を精査し、優先順位をつけて段階的に実装することで、予算内で効果的なシステム構築が可能になるでしょう。
コンテンツ制作費
ホームページに掲載する写真や文章、動画などのコンテンツ制作には以下のような費用がかかります。
| コンテンツ種別 | 費用相場 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 写真撮影(プロカメラマン) | 5万円~20万円 | 1日あたり | 撮影場所・カット数により変動 |
| 商品撮影 | 1,000円~5,000円 | 1点あたり | スタジオ撮影・画像加工込み |
| ライティング(原稿作成) | 1万円~5万円 | 1ページあたり | 取材・リサーチ込みの場合は高額 |
| キャッチコピー作成 | 3万円~10万円 | 一式 | ブランディングに関わる重要要素 |
| 動画制作(30秒) | 10万円~50万円 | 30秒あたり | 企画・撮影・編集込み |
| イラスト制作 | 1万円~5万円 | 1点あたり | オリジナルイラストの場合 |
| 素材購入(ストックフォト) | 1,000円~1万円 | 1点あたり | 既存素材を購入する場合 |
プロに依頼すると品質は保証されますが、費用が高額になります。写真や文章などの素材を自社で用意できれば、この部分の費用を大幅に削減できるでしょう。
ただし、企業イメージに関わる重要な部分は、プロに依頼することで投資対効果が高まることもあります。
月額・運用費用(ランニングコスト)
ホームページは作成後も継続的に費用がかかります。以下の表で、主な運用費用の内訳と相場を確認しましょう。
| 項目 | 費用相場 | 支払い頻度 | 詳細・備考 |
|---|---|---|---|
| サーバー代 | 1,000円~1万円 | 月額 | アクセス数や必要な容量により変動 |
| ドメイン代 | 1,000円~5,000円 | 年額 | .com/.jpなどドメインの種類により異なる |
| SSL証明書 | 0円~5万円 | 年額 | 無料版から企業認証型まで様々 |
| 保守・メンテナンス | 5,000円~5万円 | 月額 | 対応範囲(障害対応・バックアップ等)により変動 |
| 更新作業代行 | 1万円~10万円 | 月額 | 更新頻度・作業量により変動 |
| セキュリティ対策 | 3,000円~2万円 | 月額 | WAF導入・脆弱性診断など |
| アクセス解析・改善提案 | 1万円~5万円 | 月額 | レポート作成・改善施策の提案 |
更新頻度が高い場合は、CMSを導入して自社で更新できる体制を整えることで、運用コストを削減できます。
ただし、セキュリティ対策やバックアップなどの技術的な部分は、専門業者に任せることで安全性を確保できるでしょう。初期費用だけでなく、これらの運用費用も含めた総額で予算計画を立てることが重要です。
ホームページできるくんは、低コストでプロのクリエイターが作成したホームページが持てるほか、公開後の運用もサポートしています。ホームページ活用の要となる運用部分も相談したい方はぜひご検討ください。
依頼先ごとの費用相場とメリット・デメリット比較
ホームページ作成の依頼先は大きく3つに分けられます。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 依頼先 | 費用相場 | 納期 | メリット | デメリット | 適している企業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制作会社 | 30万円~300万円以上 | 2~6か月 | ・高品質な成果物 ・手厚いサポート体制 ・チーム対応で総合的にカバー ・デザイン/機能/SEO対策まで対応 | ・費用が高額 ・小回りが利きにくい ・納期が長い | ・大規模プロジェクト ・長期的な運用サポートが必要 ・予算に余裕がある企業 |
| フリーランス | 10万円~100万円 | 1~3か月 | ・制作会社より安価 ・直接やり取りが可能 ・コミュニケーションが密 ・柔軟な対応 ・細かな要望に対応しやすい | ・スキルや経験にばらつき ・納期遅延のリスク ・病気/事故時の対応が困難 ・バックアップ体制が弱い | ・予算を抑えたい ・小~中規模サイト ・柔軟な対応を求める企業 |
| 自作(CMS) | 月額数千円程度 | 即日~1か月 | ・圧倒的な低コスト ・自由に更新可能 ・すぐに修正/追加できる ・PDCAサイクルを早く回せる | ・専門知識が必要 ・デザインが画一的 ・トラブル時は自力解決 ・学習コストがかかる | ・時間的余裕がある ・Web制作に興味がある ・極力費用を抑えたい個人/小規模事業者 |
それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った選択をすることが成功への第一歩となるでしょう。予算だけでなく、求める品質や納期、社内リソースなども考慮して、最適な依頼先を選択することが重要です。
ホームページ作成費用を安く抑える5つのコツ
限られた予算で最大限の効果を得るためには、工夫が必要です。ここでは実践的な費用削減のコツを5つご紹介していきます。
1. 小規模からスタートし、段階的に機能を追加する
最初から完璧を求めず、必要最小限の機能でスタートすることをおすすめします。まずは5ページ程度の基本構成で公開し、アクセス解析を見ながら必要なページや機能を追加していくのです。この方法なら初期投資を抑えつつ、ユーザーのニーズに合わせた改善ができます。
2. 写真や文章などの素材は可能な限り自分で用意する
プロのカメラマンやライターに依頼すると高額になりますが、自社で用意すれば大幅にコストダウンできます。スマートフォンでも十分きれいな写真が撮れますし、文章も社内の詳しい人が書けば説得力のある内容になるでしょう。ただし、クオリティが著しく低い場合は逆効果になるため注意が必要です。
3. 汎用的なテンプレートや既存の機能を使う
オリジナルデザインやカスタム機能は魅力的ですが、費用が高くなります。既存のテンプレートやプラグインを活用すれば、見た目も機能も十分なサイトが作れます。特に中小企業の場合は、独自性よりも情報の分かりやすさや使いやすさを重視すべきでしょう。
4. 複数社から相見積もりを取り、料金を比較する
最低でも3社以上から見積もりを取ることをおすすめします。同じ要件でも会社によって金額が2倍以上違うこともあります。ただし安さだけで選ぶのではなく、実績や対応の良さも含めて総合的に判断することが大切です。
5. 国や自治体の補助金・助成金を活用する
IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、ホームページ作成に使える補助金があります。最大で費用の3分の2程度が補助される場合もあるため、積極的に活用しましょう。申請には手間がかかりますが、大幅な費用削減につながります。
予算別:代表的な制作会社をご紹介
予算に応じて選ぶべき制作会社は変わってきます。ここでは予算別に、どのような会社が適しているかをご紹介します。
1. 30万円以下での制作を得意とする制作会社
この価格帯では、テンプレートを活用した効率的な制作を行う会社が中心となります。個人事業主や小規模企業向けのシンプルなサイト制作が得意で、納期も1か月程度と短めです。ただし、カスタマイズの幅は限られることを理解しておく必要があります。
私たちが提供する「ホームページできるくん」も低価格帯のホームページ制作に該当します。ただ、テンプレートは使わず、プロが1社1社オリジナルのデザインで制作しています。コストを抑えながらもオリジナルサイトを持ちたい方はお気軽にご相談ください。
2. 31万~50万円以下での制作を得意とする制作会社
中小企業向けの標準的なコーポレートサイトが作れる価格帯です。ある程度のカスタマイズも可能で、SEO対策の基本的な施策も含まれることが多いでしょう。地域密着型の制作会社が多く、アフターフォローも期待できます。
3. 51万~100万円以下での制作を得意とする制作会社
オリジナルデザインや独自機能の実装が可能な価格帯となります。ブランディングを意識したデザインや、マーケティング視点での設計も期待できるでしょう。中堅企業のリニューアル案件などに適しています。
4. 100万円以上での制作を得意とする制作会社
大手制作会社や専門性の高い会社が対応する価格帯です。戦略立案から運用支援まで、包括的なサービスを提供してくれます。大規模サイトやECサイト、複雑なシステム開発を伴うプロジェクトに適しているでしょう。
費用対効果の高いホームページを作るには?
安さだけを追求すると、結果的に損をすることがあります。費用対効果を最大化するための考え方をお伝えします。
1. 安さだけで選ぶと失敗する?よくあるトラブル例
極端に安い業者を選んだ結果、納期遅延や品質不良、追加費用の請求などのトラブルに巻き込まれるケースがあります。また、SEO対策が不十分で検索に表示されない、スマートフォン対応していないなどの問題も起こりがちです。契約前に実績や評判をしっかり確認することが重要となります。
2. 「費用=投資」として考えるべき
ホームページは単なる費用ではなく、ビジネスを成長させるための投資です。月間1,000人の訪問者から1%が問い合わせをすれば、月10件の新規顧客獲得につながります。この視点で考えると、100万円の投資も数か月で回収できる可能性があるのです。
3. 成果が出るホームページの特徴
成果の出るホームページには共通点があります。ユーザー目線で設計されていること、定期的に更新されていること、スマートフォン対応していることなどです。また、問い合わせまでの導線が明確で、信頼性を高める要素が適切に配置されています。これらの要素を満たすためには、ある程度の投資が必要になるでしょう。
【チェックリスト】見積もり前に確認すべきポイント
見積もりを依頼する前に、以下のチェックリストで準備状況を確認しましょう。
| 確認項目 | チェックポイント | 準備すべき内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 目的の明確化 | □ なぜホームページを作るのか □ 達成したい目標は何か | ・集客強化 ・ブランディング ・売上向上 ・採用強化など | 目的が曖昧だと制作会社も適切な提案ができない |
| ターゲット設定 | □ 誰に見てもらいたいか □ ペルソナは明確か | ・年齢層、性別 ・職業、収入 ・興味関心 ・利用シーン | ターゲットによってデザインや機能が変わる |
| 掲載内容の整理 | □ 何を伝えたいか □ 必要なページ構成 □ 競合サイトの分析 | ・サービス内容 ・会社情報 ・強み、差別化ポイント ・必要な機能リスト | 自社の強みを整理しておくことが重要 |
| 予算の設定 | □ 初期費用の上限 □ 月額運用費の上限 □ 投資回収期間の目安 | ・初期費用:○○万円まで ・運用費:月○万円まで ・○か月で回収目標 | 相場を大きく下回る予算では実現困難 総額で検討することが大切 |
| 社内リソース確認 | □ 社内でできること □ 外注すべきこと □ 担当者の決定 | ・写真撮影 ・原稿作成 ・更新作業 ・プロジェクト管理 | すべて外注すると費用が膨らむ 専門性の高い部分は無理せず外注 |
| スケジュール | □ 公開希望時期 □ 重要な締切 □ 段階的公開の可否 | ・○月○日公開希望 ・イベントに合わせる ・優先順位の設定 | 余裕を持ったスケジュール設定が必要 |
| 相見積もりの準備 | □ 同じ条件で依頼 □ 3社以上から取得 □ 評価基準の設定 | ・RFP(提案依頼書)作成 ・比較表の準備 ・評価項目の設定 | 金額だけでなく対応の速さや提案内容も評価 要件が曖昧だと比較できない |
よくある質問(Q&A)
ホームページ作成に関して、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でお答えします。
Q. 相場より格安の制作会社は危険?
必ずしも危険とは限りませんが、注意は必要です。テンプレートの使い回しや、海外への外注で価格を抑えている場合があります。品質やサポート体制を事前に確認し、実績を見せてもらうことが重要です。あまりにも安い場合は、何か理由があると考えた方がよいでしょう。
Q. ホームページ作成費用は経費になる?
基本的に経費として計上可能です。ただし、金額によって処理方法が異なります。10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら広告宣伝費や無形固定資産として処理することが一般的です。詳細は税理士に相談することをおすすめします。
Q. ホームページ作成に使える補助金や助成金はある?
IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、各自治体の独自補助金などがあります。補助率は費用の2分の1から3分の2程度が一般的です。申請時期が限られているため、事前に情報収集しておくことが大切です。制作会社によっては申請サポートをしてくれる場合もあります。
最適なホームページ作成パートナーを見つけるために
ホームページ作成費用は依頼先や規模によって大きく異なりますが、目的と予算のバランスを考えることが最も重要です。制作会社なら30万円から300万円、フリーランスなら10万円から100万円、自作なら月額数千円程度が相場となっています。
費用を抑えるためには、段階的な機能追加、素材の自社準備、テンプレートの活用、相見積もりの取得、補助金の活用という5つのコツを実践しましょう。ただし、安さだけを追求するのではなく、投資対効果を考慮することが大切です。
最後になりますが、「ホームページを制作したいけど、相場がわからなくて依頼しづらい」と不安に感じている方はぜひホームページできるくんにご相談ください。月額1,900円〜プロのクリエイターが高品質のホームページをオリジナルで提供します。