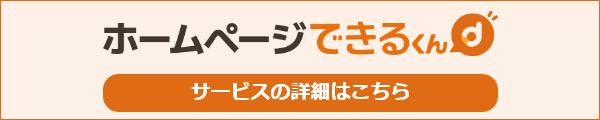お役立ち情報
サイトを簡単に作る方法は?初心者でも最短1日で公開できるステップを解説
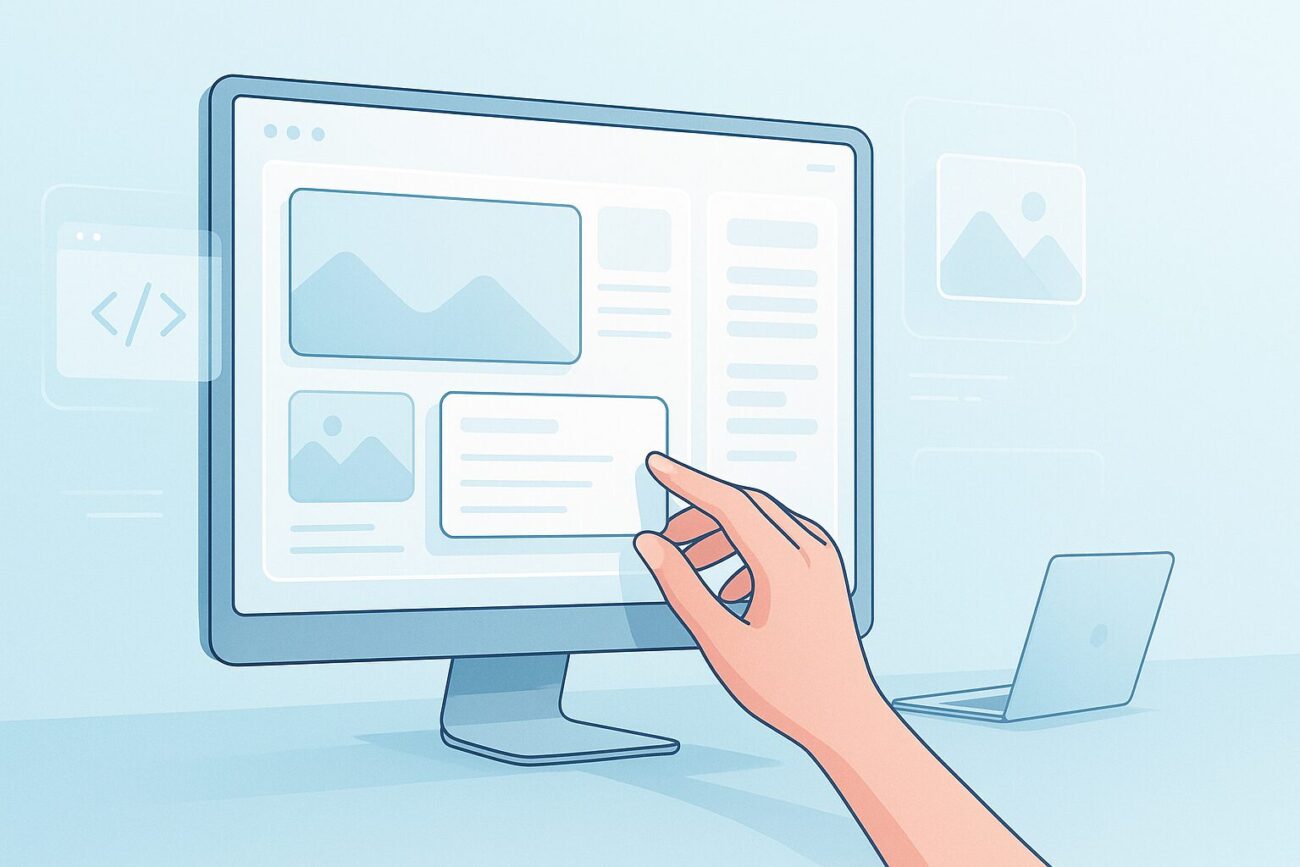
「自分でWebサイトを作りたいけど、コーディングなんてできないし難しそう」と思っていませんか。
実は今、専門知識がなくても誰でも簡単にサイトを作れる時代になりました。この記事では初心者の方でも迷わずサイトを立ち上げられるよう、具体的な方法と手順を分かりやすく解説します。
最短1日で自分のサイトを公開できる方法から、目的に合わせた最適なツールの選び方まで、必要な情報をすべてお伝えしていきます。読み終わる頃には「自分でもできそう」という確信を持っていただけるはずです。
\月額1,900円〜プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/
サイトを簡単に作れる時代になった3つの理由
かつてWebサイト制作といえば、HTMLやCSSといったコーディングの知識が必須でした。しかし技術の進化により、今では誰でもサイトを作れるほど簡単になっています。なぜこれほどまでに手軽になったのか、その背景には大きく3つの理由があります。
プログラミング不要のノーコードツールの進化
ノーコードツールとは、プログラミングコードを書かずにサイトを作れるサービスのことです。マウスでドラッグ&ドロップするだけで、文章や画像を好きな場所に配置できます。まるでパワーポイントで資料を作るような感覚で、本格的なWebサイトをつくれるのです。
代表的なサービスとしてWixやペライチがあり、これらは日本語にも完全対応しています。操作画面も直感的で分かりやすく設計されているため、パソコンが苦手な方でも30分もあれば基本操作をマスターできるでしょう。
AI技術による自動デザイン機能の充実
2024年以降、AI技術の進歩により、デザインの自動生成機能が飛躍的に向上しました。業種や目的を選ぶだけで、AIが最適なレイアウトや配色を提案してくれます。プロのデザイナーが作ったような洗練されたサイトが、わずか数クリックで完成するのです。
たとえば「美容室のサイトを作りたい」と入力すれば、清潔感のある白を基調としたデザインや、予約ボタンの配置まで自動で設定されます。もちろん後から自分好みにカスタマイズすることも可能です。
テンプレートの質と種類の向上
各サービスが提供するテンプレート(ひな形)の品質も格段に向上しています。以前は「いかにもテンプレート」という画一的なデザインばかりでしたが、現在は業種別・目的別に細分化された高品質なテンプレートが数千種類も用意されています。
飲食店向け、クリニック向け、個人事業主向けなど、それぞれの業界に特化したデザインが揃っているため、自分のビジネスにぴったりのものが見つかるはず。写真と文章を差し替えるだけで、オリジナリティのあるサイトをつくれます。
初心者がサイトを作る前に知っておくべきこと
サイト作成を始める前に、最低限知っておきたい基礎知識があります。一つずつ分かりやすく説明していきます。
ホームページとWebサイトの違い
「ホームページ」と「Webサイト」は同じ意味で使われることが多いですが、厳密には少し違います。ホームページは本来、サイトの最初のページ(トップページ)を指す言葉でした。一方Webサイトは、複数のページで構成される全体を指します。
ただし日本では「ホームページ=Webサイト」として定着しているため、どちらを使っても問題ありません。この記事でも同じ意味として扱っていきます。
ドメインとサーバーの仕組み
ドメインとは、インターネット上の住所のようなものです。「example.com」のような文字列で、世界に一つだけの固有のアドレスになります。覚えやすく、ビジネスに関連した名前を選ぶことが大切です。
サーバーは、サイトのデータを保管しておく場所です。24時間365日稼働していて、誰かがあなたのサイトにアクセスした時に情報を表示してくれます。レンタルサーバーを借りるか、サイト作成サービスに含まれているものを使うのが一般的です。
SSL証明書とセキュリティの重要性
SSL証明書は、サイトの通信を暗号化してセキュリティを高める仕組みです。SSL対応のサイトはURLが「https://」で始まり、ブラウザに鍵マークが表示されます。お客様の個人情報を守るために必須の機能といえるでしょう。
最近のサイト作成サービスでは、SSL証明書が無料で提供されることがほとんどです。特別な設定も不要で自動的に適用されるため、初心者でも安心して利用できます。
レスポンシブデザインの必要性
レスポンシブデザインとは、パソコン・スマートフォン・タブレットなど、どの端末で見ても最適な表示になる仕組みのことです。現在、Webサイトへのアクセスの約6割がスマートフォンからといわれています。
スマホ対応していないサイトは、文字が小さすぎて読めなかったり、ボタンが押しづらかったりして、訪問者がすぐに離れてしまいます。最新のサイト作成サービスなら自動でレスポンシブ対応されることが多いので、この点でも安心です。
サイトを簡単に作る5つの方法を徹底比較
サイトを作る方法は大きく分けて5つあります。それぞれに特徴があり、目的や予算、スキルレベルによって最適な選択肢が変わってきます。ここでは各方法のメリット・デメリットを詳しく比較していきましょう。
1.ホームページ作成サービス(Wix、ペライチ、Jimdo)
最も簡単で初心者向けなのが、ホームページ作成サービスです。ブラウザ上で操作するだけで、プロ並みのサイトが作れます。
メリット・デメリット
メリットは何といっても操作の簡単さです。ドラッグ&ドロップで直感的に編集でき、リアルタイムで仕上がりを確認できます。サーバーやドメインの設定も不要で、すべてがパッケージになっています。
デメリットは、カスタマイズの自由度に限界があることです。また、無料プランでは広告が表示されたり、独自ドメインが使えなかったりする制限があります。
料金プラン比較
Wixは月額1300円から、ペライチは月額1,465円から、Jimdoは月額990円からの有料プランがあります。無料プランもありますが、ビジネス利用なら有料プランがおすすめです。年間契約にすると割引が適用されることも多いため、長期利用を考えている方は検討してみましょう。
おすすめの使用シーン
個人事業主の名刺代わりのサイト、小規模な店舗の紹介サイト、イベントの告知ページなどに最適です。更新頻度が低く、5〜10ページ程度のシンプルなサイトを作りたい方におすすめします。
2.CMS(WordPress、はてなブログPro)
CMS(コンテンツ管理システム)は、より本格的なサイト運営に適したツールです。世界中のWebサイトの約40%がWordPressで作られているといわれています。
初期設定の手順
WordPressの場合、まずレンタルサーバーを契約し、ドメインを取得します。その後、サーバーにWordPressをインストールして初期設定を行います。最近は「簡単インストール機能」があるサーバーが多く、数クリックで導入できるようになりました。
必要なスキルレベル
基本的な操作はそれほど難しくありませんが、ホームページ作成サービスと比べると学習時間が必要です。プラグイン(拡張機能)の選定や、テーマのカスタマイズには多少の知識が求められます。ただし、情報が豊富にあるため、検索すれば大抵の問題は解決できるでしょう。
カスタマイズの自由度
CMSの最大の魅力は、カスタマイズの自由度の高さです。数万種類のテーマやプラグインから選べるため、どんな機能でも実現可能です。ブログ機能、会員制サイト、多言語対応など、成長に合わせて機能を追加していけます。
3.ECサイト構築サービス(BASE、STORES)
ネットショップを開きたい方には、EC専門のサービスがおすすめです。商品管理から決済まで、必要な機能がすべて揃っています。
ネットショップ特化の機能
在庫管理、顧客管理、売上分析など、ネットショップ運営に必要な機能が標準装備されています。商品写真のアップロードも簡単で、Instagram連携で自動投稿することも可能です。配送業者との連携機能もあり、送り状の作成まで一元管理できます。
決済システムの導入方法
クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込など、主要な決済方法に対応しています。面倒な審査や契約は不要で、サービス登録と同時に利用開始できます。手数料は売上の3〜5%程度が一般的で、初期費用や月額費用が無料のプランもあります。
4.AIサイト作成ツール(10Web、Durable)
最新のAI技術を活用したサイト作成ツールも登場しています。質問に答えるだけで、AIが最適なサイトを自動生成してくれます。
AI活用のメリット
最大のメリットは、圧倒的な作成スピードです。業種や目的、好みの色などを入力すると、わずか数分で完成度の高いサイトが出来上がります。文章もAIが自動生成してくれるため、「何を書けばいいか分からない」という悩みも解決します。
生成されるサイトの品質
AIが作るサイトの品質は日々向上していますが、完璧ではありません。生成された文章は必ず人の目でチェックし、自社の情報に書き換える必要があります。デザインも画一的になりがちなので、独自性を出したい場合は追加の編集が必要でしょう。
5.ノーコード開発プラットフォーム(Bubble、Webflow)
より高度な機能を実装したい方向けの選択肢です。プログラミングは不要ですが、ロジックを理解する必要があります。
高度な機能実装の可能性
会員登録機能、データベース連携、外部API連携など、通常はプログラマーに依頼するような機能も実装できます。独自のWebアプリケーションを作ることも可能で、ビジネスの差別化につながります。
学習コストと時間
他の方法と比べて学習曲線が急です。基本操作を覚えるだけでも数週間、実用的なサイトを作れるようになるまでには数ヶ月かかることもあります。ただし、一度マスターすれば、どんなアイデアも形にできる強力なツールとなるでしょう。
目的別|最適なサイト作成方法の選び方
ここまで5つの方法を紹介してきましたが、「結局どれを選べばいいの?」と迷っている方も多いはずです。そこで、目的別に最適な選択肢をご提案します。
コーポレートサイト・企業ホームページの場合
企業の信頼性を高めるサイトには、WordPressがおすすめです。デザインの自由度が高く、SEO対策もしやすいため、長期的な運用に適しています。ただし、すぐに公開したい場合は、WixやJimdoでまず作成し、後からWordPressに移行する方法もあります。
個人ブログ・ポートフォリオサイトの場合
個人の発信なら、はてなブログProやnoteがおすすめです。記事の執筆に集中でき、読者とのコミュニケーション機能も充実しています。デザイナーやフォトグラファーのポートフォリオなら、ビジュアル重視のWixやSquarespaceが適しているでしょう。
ネットショップ・ECサイトの場合
商品販売が目的なら、BASEかSTORESがおすすめです。初期費用無料で始められ、売上が発生してから手数料を払うシステムなので、リスクがありません。商品数が多い場合や、独自の販売方法を実現したい場合は、ShopifyやEC-CUBEも検討してみてください。
ランディングページ(LP)の場合
1ページ完結の訴求力の高いページなら、ペライチが最適です。LP専用のテンプレートが豊富で、A/Bテスト機能もあります。広告運用との相性も良く、コンバージョン率の改善に役立つでしょう。
\月額1,900円〜プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/
簡単な方法でサイトを作る手順
ここからは、実際にサイトを作る具体的な手順を解説します。今回は最も簡単なホームページ作成サービスを使った方法を例に、ステップバイステップで進めていきましょう。
Step1:目的とターゲットを明確にする
まず「何のためにサイトを作るのか」を明確にします。集客なのか、信頼性向上なのか、商品販売なのか。次に「誰に見てもらいたいか」を具体的にイメージしましょう。20代女性なのか、50代男性なのかで、デザインや文章の方向性が変わってきます。
Step2:サービスを選んで無料登録する
目的が決まったら、適したサービスに登録します。ほとんどのサービスが無料で始められるので、まずは試してみることが大切です。メールアドレスとパスワードを設定するだけで、すぐに作成を開始できます。
Step3:テンプレートを選択する
業種や目的に合ったテンプレートを選びます。「美容室」「レストラン」「コンサルタント」など、カテゴリー別に整理されているので、近いものを選びましょう。色やレイアウトは後から変更できるので、完璧を求めすぎず、まずは進めることが重要です。
Step4:必要なページを作成する
基本的なサイト構成として、最低限必要なページを作っていきます。
トップページの構成要素
トップページには、キャッチコピー、事業内容の簡単な説明、特徴やメリット、お客様の声などを配置します。訪問者が最初に見るページなので、3秒で何のサイトか分かるようにすることが大切です。写真は高品質なものを使い、第一印象を良くしましょう。
会社概要・プロフィールページ
信頼性を高めるために、運営者情報は必須です。会社名(屋号)、代表者名、所在地、連絡先などを記載します。個人事業主の場合は、経歴や資格、想いなども書くと親近感が湧きます。
お問い合わせフォームの設置
お客様からの連絡を受けるフォームを設置します。名前、メールアドレス、問い合わせ内容の3項目があれば十分です。自動返信メールの設定も忘れずに行いましょう。
Step5:コンテンツを入力・編集する
ページの枠組みができたら、実際の内容を入れていきます。
効果的な文章の書き方
難しい専門用語は避け、中学生でも理解できる平易な文章を心がけます。一文は短く、要点を明確に。「私たちは〜」ではなく「あなたは〜」という視点で書くと、読者に響きやすくなります。
SEO(検索エンジン最適化)を意識し、キーワードを自然に含めることも大切です。
画像の選び方と配置のコツ
画像は文章の3倍の情報量があるといわれています。自社で撮影した写真が理想ですが、難しい場合は無料の素材サイトを活用しましょう。人物が写っている写真を使うと、親しみやすさが増します。
画像はWebサイトの読み込み速度に影響するため、適切なサイズに圧縮してからアップロードしましょう。多くのサービスでは自動で最適化されますが、手動で調整することも可能です。
Step6:スマホ表示を確認・調整する
パソコンで作成したサイトも、必ずスマートフォンでの表示を確認します。文字が小さすぎないか、ボタンは押しやすいか、画像は見切れていないかをチェック。プレビュー機能を使えば、実際の表示を確認しながら調整できます。
Step7:公開前の最終チェックリスト
誤字脱字はないか、リンクは正しく機能するか、フォームは正常に送信されるか。これらを一つずつ確認します。可能であれば、家族や友人に見てもらい、第三者の意見も聞いてみましょう。問題がなければ、いよいよ公開です。
サイト作成後に必ず行うべき5つの設定
サイトを公開したら終わりではありません。より多くの人に見てもらい、成果を上げるために必要な設定があります。
1.Google Analytics(アクセス解析)の導入
どれくらいの人がサイトを見ているか、どのページが人気かを知るために、Google Analyticsを導入します。無料で使える高機能な分析ツールで、訪問者の行動を詳しく把握できます。設定は少し複雑ですが、各サービスのヘルプページに手順が載っているので参考にしてください。
2.Search Console(検索順位確認)の設定
Googleの検索結果に表示されるようにするため、Search Consoleに登録します。どんなキーワードで検索されているか、検索順位は何位かなどが分かります。サイトマップを送信することで、Googleにサイトの存在を知らせることができます。
3.SNS連携の設定
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)との連携設定を行います。サイトの更新情報を自動でSNSに投稿したり、SNSのフォローボタンを設置したりできます。特に個人事業主の方は、SNSとの連携が集客の要となることが多いです。
4.お問い合わせフォームのテスト送信
フォームが正常に機能するか、必ずテスト送信を行います。自分宛てに送信し、メールが届くか確認しましょう。迷惑メールフォルダに入ってしまうこともあるので、その点も確認が必要です。
5.バックアップ設定の確認
万が一のトラブルに備えて、バックアップの設定を確認します。多くのサービスで自動バックアップ機能がありますが、手動でもバックアップを取る習慣をつけると安心です。特に大きな更新をする前は、必ずバックアップを取りましょう。
簡単に作ったサイトを成功させるための運用ポイント
サイトは作って終わりではなく、継続的な運用が重要になります。ここでは、効果的な運用方法について解説します。
定期的な更新の重要性と方法
検索エンジンは、定期的に更新されているサイトを高く評価します。週に1回でも良いので、新しい情報を追加しましょう。ブログ記事の投稿、お客様の声の追加、商品情報の更新など、小さな更新でも効果があります。
SEO対策の基本(タイトル、見出し、メタディスクリプション)
各ページのタイトルには、検索されやすいキーワードを含めます。見出しも階層構造を意識して設定し、メタディスクリプション(検索結果に表示される説明文)も魅力的に書きましょう。これらの基本を押さえるだけで、検索順位は改善されます。
ページ表示速度の改善方法
サイトの表示が遅いと、訪問者はすぐに離脱してしまいます。画像のファイルサイズを小さくする、不要なプラグインを削除する、キャッシュ機能を活用するなどの対策を行いましょう。Google PageSpeed Insightsという無料ツールで、速度をチェックできます。
モバイルファーストインデックスを意識し、スマートフォンでの表示速度が特に重要です。
コンバージョン率を上げる工夫
サイトの目的(問い合わせ、購入など)を達成する割合を高めるには、導線の改善が重要です。目立つ場所にボタンを配置する、フォームの項目を減らす、信頼性を示す情報を追加するなど、小さな改善の積み重ねが成果につながります。
よくある失敗例と対処法
初心者が陥りやすい失敗パターンと、その対処法をご紹介します。事前に知っておくことで、同じ失敗を避けることができるでしょう。
デザインにこだわりすぎて完成しない
完璧を求めるあまり、いつまでも公開できない方が多くいます。まずは70%の完成度で公開し、運用しながら改善していく方が効果的です。実際の訪問者の反応を見ながら調整する方が、的確な改善ができます。
無料プランの制限で後悔する
無料プランは手軽に始められますが、独自ドメインが使えない、広告が表示されるなどの制限があります。ビジネス利用なら最初から有料プランを選ぶか、早めに切り替えることをおすすめします。毎月少額の投資で、プロフェッショナルな印象を与えられます。
モバイル対応を軽視してしまう
パソコンでの見た目ばかり気にして、スマホ表示を確認しない方がいます。しかし実際の訪問者の多くはスマホから閲覧しているため、モバイルファーストで考えることが大切です。作成中も定期的にスマホでチェックする習慣をつけましょう。
更新が続かない理由と解決策
最初は張り切って更新していても、徐々に頻度が下がってしまうことがあります。原因は「完璧な記事を書かなければ」というプレッシャーです。短くても良いので定期的に更新する、更新スケジュールを決めておく、外注を活用するなどの方法で継続しやすくなります。
プロに依頼する場合との比較
ここまで自作する方法を解説してきましたが、プロに依頼する選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
制作会社に依頼するメリット・デメリット
プロに依頼する最大のメリットは、高品質なサイトを制作してくれることです。デザイン性、機能性、SEO対策など、すべてにおいてプロフェッショナルな仕上がりが期待できます。また、自分の時間を本業に集中できることも大きな利点です。
デメリットは費用の高さと、更新の手間です。制作費は30万円から100万円以上かかることも珍しくありません。また、ちょっとした修正でも制作会社に依頼する必要があり、追加費用が発生します。
費用相場の比較(自作vs外注)
自作の場合、有料プランを使っても年間1〜3万円程度で運用できます。一方、制作会社に依頼すると初期費用だけで30万円以上、月額保守費用も1〜3万円かかることが一般的です。予算に余裕がない場合は、まず自作で始めて、売上が安定してから外注を検討するのも一つの方法です。
ハイブリッド型の選択肢(一部外注)
すべてを自作するか、すべてを外注するかの二択ではありません。基本的な部分は自分で作り、デザインや高度な機能だけプロに依頼する方法もあります。たとえば、ロゴデザインだけデザイナーに依頼する、SEO対策だけコンサルタントに相談するなど、予算に応じて使い分けることができます。
今すぐサイトを作り始めよう
サイトは育てるもので、最初から完璧を目指す必要はありません。月に一度は分析データを確認し、改善点を見つけて実行する習慣をつけましょう。自作に挑戦してみてやはり難しいと感じたら、プロのサポートを検討してください。
最近は、初心者向けのサポートサービスも充実しています。ホームページできるくんのような、手頃な価格で質の高いサイトを提供するサービスもあります。大切なことは、一人で悩まずに適切なサポートを受けることです。
サイト作成は、もはや特別なスキルを持つ人だけのものではありません。この記事を参考に、ぜひあなたも自分のサイトを立ち上げてみてください。最初の一歩を踏み出せば、思っているより簡単に実現できるはずです。
\月額1,900円〜プロのデザイナーが高品質のホームページを制作・運用 | ホームページできるくん/